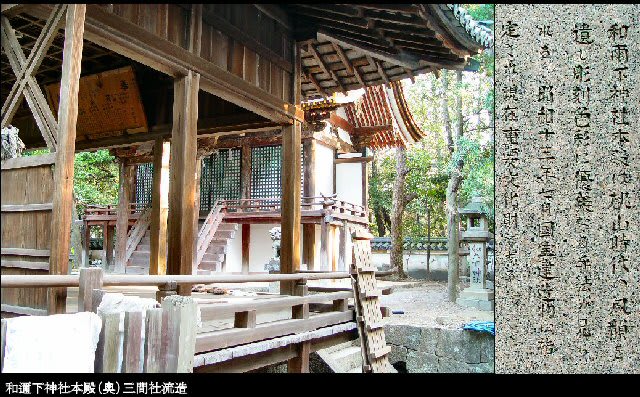島津氏初代忠久(?-1227)が拠点としたと伝えられる「木牟礼(きのむれ)城館跡」を含む中郡遺跡群(同市野田町下名中郡)で、鎌倉時代(12~14世紀)の堀跡(長さ20m、幅7~8m、深さ2.5m)や掘立柱建物跡・竪穴建物跡計9棟、中国・景徳鎮製の極めて希少な青白磁の水差し「竜首水注(りゅうしゅすいちゅう)」が出土していたことが分かった。
島津家発祥の伝承地での発見で、謎の島津氏の南九州支配の始まりとの関係が注目されそうだ。
中郡遺跡群からは、縄文時代と中世の遺構・遺物が出土している。昨年11月7日に現地説明会が行われており、その時には既に竜首水注ほか青磁や白磁、青白磁などの碗が出土していたようである。
[参考:2009.1.4南日本新聞、鹿児島県立埋蔵文化財HP]
関連のニュース・情報
2008.11.19 喜界町・城久遺跡群 石鍋片に中世の文字
2008.9.14 志布志市大崎町・天神段遺跡
島津家発祥の伝承地での発見で、謎の島津氏の南九州支配の始まりとの関係が注目されそうだ。
中郡遺跡群からは、縄文時代と中世の遺構・遺物が出土している。昨年11月7日に現地説明会が行われており、その時には既に竜首水注ほか青磁や白磁、青白磁などの碗が出土していたようである。
[参考:2009.1.4南日本新聞、鹿児島県立埋蔵文化財HP]
関連のニュース・情報
2008.11.19 喜界町・城久遺跡群 石鍋片に中世の文字
2008.9.14 志布志市大崎町・天神段遺跡