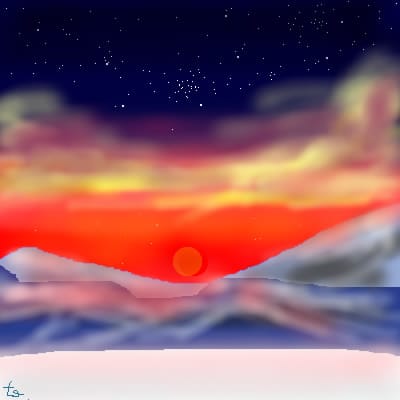いつも想いを、

第30話 誓夜act.1―side story「陽はまた昇る」
ときおり雪が、おだやかに頬を撫でる。
明日はホワイト・クリスマスになるかな。白く雪ふる夜空を見上げて英二は微笑んだ。
山の冷気は凍てついて、けれど顔を照らす焚火は温かい。のんびり雪染まる河原を眺めながら英二は酒を啜った。
「ほら、宮田。焼けたよ、腹減ってるだろ?食いなよ」
雪を眺めていた視界に、串うった鶏肉が差し出された。鶏に塗られた柚子味噌の焼かれた香が芳ばしい。
串を持つ白い手を振り向くと、細い目が愉しげに笑っていた。
そのもう一方の手には酒のコップを持って、国村はご機嫌でいる。
ほんと酒で山ならご機嫌だな、英二は笑って串を受取った。
「うん、ありがとう。でもさ、国村?ほんと、大丈夫なのかよ?」
「なにが?」
英二の問いかけに訊き返しながら、国村は焚火の具合を見ている。
そんな様子を眺めながら、ちょっと呆れて英二は尋ねた。
「あのさ、国村?今日はクリスマス・イヴで土曜日だ。
そして今日は国村も美代さんも休みだろ?それなのにさ、俺達と河原でいつも通りにこんな、呑んでていいの?」
クリスマス・イヴで土曜日、だから美代と国村は一緒にいる。
元々は今日の英二が非番で国村が日勤だった、それを英二が周太の休みに合わせたくてシフト交換した。
そして藤岡も勤務日だった、だから普通に夕飯を寮で英二と藤岡は食べるつもりでいた。
けれど勤務を終えて吉村医師とコーヒーを淹れていたら、国村が掴まえた藤岡と一緒に現れた。
「あ、宮田。コーヒー3人前追加ね?」
「…国村、おまえ、クリスマス・イヴに休みの癖に、なにやってんの?」
そう呆れかえった英二の前に、きれいな明るい瞳で美代が「こんばんわ」と診察室の入口から微笑んだ。
それから5人でコーヒーを飲むと、いつもの河原に藤岡も英二も拉致されて飲み会が始まった。
そんなわけで英二は今、焚火の前に座っている。
ほんとに大丈夫か?そう首傾げる英二に、国村は底抜けに明るい目で笑った。
「うん、楽しいだろ?美代もさ、楽しい方が好きなんだよね」
相変わらず国村は、機嫌良く酒を飲みながら料理の具合を見ている。
ちょっとため息ついて英二は、河原のむこうを振り返った。
その河原縁で藤岡と美代が雪合戦に喜んでいる。そんな様子は可愛らしく無邪気で、楽しげな良い光景だと思う。
でも美代は本当に良いのだろうか?女性と付き合った数だけは多い英二としては、ちょっと心配になってしまう。
そんな英二の横で国村は、焚火で炙った鶏肉と野菜の串を確認して笑った。
「うん、焼けてるな、どれも。宮田、ちょっと2人呼んできてよ?飯出来たよってさ」
「あ、?うん」
言われて英二は串を地面に挿しコップを地面に置いて立ちあがった。
いくらか積った夜の雪の中で、藤岡と美代は頬赤くして笑っている。本当に楽しそうだな、微笑んで英二は声をかけた。
「飯が出来たって、国村が呼んでるよ?」
「お、うれしいな。俺さ、腹減ったなって思ってたんだ」
からっと笑って藤岡は、器用に雪を踏んで走っていってしまった。
藤岡は宮城出身で雪馴れしているから、いつも雪山でも上手に走るように歩く。
そういうとき英二はすこし羨ましい。いいなと眺めていると、美代が笑いかけてくれた。
「宮田くん、今夜もちゃんと楽しい?」
「うん、楽しいよ。でも俺はね、周太がいないとさ、やっぱ寂しい」
素直に答えて英二は微笑んだ。
美代も素直に頷いて、笑って言ってくれた。
「そうだね、湯原くんも一緒なら良かったのにね。私も会いたかったな?」
「うん、ありがとう。周太もね、美代さんには会いたいと思うよ?話すの楽しいって言っていたから」
「そう?…うん、うれしいな。私もね、湯原くんと話すの好きよ」
ゆっくり歩きながら、きれいな明るい瞳で美代が笑ってくれる。
その瞳を見ながら英二は、すこし遠慮がちに訊いてみた。
「今日はクリスマス・イヴだよね、恋人同士で過ごす人が多い。でも美代さんは今日、こんなで良かったの?」
訊かれて美代が可笑しそうに笑った。
そして英二の腕をそっと掴むと、背伸びするように英二にささやいた。
「あのね、光ちゃんと毎年こんな感じでイヴしているの。でもね、二人でちょっと寂しかったのよ?」
「どうして寂しいの?」
微笑んで英二は美代に尋ねた。
それを見上げる明るい瞳がすこし寂しげに微笑んで、美代はそっと口を開いた。
「うん…本当はずっとね、光ちゃんのお父さんとお母さんが、私達にこうしてクリスマス・イヴを楽しませてくれたのよ。
だから亡くなってからはね、光ちゃんと私は、ずっと2人だけでしてきたの。それってやっぱりね、ちょっと寂しかった」
そう言って美代は、きれいに温かく笑ってくれた。
その笑顔と国村の想いが英二の心にふれて、切なくてどこか温かい。おだやかに微笑んで、英二は訊いてみた。
「国村のご両親だと、楽しかったろうな」
「うん、すごくね楽しかった。いつも毎年ね、楽しみだったの私。私ね、おじさんも、おばさんも、大好きなの」
懐かしげに微笑んで、きれいな瞳が温かい。
この娘は本当に国村と似合っているな、なんだか嬉しくて英二は微笑んだ。
「そんな大切な想い出の夜にさ、俺と藤岡が加わって大丈夫なの?」
「あのね、一緒できて本当に楽しいよ?私はね、うれしい。こういうのって良いね?」
明るい瞳が本当にうれしげに笑ってくれる。
こんな純粋な笑顔の女性は今時少ないだろう、こんなひとが自分の大切なパートナーの相手でいる。
きっと本当に国村と美代は運命の相手なのだろう、微笑んで英二は相槌を打った。
「そう?」
「うん、そう。だってね、光ちゃんがね、こんなに寛いで友達と話すのって、見たこと無いから」
すこし意外で英二は、美代の顔を見つめた。
いつも国村は朗らかで愉快で楽しい。だから山岳救助隊でも寮でも警察署でも、奥多摩の街でも人に囲まれている。
つい3日前だって、英二の雪山装備を選んだアウトドア用品店の主人たちと楽しげに話していた。
その様子は寛いでいないようには見えない。どういうことだろう?英二は美代に訊いてみた。
「あいつ、いつも、こんなじゃないの?」
「うん、ちょっと違うよ?たぶん宮田くんと一緒だと、どこでもこんなだと思うけど」
英二を見上げて美代は微笑んでいる。
その話を訊きたいな?そんなふうに英二が見つめると、美代は軽く頷いた。
「光ちゃんはね、友達たくさんいるのよ。でもね、ちょっと一線を引いているなって。
光ちゃんは生まれつき山ヤでしょう?だから山ヤの気持ちが解らない相手だと、本当には話せないんだと思う」
「うん。…それって、なんか俺もわかるな」
山ヤには山ヤのルールがある、そして山ヤ同士の紐帯がある。
それはたとえ未知の相手でも山ヤが遭難すれば、近くにいる山ヤはすぐ救助に向かう。
そんな生命を懸けた連携が山ヤにはある。
そうした山ヤの想いが解らないと国村には難しいだろう。英二が頷くと美代も頷いた。
「でしょう?だからね、高校も山岳部は入らなかったの。
同じ山好きだからこそ逆に自分とのペースの違いが解るみたい。
それに光ちゃん生まれつき『山づくし』で生粋の山ヤでしょ?そんな人自体少ないし、高校生なら余計に、ね?」
「うん、そうだね」
国村は田中の四十九日の夜に「自分の山のペースを乱されたくないだろ?俺は我儘だからさ」と言っている。
そして国村は高校1年の夏にマッターホルン北壁を踏破した。
そういう国村が、普通の高校生レベルに合わせる事は難しいだろう。
加えて生粋の山ヤだからルールブックも「山の掟」が基盤でいる。
そんな国村が「山」を話題に本当に話せるのは、大人の山ヤだけだったろう。
なるほどなと納得していると、微笑んで美代が続けた。
「それにね、光ちゃんて律儀に年の差とか気にするところがあるの。
国村の家は古い家だから、昔ながらの年齢の序列とか大事にするから、かな?
だから、本音は同じ年じゃないと話し難いみたい。
それでね、山岳救助隊で山ヤの先輩はたくさんできたけど、本当に遠慮なく話せる相手は見つからなかったの」
同じ年だからタメぐちで。そう言って国村は、英二と藤岡と話すようになった。
そんな国村は高卒任官だから英二達の4年先輩になる。
だから序列の厳しい警察世界では、当然敬語を遣う相手だった。
けれど国村は冗談じゃないねと笑い飛ばすと、タメぐちで話せと断言した。そうして話して親しくなる基礎が積まれている。
そうだったなと思いだしながら、英二は頷いた。
「ああ、国村はそうだね。だから俺や藤岡とは仲良くしやすかったかな」
「うん。同じ年で山ヤだから、ね?だから、光ちゃんにそういう友達が出来てね、私うれしかったの」
河原の雪と雪明りの御岳山を眺めながら、美代は微笑んだ。
美代はずっと国村と一緒に育っている、そんな彼女には国村の気持ちがよく解るのだろう。
こういう存在は国村にとって大切で宝物だろうな、英二は美代に微笑みかけた。
そんな美代は英二の目に笑いかけてくれる、そして口を開いた。
「でも宮田くんはね、やっぱりきっと特別よ。生涯のアイザイレンパートナーだから、ね?」
生涯のアイザイレンパートナー、それは山ヤとして大切な意味がある。
生涯をザイルで結びあい、生命を互いに預け合う。そしてどんな過酷な状況でも、お互いだけは見捨てない。
そんなふうに互いの運命と生命を結んで、責任と義務と権利を背負い合うことになる。
美代は「生涯のアイザイレンパートナー」として英二が現れたことを、どう受けとめているのだろう?
それを訊いてみたいと英二は想っていた。美代は国村の運命の相手で、そして美代と周太はどこか似ている。
きっと美代と周太の想いは重なるものがあるだろう、そんな彼女の想いを英二は聴きたい。
すこし微笑んで英二は美代に訊いた。
「美代さん、俺のこと聴いたとき、どんなふうに想った?」
「うん?宮田くんが光ちゃんの生涯のアイザイレンパートナーだってこと?」
「そう、」
頷いて英二は目だけで訊いた、あなたに俺の存在はどう映るの?
そんな英二の目を真直ぐ見つめて美代は、きれいに笑って言った。
「やっと出会えたのね?よかった、本当におめでとう。って想ったよ?」
明るい瞳が心の底から幸せそうに笑ってくれる。
わたしにとっても、あなたの存在がうれしいのよ?そんな目で美代は英二を見つめてくれている。
こんなふうに見つめて笑ってくれて、英二は嬉しかった。うれしくて微笑んで、英二は訊いてみた。
「美代さんも、俺のこと待っててくれたの?」
「うん、そうよ?」
きれいに笑って美代は頷いた。
そして英二を見つめたまま、言葉をゆっくりと続けてくれた。
「光ちゃんにアイザイレンパートナーが居てくれたら、光ちゃんは山でも1人じゃないでしょう?
2人なら援け合える、そして光ちゃんが望むままに高い高い山にも登って行ける。
そうして光ちゃんの夢をね、叶えて欲しい。
それは若いうちから始めないと難しい夢でしょう?だからね、そういうひとに早く現れてほしいって想っていたの」
真直ぐな実直な目が英二を見つめてくれる。
そしてきれいな明るい目が笑って、英二に言った。
「でも光ちゃんって気難しいから、なかなか心を開かないでしょ?
そんな光ちゃんはアイザイレンパートナーには、体格や技術だけじゃなくて『ホントの友達』まで求めていたのね。
ほんとに信頼して寛げる相手じゃないと、自分が望むような過酷な山ではザイルを繋げない。そう想っていたのかな?」
田中の四十九日の夜に国村が言っていたこと。
―俺のペースに合わせられて、しかも俺と体格が同じ奴じゃないとね、俺はパートナーにしたくなかったんだ
アイザイレンパートナーは一緒にいて楽なやつが良い。だって過酷な状況下で一蓮托生やらなきゃないからね
それと同じことを美代は言っている。そして心から国村の無事と夢を祈って、英二の存在を喜んでくれている。
けれど英二には抱えるものが多い、それも美代は大丈夫なのだろうか。思ったままに英二は訊いた。
「美代さん、俺はね?…周太を愛しているよ。そして周太の事情も全部背負っている、それは危険も多い事情なんだ」
きれいな瞳が、話す英二を静かに見つめてくれる。
やっぱりどこか美代は周太と似ている、そんな想いに微笑んで英二は続けた。
「それでも国村はね、俺を生涯のアイザイレンパートナーに選んだんだ。あいつね、こう言ったよ、
『最高峰ほど危険な場所が世界のどこにある?
そんな最高の危険へと俺は、アイザイレンパートナーとして宮田を惹きこんだ。
これからの人生をより危険に惹きこんでいくのは俺の方だ。だから宮田の危険に俺が巻き込まれるくらいで調度いい』
そんなふうに国村はね、俺を選んでくれたんだ。
だからね、美代さん。俺はね、あいつにリスクを背負わせて、あいつの生涯のアイザイレンパートナーになったんだ」
それでもいいの?
そんなふうに英二は目だけで、きれいな瞳へと訊いた。
きれいな瞳は静かに英二を見上げてくれている。それは真直ぐに穏やかで静かな眼差しだった。
どこかそれは周太によく似ていて、英二は美代の瞳に周太の黒目がちの瞳を見つめていた。
「うん。大丈夫よ、宮田くん?」
美代の瞳が微笑んだ。
そして美代は、きれいな明るい瞳のままで英二に言った。
「光ちゃんの言う通りだと、私も想うな?
だって光ちゃんの夢って、ほんとうに危険よね?だから光ちゃんが言う通り、それで調度いいのよ、きっと」
受けとめてくれた。
うれしくて申し訳なくて、そして幸せで英二は微笑んだ。
「うん…ありがとう、美代さん」
「ううん、こっちこそよ?光ちゃんの相手を一生するなんて、きっと大変ね?がんばってね、宮田くん」
軽やかに笑って美代が言ってくれる。
このひとは本当に国村に似合っているんだ、それが英二には国村の為に嬉しかった。
そしてもう一つ訊きたくて、英二は口を開いた。
「美代さんはね、そんな危険に国村が立つことは大丈夫なの?」
「そうね、ほんとうに危険よね?だって8,000mの高さから落っこちたら、ほんと大変だもの、」
からり明るい調子で美代が微笑んだ。なんだか少し国村にも似た口調に、可笑しくて英二は少し笑った。
きっとずっと一緒に育ったから話すトーンも似てしまったのだろう。そんな2人の繋がりが少し英二は羨ましい。
いいなと見つめる英二に、続けて美代は話してくれた。
「でもね、最高峰に立つことは、ほんとうに楽しいって想うの。
だって世界でいちばん高いところから、世界を見渡すのでしょう?
そこに自分の大好きな人が立って、自分を想ってくれる。それってきっと、世界一に愉快なことよ、でしょう?」
「うん、そうだな。世界一だね、」
頷いて英二は微笑んだ。
自分がいつも想うこと「最高峰から周太に想いを届けたい」
それと同じように国村も、美代に話してきたのだろう。きっと小さい頃からずっと。
この2人には幸せになってほしい、そんな想いが英二の心に温かい。そんな想いのままに英二は言った。
「美代さん。俺はね、国村の生涯のアイザイレンパートナーだ。だから約束するよ、あいつを必ず支えて守ってみせる。
どんな最高峰に立った時でも、ザイルで繋いで守るよ。そして世界一に愉快なことを、あいつに一生ね、させるよ」
きれいな瞳が花咲くように笑ってくれた。
ときおりふる雪の中で美代は、きれいな明るい笑顔で静かに頷いた。
「うん、約束ね?ありがとう、そしてよろしくね」
自分の愛するひとに似た、きれいな瞳のひと。
そのひとの願いも背負ったな、そんな責任感と温かな想いが英二はうれしかった。
こうして背負うごとにきっと自分は強くなれる、賢く深くなっていける。
そうして周太の背負う哀しい運命だって、自分は明るい方へと変えてみせるだろう。
なぜなら背負う責任が、また誰かに援けてもらえる権利も与えてくれると知っている。
「こちらこそ、よろしくね、美代さん」
きれいに笑って英二は頷いた。
頷いていま背負ったのは、最高のクライマーの運命とその相手の想い。
それは大きな責任がある「最高のクライマー」は世界中の山ヤの夢で、そして自分の夢だから。
けれど、こんな大きな責任を背負った自分は、きっと大きな権利も得ただろう。
そう既に最高のクライマー自身が自分に言ってくれている、だから周太の運命すらも自分は変えられる。
だって最高のクライマーはきっと、世界最高の危険地帯から愛される運命の男。
そんな世界最高の危険にすら愛される男から、自分は望まれてその運命の横に並んだ。
そんな世界最高の危険の前では、きっと警察機構の危険など小さく儚いもの。
だからもう、自分はきっと周太の危険を越えられる。そう信じて越えていくだろう。
…周太、俺はね、最高の危険地帯に立つことをさ、選んだよ?
そんな想いに英二は空を見上げた。
ふる雪を生む雲がゆるやかに透明な紺青をながれていく。
その合間からふる星の輝きは、高く遠いけれど明りは静かに山へとふっていた。
「いま、湯原くんのことを想ってる?」
美代の声に英二はゆっくり横へと視線をおろした。
おろした視線のなかで美代は微笑んだ。そして、きれいな封筒を美代は差出してくれた。
「宮田くん。あのね、これを湯原くんに渡してくれる?明日は会うのでしょ?」
「うん、そうなんだ。明日はね、やっと周太に逢えるんだ」
そう、やっと逢える。
微笑んで英二は、登山ジャケットの胸ポケットから手帳を出してはさみこんだ。
そんな英二を見て美代は、微笑んで教えてくれた。
「あのね、先月に会った時の約束なの。味噌のレシピよ?あと、季節のお便り」
「あ、味噌ね?周太も言っていたよ。ありがとう、きっと喜ぶよ」
そんなふうに話しながら歩いて焚火へ戻ると、一升瓶はもう半分ほど空いていた。
その瓶から酒を注がれる藤岡が、いつも以上に笑い転げている。
それを見て美代が国村の隣に立った。
「光ちゃん?すごい呑ませちゃったんでしょ、藤岡くんちょっとハイテンション過ぎだよ」
「うん?そうだったかな。でも俺、無理強いなんかしてないけど?」
飄々と国村が笑っている。
その前では藤岡が人の好い顔のままで、真赤な顔をほころばせていた。
だいじょうぶかな?英二は藤岡の顔を覗きこんだ。
「藤岡、だいじょうぶ?おまえ、何杯呑んだんだよ?」
訊かれた藤岡は相変わらず笑っている。
もとが良い酒だから楽しげだけれど、まだ飲み会は始まって1時間程度だった。
そんな短時間で藤岡がこうも酔うなんて、どれだけハイペースなのだろう?
すこし心配になる英二に、機嫌よく赤い顔の藤岡が言った。
「えっと?そうだなぁ、2杯かなぁ?うん、そうそう、2杯だよ」
「2杯?」
それはおかしい、英二は不審に思った。
藤岡は笑い上戸で赤くなりやすい、けれど東北人らしく酒は強い。
そしていつもの飲み会でも、日本酒2杯程度でこうはならない。一升瓶の2/3位は軽いはずだ。
なにかおかしいな?英二は国村の方を見、その足許に目がとまった。
「国村。その瓶ってさ、中身なに?」
訊かれた国村の細い目が、愉快げに細められた。
流木に座っている国村の足許には、1本の五合瓶が置かれている。
それを見る美代の瞳が少し大きくなった。
「光ちゃん、それって自分で作ったお酒でしょ?」
「うん、そうだよ?」
得意気に細い目が笑っている。
そんな国村を見て、美代が呆れたように笑った。
「それ飲ましちゃったんだ、藤岡くんに?じゃあ酔っ払っちゃうわよね」
「うん、藤岡が呑んでみたいって言うからさ、ご馳走しただけだけど?」
自分で酒まで作るんだ?でも酒造法とかあるだろうに。法学部出身の英二は少し心配になった。
けれど国村は農業高校の出身で農家、学校や家で習ったのだろう。それに酒造法には例外がある。
ちょっとおもしろそうで英二は訊いてみた。
「おまえさ、その酒はお神酒用なんだろ?」
「そ。収穫祭用のさ、濁酒の余りだよ。俺ん家の米で造ったんだ」
収穫された米を神に捧げるとき、濁酒を作って供えて翌年の豊穣を祈願する伝統がある。
そうした宗教的行事における濁酒の製造と飲用は、濁酒の製造免許を受ければ製造可能とされていた。
その場合は境内など神社の一定の敷地内で飲用が許可されている。
そして神社の濁酒など販売を目的とせず、伝統文化的価値の大きいものは酒税法の適用外もある。
たぶんそういう事なのだろうな、英二は訊いてみた。
「じゃあさ、この河原って神社の敷地なんだ?」
「そうだよ。ウチの氏神様の境内地なんだよね、俺、ちゃんと濁酒の製造免許も持ってるしさ。だから合法、だろ?」
やっぱり免許持ってるんだな。予想通りが可笑しくて英二は笑った。
きっと酒好きな国村だから、農業高校の授業でも熱心に勉強したのだろう。
そんな国村は突き詰めるタイプだから、免許取得まで考えて当然だった。
ちょっと興味のままに英二は質問した。
「濁酒製造免許の取得はさ、たしか農業と民宿や農家レストランとかの兼業だよな?」
「そ。ウチはさ、ばあちゃんが週末は農家レストランやってるんだよね。それで俺、免許を取れたんだ」
国村の祖母の手料理は、飲み会の差入れで英二も何度かご馳走になっている。
素朴な食材だけれど味がいいなといつも思っていた。
「そっか。おばあさんの差入れ、いつも旨いけどプロなんだ」
「だろ?ばあちゃんは料理名人なんだよね。それでさ。JAとかに提案されてね、店始めたんだ」
なるほどねと英二は頷いた、けれど疑問が残ってしまう。
濁酒のアルコール度数は普通の清酒と同程度14~17%になる。
それなのに2杯で藤岡は出来あがってしまった。どういうことだろう?英二は首を傾げた。
「なあ、国村?普通の濁酒のアルコール度数はさ、いつもの酒と変わらないはずだろ?
それなのに2杯で藤岡が酔っぱらうなんて変だ。おまえの濁酒って、度数いくつなんだよ?」
言われて国村の細い目が、すっと細まった。その目がさも愉快げに笑っている。
その隣で美代が「仕方ないね?」と少し困った顔で微笑みかけくれた。
「光ちゃんって、研究とかも器用なのよね。それで農業高校の時にちょっと工夫を、ね?」
「なんか、聴くのが怖くなってくるね?」
英二は笑った。きっと、とんでもない度数の酒を合法的に醸造しているのだろう。
そしてなんだか可笑しかった。だって今日はクリスマス・イヴだ、世間はシャンパンで華やかなことだろう。
けれど自分は河原で、友人が作った濁酒の話に笑っている。それが英二はなんだか愉快で楽しかった。
12月24日クリスマス・イヴの夜。毎年ずっと女の人と過ごしていた、そして毎年違う人だった。
それなりに楽しくて、それなりにいつも傷ついていた。いつも自分は作り笑いばかりだったから。
でも今年はこんなふうに、大好きな友人や仲間と心から笑っている。そして明日は心から愛するひとに逢える。
そんな今が幸せで英二は嬉しかった。
うれしくて微笑む英二に、クライマーウォッチを示して国村が笑った。
「ほら宮田、21時前だよ?」
「うん、ありがとう。じゃあ、ちょっとごめんな?」
立ち上がると英二は携帯を開いて、電波状況が良い場所まで歩いた。
いつも英二は周太に21時に電話する、そして周太が当番勤務のときは周太から架ける。
今日の周太は当番勤務、けれど今夜はクリスマス・イヴだから英二から架けたかった。
アンテナ3本が立つ場所に来ると、英二は発信履歴から電話を繋いだ。
「…はい、」
コール0ですぐ繋がってくれる、きっと待っていてくれた。
雪ゆるやかに舞う中で、きれいに英二は笑った。
「周太、待っててくれた?」
すこし気恥ずかしげな気配。
きっと自分が架ける当番勤務だけれど、今日は英二から架けてほしかったのだろう。
きっと華やかなクリスマスの街で、すこし周太は寂しくイルミネーションを見つめていた。
だから自分を待ってくれていた、そんな想いが気恥ずかしげな気配に伝わってしまう。
「…ん、待ってた。今夜はね、英二から声、かけてほしかった。…わがまま、かな?」
ほら、やっぱりそうだ。
こんな遠慮がちで初々しい、そんな自分の運命のひと。
「わがまま、うれしいよ?」
「そう、なの?」
落ち着いた声、ゆるやかな独特のトーン。
このトーンは素顔の周太でいる時だけだと知っている。
そんな1つずつがうれしい、微笑んで英二は答えた。
「そうだよ周太?俺はね、周太の我儘たくさん聴きたい。ね、周太?もっとさ、我儘いっぱい言ってよ?」
「…ん、…わがままって、なんて言ったらいいの?」
英二は笑ってしまった。
こんなふうに周太は、自分の我儘すらも思いつけない。
そんな奥ゆかしさが可愛くて、そんな不器用さが寂しかった生立ちを偲ばせ切なくて。
だから余計に幸せにしたくなる、きれいに笑って英二は言った。
「周太がね、俺にして欲しいこと。全部そのまま言ってくれたら良い。
そして少しはさ、周太のお願いで俺を困らせてよ?そういう周太の『おねだり』俺は聴きたいな」
「…おねだり、って…」
そう、たくさんお願いしてほしい。
困らせられるほどの『おねだり』で自分を繋ぎとめて欲しい。
そうして周太からだって、自分を独占してくれたらいいのに。
そんな想いに英二は、そっと周太に訊いた。
「ね、周太。俺にね、少しでも早く、あいたい?」
繋いだ電話の向こう、微笑みの気配が伝わってくる。
そして幸せそうな想いがそっと、微かな吐息で英二の耳に返響した。
「ん、…早くね、あいたい」
さあ、この『おねだり』は、どんなふうに叶えよう?
(to be continued)
blogramランキング参加中!
ネット小説ランキング
http://www.webstation.jp/syousetu/rank.cgi?mode=r_link&id=5955

 にほんブログ村
にほんブログ村

第30話 誓夜act.1―side story「陽はまた昇る」
ときおり雪が、おだやかに頬を撫でる。
明日はホワイト・クリスマスになるかな。白く雪ふる夜空を見上げて英二は微笑んだ。
山の冷気は凍てついて、けれど顔を照らす焚火は温かい。のんびり雪染まる河原を眺めながら英二は酒を啜った。
「ほら、宮田。焼けたよ、腹減ってるだろ?食いなよ」
雪を眺めていた視界に、串うった鶏肉が差し出された。鶏に塗られた柚子味噌の焼かれた香が芳ばしい。
串を持つ白い手を振り向くと、細い目が愉しげに笑っていた。
そのもう一方の手には酒のコップを持って、国村はご機嫌でいる。
ほんと酒で山ならご機嫌だな、英二は笑って串を受取った。
「うん、ありがとう。でもさ、国村?ほんと、大丈夫なのかよ?」
「なにが?」
英二の問いかけに訊き返しながら、国村は焚火の具合を見ている。
そんな様子を眺めながら、ちょっと呆れて英二は尋ねた。
「あのさ、国村?今日はクリスマス・イヴで土曜日だ。
そして今日は国村も美代さんも休みだろ?それなのにさ、俺達と河原でいつも通りにこんな、呑んでていいの?」
クリスマス・イヴで土曜日、だから美代と国村は一緒にいる。
元々は今日の英二が非番で国村が日勤だった、それを英二が周太の休みに合わせたくてシフト交換した。
そして藤岡も勤務日だった、だから普通に夕飯を寮で英二と藤岡は食べるつもりでいた。
けれど勤務を終えて吉村医師とコーヒーを淹れていたら、国村が掴まえた藤岡と一緒に現れた。
「あ、宮田。コーヒー3人前追加ね?」
「…国村、おまえ、クリスマス・イヴに休みの癖に、なにやってんの?」
そう呆れかえった英二の前に、きれいな明るい瞳で美代が「こんばんわ」と診察室の入口から微笑んだ。
それから5人でコーヒーを飲むと、いつもの河原に藤岡も英二も拉致されて飲み会が始まった。
そんなわけで英二は今、焚火の前に座っている。
ほんとに大丈夫か?そう首傾げる英二に、国村は底抜けに明るい目で笑った。
「うん、楽しいだろ?美代もさ、楽しい方が好きなんだよね」
相変わらず国村は、機嫌良く酒を飲みながら料理の具合を見ている。
ちょっとため息ついて英二は、河原のむこうを振り返った。
その河原縁で藤岡と美代が雪合戦に喜んでいる。そんな様子は可愛らしく無邪気で、楽しげな良い光景だと思う。
でも美代は本当に良いのだろうか?女性と付き合った数だけは多い英二としては、ちょっと心配になってしまう。
そんな英二の横で国村は、焚火で炙った鶏肉と野菜の串を確認して笑った。
「うん、焼けてるな、どれも。宮田、ちょっと2人呼んできてよ?飯出来たよってさ」
「あ、?うん」
言われて英二は串を地面に挿しコップを地面に置いて立ちあがった。
いくらか積った夜の雪の中で、藤岡と美代は頬赤くして笑っている。本当に楽しそうだな、微笑んで英二は声をかけた。
「飯が出来たって、国村が呼んでるよ?」
「お、うれしいな。俺さ、腹減ったなって思ってたんだ」
からっと笑って藤岡は、器用に雪を踏んで走っていってしまった。
藤岡は宮城出身で雪馴れしているから、いつも雪山でも上手に走るように歩く。
そういうとき英二はすこし羨ましい。いいなと眺めていると、美代が笑いかけてくれた。
「宮田くん、今夜もちゃんと楽しい?」
「うん、楽しいよ。でも俺はね、周太がいないとさ、やっぱ寂しい」
素直に答えて英二は微笑んだ。
美代も素直に頷いて、笑って言ってくれた。
「そうだね、湯原くんも一緒なら良かったのにね。私も会いたかったな?」
「うん、ありがとう。周太もね、美代さんには会いたいと思うよ?話すの楽しいって言っていたから」
「そう?…うん、うれしいな。私もね、湯原くんと話すの好きよ」
ゆっくり歩きながら、きれいな明るい瞳で美代が笑ってくれる。
その瞳を見ながら英二は、すこし遠慮がちに訊いてみた。
「今日はクリスマス・イヴだよね、恋人同士で過ごす人が多い。でも美代さんは今日、こんなで良かったの?」
訊かれて美代が可笑しそうに笑った。
そして英二の腕をそっと掴むと、背伸びするように英二にささやいた。
「あのね、光ちゃんと毎年こんな感じでイヴしているの。でもね、二人でちょっと寂しかったのよ?」
「どうして寂しいの?」
微笑んで英二は美代に尋ねた。
それを見上げる明るい瞳がすこし寂しげに微笑んで、美代はそっと口を開いた。
「うん…本当はずっとね、光ちゃんのお父さんとお母さんが、私達にこうしてクリスマス・イヴを楽しませてくれたのよ。
だから亡くなってからはね、光ちゃんと私は、ずっと2人だけでしてきたの。それってやっぱりね、ちょっと寂しかった」
そう言って美代は、きれいに温かく笑ってくれた。
その笑顔と国村の想いが英二の心にふれて、切なくてどこか温かい。おだやかに微笑んで、英二は訊いてみた。
「国村のご両親だと、楽しかったろうな」
「うん、すごくね楽しかった。いつも毎年ね、楽しみだったの私。私ね、おじさんも、おばさんも、大好きなの」
懐かしげに微笑んで、きれいな瞳が温かい。
この娘は本当に国村と似合っているな、なんだか嬉しくて英二は微笑んだ。
「そんな大切な想い出の夜にさ、俺と藤岡が加わって大丈夫なの?」
「あのね、一緒できて本当に楽しいよ?私はね、うれしい。こういうのって良いね?」
明るい瞳が本当にうれしげに笑ってくれる。
こんな純粋な笑顔の女性は今時少ないだろう、こんなひとが自分の大切なパートナーの相手でいる。
きっと本当に国村と美代は運命の相手なのだろう、微笑んで英二は相槌を打った。
「そう?」
「うん、そう。だってね、光ちゃんがね、こんなに寛いで友達と話すのって、見たこと無いから」
すこし意外で英二は、美代の顔を見つめた。
いつも国村は朗らかで愉快で楽しい。だから山岳救助隊でも寮でも警察署でも、奥多摩の街でも人に囲まれている。
つい3日前だって、英二の雪山装備を選んだアウトドア用品店の主人たちと楽しげに話していた。
その様子は寛いでいないようには見えない。どういうことだろう?英二は美代に訊いてみた。
「あいつ、いつも、こんなじゃないの?」
「うん、ちょっと違うよ?たぶん宮田くんと一緒だと、どこでもこんなだと思うけど」
英二を見上げて美代は微笑んでいる。
その話を訊きたいな?そんなふうに英二が見つめると、美代は軽く頷いた。
「光ちゃんはね、友達たくさんいるのよ。でもね、ちょっと一線を引いているなって。
光ちゃんは生まれつき山ヤでしょう?だから山ヤの気持ちが解らない相手だと、本当には話せないんだと思う」
「うん。…それって、なんか俺もわかるな」
山ヤには山ヤのルールがある、そして山ヤ同士の紐帯がある。
それはたとえ未知の相手でも山ヤが遭難すれば、近くにいる山ヤはすぐ救助に向かう。
そんな生命を懸けた連携が山ヤにはある。
そうした山ヤの想いが解らないと国村には難しいだろう。英二が頷くと美代も頷いた。
「でしょう?だからね、高校も山岳部は入らなかったの。
同じ山好きだからこそ逆に自分とのペースの違いが解るみたい。
それに光ちゃん生まれつき『山づくし』で生粋の山ヤでしょ?そんな人自体少ないし、高校生なら余計に、ね?」
「うん、そうだね」
国村は田中の四十九日の夜に「自分の山のペースを乱されたくないだろ?俺は我儘だからさ」と言っている。
そして国村は高校1年の夏にマッターホルン北壁を踏破した。
そういう国村が、普通の高校生レベルに合わせる事は難しいだろう。
加えて生粋の山ヤだからルールブックも「山の掟」が基盤でいる。
そんな国村が「山」を話題に本当に話せるのは、大人の山ヤだけだったろう。
なるほどなと納得していると、微笑んで美代が続けた。
「それにね、光ちゃんて律儀に年の差とか気にするところがあるの。
国村の家は古い家だから、昔ながらの年齢の序列とか大事にするから、かな?
だから、本音は同じ年じゃないと話し難いみたい。
それでね、山岳救助隊で山ヤの先輩はたくさんできたけど、本当に遠慮なく話せる相手は見つからなかったの」
同じ年だからタメぐちで。そう言って国村は、英二と藤岡と話すようになった。
そんな国村は高卒任官だから英二達の4年先輩になる。
だから序列の厳しい警察世界では、当然敬語を遣う相手だった。
けれど国村は冗談じゃないねと笑い飛ばすと、タメぐちで話せと断言した。そうして話して親しくなる基礎が積まれている。
そうだったなと思いだしながら、英二は頷いた。
「ああ、国村はそうだね。だから俺や藤岡とは仲良くしやすかったかな」
「うん。同じ年で山ヤだから、ね?だから、光ちゃんにそういう友達が出来てね、私うれしかったの」
河原の雪と雪明りの御岳山を眺めながら、美代は微笑んだ。
美代はずっと国村と一緒に育っている、そんな彼女には国村の気持ちがよく解るのだろう。
こういう存在は国村にとって大切で宝物だろうな、英二は美代に微笑みかけた。
そんな美代は英二の目に笑いかけてくれる、そして口を開いた。
「でも宮田くんはね、やっぱりきっと特別よ。生涯のアイザイレンパートナーだから、ね?」
生涯のアイザイレンパートナー、それは山ヤとして大切な意味がある。
生涯をザイルで結びあい、生命を互いに預け合う。そしてどんな過酷な状況でも、お互いだけは見捨てない。
そんなふうに互いの運命と生命を結んで、責任と義務と権利を背負い合うことになる。
美代は「生涯のアイザイレンパートナー」として英二が現れたことを、どう受けとめているのだろう?
それを訊いてみたいと英二は想っていた。美代は国村の運命の相手で、そして美代と周太はどこか似ている。
きっと美代と周太の想いは重なるものがあるだろう、そんな彼女の想いを英二は聴きたい。
すこし微笑んで英二は美代に訊いた。
「美代さん、俺のこと聴いたとき、どんなふうに想った?」
「うん?宮田くんが光ちゃんの生涯のアイザイレンパートナーだってこと?」
「そう、」
頷いて英二は目だけで訊いた、あなたに俺の存在はどう映るの?
そんな英二の目を真直ぐ見つめて美代は、きれいに笑って言った。
「やっと出会えたのね?よかった、本当におめでとう。って想ったよ?」
明るい瞳が心の底から幸せそうに笑ってくれる。
わたしにとっても、あなたの存在がうれしいのよ?そんな目で美代は英二を見つめてくれている。
こんなふうに見つめて笑ってくれて、英二は嬉しかった。うれしくて微笑んで、英二は訊いてみた。
「美代さんも、俺のこと待っててくれたの?」
「うん、そうよ?」
きれいに笑って美代は頷いた。
そして英二を見つめたまま、言葉をゆっくりと続けてくれた。
「光ちゃんにアイザイレンパートナーが居てくれたら、光ちゃんは山でも1人じゃないでしょう?
2人なら援け合える、そして光ちゃんが望むままに高い高い山にも登って行ける。
そうして光ちゃんの夢をね、叶えて欲しい。
それは若いうちから始めないと難しい夢でしょう?だからね、そういうひとに早く現れてほしいって想っていたの」
真直ぐな実直な目が英二を見つめてくれる。
そしてきれいな明るい目が笑って、英二に言った。
「でも光ちゃんって気難しいから、なかなか心を開かないでしょ?
そんな光ちゃんはアイザイレンパートナーには、体格や技術だけじゃなくて『ホントの友達』まで求めていたのね。
ほんとに信頼して寛げる相手じゃないと、自分が望むような過酷な山ではザイルを繋げない。そう想っていたのかな?」
田中の四十九日の夜に国村が言っていたこと。
―俺のペースに合わせられて、しかも俺と体格が同じ奴じゃないとね、俺はパートナーにしたくなかったんだ
アイザイレンパートナーは一緒にいて楽なやつが良い。だって過酷な状況下で一蓮托生やらなきゃないからね
それと同じことを美代は言っている。そして心から国村の無事と夢を祈って、英二の存在を喜んでくれている。
けれど英二には抱えるものが多い、それも美代は大丈夫なのだろうか。思ったままに英二は訊いた。
「美代さん、俺はね?…周太を愛しているよ。そして周太の事情も全部背負っている、それは危険も多い事情なんだ」
きれいな瞳が、話す英二を静かに見つめてくれる。
やっぱりどこか美代は周太と似ている、そんな想いに微笑んで英二は続けた。
「それでも国村はね、俺を生涯のアイザイレンパートナーに選んだんだ。あいつね、こう言ったよ、
『最高峰ほど危険な場所が世界のどこにある?
そんな最高の危険へと俺は、アイザイレンパートナーとして宮田を惹きこんだ。
これからの人生をより危険に惹きこんでいくのは俺の方だ。だから宮田の危険に俺が巻き込まれるくらいで調度いい』
そんなふうに国村はね、俺を選んでくれたんだ。
だからね、美代さん。俺はね、あいつにリスクを背負わせて、あいつの生涯のアイザイレンパートナーになったんだ」
それでもいいの?
そんなふうに英二は目だけで、きれいな瞳へと訊いた。
きれいな瞳は静かに英二を見上げてくれている。それは真直ぐに穏やかで静かな眼差しだった。
どこかそれは周太によく似ていて、英二は美代の瞳に周太の黒目がちの瞳を見つめていた。
「うん。大丈夫よ、宮田くん?」
美代の瞳が微笑んだ。
そして美代は、きれいな明るい瞳のままで英二に言った。
「光ちゃんの言う通りだと、私も想うな?
だって光ちゃんの夢って、ほんとうに危険よね?だから光ちゃんが言う通り、それで調度いいのよ、きっと」
受けとめてくれた。
うれしくて申し訳なくて、そして幸せで英二は微笑んだ。
「うん…ありがとう、美代さん」
「ううん、こっちこそよ?光ちゃんの相手を一生するなんて、きっと大変ね?がんばってね、宮田くん」
軽やかに笑って美代が言ってくれる。
このひとは本当に国村に似合っているんだ、それが英二には国村の為に嬉しかった。
そしてもう一つ訊きたくて、英二は口を開いた。
「美代さんはね、そんな危険に国村が立つことは大丈夫なの?」
「そうね、ほんとうに危険よね?だって8,000mの高さから落っこちたら、ほんと大変だもの、」
からり明るい調子で美代が微笑んだ。なんだか少し国村にも似た口調に、可笑しくて英二は少し笑った。
きっとずっと一緒に育ったから話すトーンも似てしまったのだろう。そんな2人の繋がりが少し英二は羨ましい。
いいなと見つめる英二に、続けて美代は話してくれた。
「でもね、最高峰に立つことは、ほんとうに楽しいって想うの。
だって世界でいちばん高いところから、世界を見渡すのでしょう?
そこに自分の大好きな人が立って、自分を想ってくれる。それってきっと、世界一に愉快なことよ、でしょう?」
「うん、そうだな。世界一だね、」
頷いて英二は微笑んだ。
自分がいつも想うこと「最高峰から周太に想いを届けたい」
それと同じように国村も、美代に話してきたのだろう。きっと小さい頃からずっと。
この2人には幸せになってほしい、そんな想いが英二の心に温かい。そんな想いのままに英二は言った。
「美代さん。俺はね、国村の生涯のアイザイレンパートナーだ。だから約束するよ、あいつを必ず支えて守ってみせる。
どんな最高峰に立った時でも、ザイルで繋いで守るよ。そして世界一に愉快なことを、あいつに一生ね、させるよ」
きれいな瞳が花咲くように笑ってくれた。
ときおりふる雪の中で美代は、きれいな明るい笑顔で静かに頷いた。
「うん、約束ね?ありがとう、そしてよろしくね」
自分の愛するひとに似た、きれいな瞳のひと。
そのひとの願いも背負ったな、そんな責任感と温かな想いが英二はうれしかった。
こうして背負うごとにきっと自分は強くなれる、賢く深くなっていける。
そうして周太の背負う哀しい運命だって、自分は明るい方へと変えてみせるだろう。
なぜなら背負う責任が、また誰かに援けてもらえる権利も与えてくれると知っている。
「こちらこそ、よろしくね、美代さん」
きれいに笑って英二は頷いた。
頷いていま背負ったのは、最高のクライマーの運命とその相手の想い。
それは大きな責任がある「最高のクライマー」は世界中の山ヤの夢で、そして自分の夢だから。
けれど、こんな大きな責任を背負った自分は、きっと大きな権利も得ただろう。
そう既に最高のクライマー自身が自分に言ってくれている、だから周太の運命すらも自分は変えられる。
だって最高のクライマーはきっと、世界最高の危険地帯から愛される運命の男。
そんな世界最高の危険にすら愛される男から、自分は望まれてその運命の横に並んだ。
そんな世界最高の危険の前では、きっと警察機構の危険など小さく儚いもの。
だからもう、自分はきっと周太の危険を越えられる。そう信じて越えていくだろう。
…周太、俺はね、最高の危険地帯に立つことをさ、選んだよ?
そんな想いに英二は空を見上げた。
ふる雪を生む雲がゆるやかに透明な紺青をながれていく。
その合間からふる星の輝きは、高く遠いけれど明りは静かに山へとふっていた。
「いま、湯原くんのことを想ってる?」
美代の声に英二はゆっくり横へと視線をおろした。
おろした視線のなかで美代は微笑んだ。そして、きれいな封筒を美代は差出してくれた。
「宮田くん。あのね、これを湯原くんに渡してくれる?明日は会うのでしょ?」
「うん、そうなんだ。明日はね、やっと周太に逢えるんだ」
そう、やっと逢える。
微笑んで英二は、登山ジャケットの胸ポケットから手帳を出してはさみこんだ。
そんな英二を見て美代は、微笑んで教えてくれた。
「あのね、先月に会った時の約束なの。味噌のレシピよ?あと、季節のお便り」
「あ、味噌ね?周太も言っていたよ。ありがとう、きっと喜ぶよ」
そんなふうに話しながら歩いて焚火へ戻ると、一升瓶はもう半分ほど空いていた。
その瓶から酒を注がれる藤岡が、いつも以上に笑い転げている。
それを見て美代が国村の隣に立った。
「光ちゃん?すごい呑ませちゃったんでしょ、藤岡くんちょっとハイテンション過ぎだよ」
「うん?そうだったかな。でも俺、無理強いなんかしてないけど?」
飄々と国村が笑っている。
その前では藤岡が人の好い顔のままで、真赤な顔をほころばせていた。
だいじょうぶかな?英二は藤岡の顔を覗きこんだ。
「藤岡、だいじょうぶ?おまえ、何杯呑んだんだよ?」
訊かれた藤岡は相変わらず笑っている。
もとが良い酒だから楽しげだけれど、まだ飲み会は始まって1時間程度だった。
そんな短時間で藤岡がこうも酔うなんて、どれだけハイペースなのだろう?
すこし心配になる英二に、機嫌よく赤い顔の藤岡が言った。
「えっと?そうだなぁ、2杯かなぁ?うん、そうそう、2杯だよ」
「2杯?」
それはおかしい、英二は不審に思った。
藤岡は笑い上戸で赤くなりやすい、けれど東北人らしく酒は強い。
そしていつもの飲み会でも、日本酒2杯程度でこうはならない。一升瓶の2/3位は軽いはずだ。
なにかおかしいな?英二は国村の方を見、その足許に目がとまった。
「国村。その瓶ってさ、中身なに?」
訊かれた国村の細い目が、愉快げに細められた。
流木に座っている国村の足許には、1本の五合瓶が置かれている。
それを見る美代の瞳が少し大きくなった。
「光ちゃん、それって自分で作ったお酒でしょ?」
「うん、そうだよ?」
得意気に細い目が笑っている。
そんな国村を見て、美代が呆れたように笑った。
「それ飲ましちゃったんだ、藤岡くんに?じゃあ酔っ払っちゃうわよね」
「うん、藤岡が呑んでみたいって言うからさ、ご馳走しただけだけど?」
自分で酒まで作るんだ?でも酒造法とかあるだろうに。法学部出身の英二は少し心配になった。
けれど国村は農業高校の出身で農家、学校や家で習ったのだろう。それに酒造法には例外がある。
ちょっとおもしろそうで英二は訊いてみた。
「おまえさ、その酒はお神酒用なんだろ?」
「そ。収穫祭用のさ、濁酒の余りだよ。俺ん家の米で造ったんだ」
収穫された米を神に捧げるとき、濁酒を作って供えて翌年の豊穣を祈願する伝統がある。
そうした宗教的行事における濁酒の製造と飲用は、濁酒の製造免許を受ければ製造可能とされていた。
その場合は境内など神社の一定の敷地内で飲用が許可されている。
そして神社の濁酒など販売を目的とせず、伝統文化的価値の大きいものは酒税法の適用外もある。
たぶんそういう事なのだろうな、英二は訊いてみた。
「じゃあさ、この河原って神社の敷地なんだ?」
「そうだよ。ウチの氏神様の境内地なんだよね、俺、ちゃんと濁酒の製造免許も持ってるしさ。だから合法、だろ?」
やっぱり免許持ってるんだな。予想通りが可笑しくて英二は笑った。
きっと酒好きな国村だから、農業高校の授業でも熱心に勉強したのだろう。
そんな国村は突き詰めるタイプだから、免許取得まで考えて当然だった。
ちょっと興味のままに英二は質問した。
「濁酒製造免許の取得はさ、たしか農業と民宿や農家レストランとかの兼業だよな?」
「そ。ウチはさ、ばあちゃんが週末は農家レストランやってるんだよね。それで俺、免許を取れたんだ」
国村の祖母の手料理は、飲み会の差入れで英二も何度かご馳走になっている。
素朴な食材だけれど味がいいなといつも思っていた。
「そっか。おばあさんの差入れ、いつも旨いけどプロなんだ」
「だろ?ばあちゃんは料理名人なんだよね。それでさ。JAとかに提案されてね、店始めたんだ」
なるほどねと英二は頷いた、けれど疑問が残ってしまう。
濁酒のアルコール度数は普通の清酒と同程度14~17%になる。
それなのに2杯で藤岡は出来あがってしまった。どういうことだろう?英二は首を傾げた。
「なあ、国村?普通の濁酒のアルコール度数はさ、いつもの酒と変わらないはずだろ?
それなのに2杯で藤岡が酔っぱらうなんて変だ。おまえの濁酒って、度数いくつなんだよ?」
言われて国村の細い目が、すっと細まった。その目がさも愉快げに笑っている。
その隣で美代が「仕方ないね?」と少し困った顔で微笑みかけくれた。
「光ちゃんって、研究とかも器用なのよね。それで農業高校の時にちょっと工夫を、ね?」
「なんか、聴くのが怖くなってくるね?」
英二は笑った。きっと、とんでもない度数の酒を合法的に醸造しているのだろう。
そしてなんだか可笑しかった。だって今日はクリスマス・イヴだ、世間はシャンパンで華やかなことだろう。
けれど自分は河原で、友人が作った濁酒の話に笑っている。それが英二はなんだか愉快で楽しかった。
12月24日クリスマス・イヴの夜。毎年ずっと女の人と過ごしていた、そして毎年違う人だった。
それなりに楽しくて、それなりにいつも傷ついていた。いつも自分は作り笑いばかりだったから。
でも今年はこんなふうに、大好きな友人や仲間と心から笑っている。そして明日は心から愛するひとに逢える。
そんな今が幸せで英二は嬉しかった。
うれしくて微笑む英二に、クライマーウォッチを示して国村が笑った。
「ほら宮田、21時前だよ?」
「うん、ありがとう。じゃあ、ちょっとごめんな?」
立ち上がると英二は携帯を開いて、電波状況が良い場所まで歩いた。
いつも英二は周太に21時に電話する、そして周太が当番勤務のときは周太から架ける。
今日の周太は当番勤務、けれど今夜はクリスマス・イヴだから英二から架けたかった。
アンテナ3本が立つ場所に来ると、英二は発信履歴から電話を繋いだ。
「…はい、」
コール0ですぐ繋がってくれる、きっと待っていてくれた。
雪ゆるやかに舞う中で、きれいに英二は笑った。
「周太、待っててくれた?」
すこし気恥ずかしげな気配。
きっと自分が架ける当番勤務だけれど、今日は英二から架けてほしかったのだろう。
きっと華やかなクリスマスの街で、すこし周太は寂しくイルミネーションを見つめていた。
だから自分を待ってくれていた、そんな想いが気恥ずかしげな気配に伝わってしまう。
「…ん、待ってた。今夜はね、英二から声、かけてほしかった。…わがまま、かな?」
ほら、やっぱりそうだ。
こんな遠慮がちで初々しい、そんな自分の運命のひと。
「わがまま、うれしいよ?」
「そう、なの?」
落ち着いた声、ゆるやかな独特のトーン。
このトーンは素顔の周太でいる時だけだと知っている。
そんな1つずつがうれしい、微笑んで英二は答えた。
「そうだよ周太?俺はね、周太の我儘たくさん聴きたい。ね、周太?もっとさ、我儘いっぱい言ってよ?」
「…ん、…わがままって、なんて言ったらいいの?」
英二は笑ってしまった。
こんなふうに周太は、自分の我儘すらも思いつけない。
そんな奥ゆかしさが可愛くて、そんな不器用さが寂しかった生立ちを偲ばせ切なくて。
だから余計に幸せにしたくなる、きれいに笑って英二は言った。
「周太がね、俺にして欲しいこと。全部そのまま言ってくれたら良い。
そして少しはさ、周太のお願いで俺を困らせてよ?そういう周太の『おねだり』俺は聴きたいな」
「…おねだり、って…」
そう、たくさんお願いしてほしい。
困らせられるほどの『おねだり』で自分を繋ぎとめて欲しい。
そうして周太からだって、自分を独占してくれたらいいのに。
そんな想いに英二は、そっと周太に訊いた。
「ね、周太。俺にね、少しでも早く、あいたい?」
繋いだ電話の向こう、微笑みの気配が伝わってくる。
そして幸せそうな想いがそっと、微かな吐息で英二の耳に返響した。
「ん、…早くね、あいたい」
さあ、この『おねだり』は、どんなふうに叶えよう?
(to be continued)
blogramランキング参加中!
ネット小説ランキング
http://www.webstation.jp/syousetu/rank.cgi?mode=r_link&id=5955