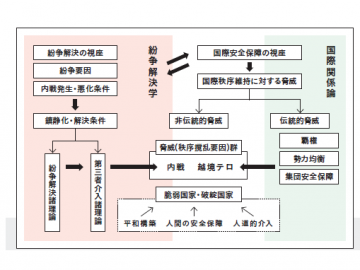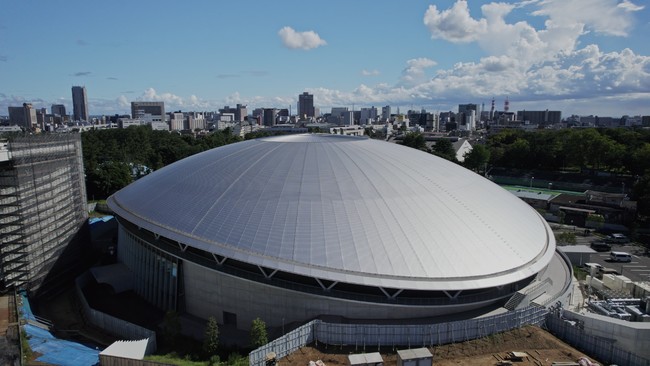[2020年9月10日:更新]
詐欺的“サクラサイト商法”トラブルについて
詐欺的“サクラサイト商法”とは?

“サクラサイト”とは、サイト業者に雇われた“サクラ”が異性、芸能人、社長、弁護士、占い師などのキャラクターになりすまして、消費者のさまざまな気持ちを利用し、サイトに誘導し、メール交換等の有料サービスを利用させ、その度に支払いを続けさせるサイトを言います。このような“サクラサイト”でお金を支払ってしまったという相談があとを絶ちません。国民生活センターでは、このような手口を“サクラサイト商法”と呼んでいます。
“サクラサイト商法”の手口とは? こんなメールきていませんか?
きっかけは
- メールアドレスに直接届く広告メール
- SNSサイトへのメッセージの書き込み
- 内職・副業に関するサイトを探してサイトに登録後に届くメール
- 懸賞サイト、占いサイト等に登録した後に届くメール
こういうメールが届いたら要注意!お金を支払う前に相談を!
サイトからの手口には、いろいろなパターンがあります。消費者に心理的圧迫を与えて、お金を支払わせるケースもあります。以下のような内容のメールが届いたり、おかしいと思った場合には、お金を支払う前に、お近くの消費生活センター等に相談してください。
サイト登録前
- 芸能人や芸能事務所のマネジャーなどをかたる
- 相談にのってくれたら報酬を払う
- お金を受け取ってほしい(例:遺産を受け取ってほしい、節税のためにお金を渡したい 等)
サイト登録後
サイト運営業者を名乗って届く内容
- やりとりの相手からお金やポイントを預かっている
- メールアドレスなどを交換するためには、ランクアップ費用が必要
- 文字化けしたので、文字化け解除料が必要
- 「あなたがわいせつな画像を送信したので、広告スポンサーの信頼を損ねた。サーバーから削除する費用がかかるので損害賠償する」とお金を請求される
やりとりの相手を名乗って届く内容
- 芸能人からテレビの出演情報など仕事の情報を交えてメールが送られてくる
- やりとりをやめようとすると、「後からポイント代を渡すから続けて」「私を信じてほしい」と連絡がくる
- 「あなたが話を聞いてくれないと自殺するしかない」「やめるならこれまで私の払ったお金が無駄になる。裁判で訴える」など、消費者の不安をあおるなどして、やりとりをやめられないようにさせる
- 占いをするためと言って、何度もメールの送信を求められる(例:メールで呪文を30回唱(とな)えるように 等)
大量のメールが届くようになり、リンク先のサイトが別のサイトになっている可能性も…
一度サイトに登録すると、大量のメールが届くことがほとんどです。メールにはられているリンクをクリックしないと、メール全体を読むことができません。しかし、リンクのURLが、同じサイトにつながっているのかわからないので、今までに使っていたサイトと思って利用していても、気がつかないうちに自分が登録したと思っているサイトとは別のサイトにつながっていることもあります。
サイト登録後のメールのやりとりの仕組み
やりとりの相手が消費者にメールを送ると、サイト運営業者からのメールが消費者の携帯電話等に届き、やりとりの相手からのメールの一部分が読めるようになっています。そこにリンクのはられたURLから入ったサイト内のメールボックスで、メールの続きを読むことができます。多くの場合、消費者は、やりとりをするためにポイントを購入する必要があります。有料の場合には、メール1通あたり数百円分のポイントがかかる場合が多いです。最近では、メールの送受信は、無料とうたっているサイトもあります。
主な相談事例
- 【事例1】
- 無料SNSサイトで、好きなタレントのページにリンクをはって利用していた。すると、そのタレントから直接メッセージが届き、「事務所に内緒なので、別サイトでやりとりしたい」と別のサイトに誘導された。メール交換のためのポイント購入で260万円支払ったが、だまされたのだろうか。
- (30歳代 女性)
- 【事例2】
- 高収入の人と連絡先を交換できるというメールが届き、サイトに登録した。すると、「800万円を援助する」というメールが届いた。援助を受けるための手続きとして、数千円を振り込んだが、その後、数十万円の請求をされるようになり、3日間で約180万円を振り込んでしまったが、収入は得られなかった。
- (30歳代 女性)
- 【事例3】
- 「在宅ワーク」と携帯電話で検索したところ、「男性から悩みを聞けば収入を得られる」という広告を見て、誘導されたサイトに登録した。メールの送受信は無料と書かれていたが、お金を受け取るにはポイント購入が必要と言われ、さまざまな名目でポイントを購入し続け、1週間で180万円にもなってしまった。
- (30歳代 女性)
- 【事例4】
- 婚活サイトに登録したところ、姉妹サイトである出会い系サイトにも登録したことになったので、そのサイトでメール交換を開始した。メールの中で陰陽師を名乗る人から「悪霊がついている」、「取り除くための呪文を教えるので、その呪文をメールで50回送るように」等と言われるうちに怖くなり、ポイントを購入し、1通約700円のメールを送り続けた。タレントや300万円を渡したいという人からもメールが届いた。合計約600万円を支払ってしまったので、貯蓄もなくなった。約束通り、300万円を受け取りたい。
- (60歳代 男性)