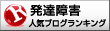6月になりました!
新学期からはや2か月。
6月2日は「横浜の開港記念日」で横浜市立の学校は、休校。
塾もお休みにして、久しぶりにのんびり。

ちょっと疲れて座ってしまったので手すりが微妙な位置です・・・。
やっぱり「海」のそばに行ってしまいます。




















今日は「技能教科」について考えてみようと思います。
教室に入ると(中学校でも)壁に作品が掲示されています。
名前順だったり、ランダムだったり。
私が教員のときは、同じ子が特定の場所にならないように、できるだけランダムに貼るように
しました。(特に図工の作品は)
並べて掲示されると、すぐ「視線」が行ってしまう作品があります。
目を引く作品。
特別支援教育について勉強し始めてからは、
気持ちや力がだしきれていないのかな、と思う作品。
子どもたちにとって、作品はたいてい背中(黒板と逆方向)に掲示されるので、
じっくり見るのは、休み時間や、給食の時間(今は前向きなのでないかな・・・)。
学年が小さいときは、自分の作品を見て、「そこにあることに満足。」
学年が上がってくるとなんとなく「友達との差」を感じることも。
私は子どものころ図工が大好きだったので、毎回授業を楽しみにしていたのですが、
あるとき、廊下に貼られたとなりの組の作品を見てショック!
「負けた~!!」
本当にダイナミックで上手な「🍉の絵」でした。
音楽では歌や演奏、体育では鉄棒や跳び箱、
家庭科では裁縫や包丁さばき。
理科では観察記録。
「一瞬」のパフォーマンスもあるけれど、
掲示されたものはしばらく「人目にさらされ」ます。
もちろん、演奏や演技だって、
高学年になると「差」が歴然。
声に出していわれはしないけれど、
気持ちがへこむこともあります。
先生のコメントで救われないとつらいこともあるかもしれないです。
(みんな得意、不得意があるのですが、
ここのがんばりがいいね、と言われれば、次もがんばろうになります!)
本来「技能教科」は「人生を楽しむ・豊かにする」ためのものであって、
「評価される」ことが主ではないのでは・・・という気もします。
漢字が苦手でも、計算が苦手でもあまり目立ちませんが、
この4教科はけっこう目立ちますものね。
子どもにとって自分なりの「満足」が得られる時間になるとよいな~と思います。
また、技能教科や理科の実験などでは、
グループ学習をすることがよくあります。
グループ活動をよく見ていると、
「片づけ」専門になっている子や、「いつも発表する」子、
いつも「掲示物をもつ」子がいるときが結構あるような気がします。
調理実習や理科の実験では、「分担」しているようで、
実際あまり包丁にさわっていない、コンロの前に立たない子がいないか、
実験器具にさわるのは、準備と片づけだけになっていないか
合奏ではいつも「リコーダー・カスタネット担当」になっていないか
サッカーではいつも「バック」担当になっていないか
「技能」がみにつく機会が子どもによって「差」がないか
ちょっと気になります。
子どもどうしの微妙な力関係が働いていないか・・・。
自分は上手ではない、という自信のなさや
グループの中の力関係でその分担が、
「暗黙の了解」になっていないか。
一見「うまくいっているグループ」の中でも
一人ひとりの子どもの中にいろんな気持ちがあるのだと思います。
幼いころから、「みんなが楽しんでいるのかな」と気遣う練習を意図的に
していくことも大切なことなのでは、と思うこのごろです。
個別学習塾びすぽうくのホームページへ (色のついているところをクリックしてください)
(色のついているところをクリックしてください)
新学期からはや2か月。
6月2日は「横浜の開港記念日」で横浜市立の学校は、休校。
塾もお休みにして、久しぶりにのんびり。

ちょっと疲れて座ってしまったので手すりが微妙な位置です・・・。
やっぱり「海」のそばに行ってしまいます。




















今日は「技能教科」について考えてみようと思います。
教室に入ると(中学校でも)壁に作品が掲示されています。
名前順だったり、ランダムだったり。
私が教員のときは、同じ子が特定の場所にならないように、できるだけランダムに貼るように
しました。(特に図工の作品は)
並べて掲示されると、すぐ「視線」が行ってしまう作品があります。
目を引く作品。
特別支援教育について勉強し始めてからは、
気持ちや力がだしきれていないのかな、と思う作品。
子どもたちにとって、作品はたいてい背中(黒板と逆方向)に掲示されるので、
じっくり見るのは、休み時間や、給食の時間(今は前向きなのでないかな・・・)。
学年が小さいときは、自分の作品を見て、「そこにあることに満足。」
学年が上がってくるとなんとなく「友達との差」を感じることも。
私は子どものころ図工が大好きだったので、毎回授業を楽しみにしていたのですが、
あるとき、廊下に貼られたとなりの組の作品を見てショック!
「負けた~!!」
本当にダイナミックで上手な「🍉の絵」でした。
音楽では歌や演奏、体育では鉄棒や跳び箱、
家庭科では裁縫や包丁さばき。
理科では観察記録。
「一瞬」のパフォーマンスもあるけれど、
掲示されたものはしばらく「人目にさらされ」ます。
もちろん、演奏や演技だって、
高学年になると「差」が歴然。
声に出していわれはしないけれど、
気持ちがへこむこともあります。
先生のコメントで救われないとつらいこともあるかもしれないです。
(みんな得意、不得意があるのですが、
ここのがんばりがいいね、と言われれば、次もがんばろうになります!)
本来「技能教科」は「人生を楽しむ・豊かにする」ためのものであって、
「評価される」ことが主ではないのでは・・・という気もします。
漢字が苦手でも、計算が苦手でもあまり目立ちませんが、
この4教科はけっこう目立ちますものね。
子どもにとって自分なりの「満足」が得られる時間になるとよいな~と思います。
また、技能教科や理科の実験などでは、
グループ学習をすることがよくあります。
グループ活動をよく見ていると、
「片づけ」専門になっている子や、「いつも発表する」子、
いつも「掲示物をもつ」子がいるときが結構あるような気がします。
調理実習や理科の実験では、「分担」しているようで、
実際あまり包丁にさわっていない、コンロの前に立たない子がいないか、
実験器具にさわるのは、準備と片づけだけになっていないか
合奏ではいつも「リコーダー・カスタネット担当」になっていないか
サッカーではいつも「バック」担当になっていないか
「技能」がみにつく機会が子どもによって「差」がないか
ちょっと気になります。
子どもどうしの微妙な力関係が働いていないか・・・。
自分は上手ではない、という自信のなさや
グループの中の力関係でその分担が、
「暗黙の了解」になっていないか。
一見「うまくいっているグループ」の中でも
一人ひとりの子どもの中にいろんな気持ちがあるのだと思います。
幼いころから、「みんなが楽しんでいるのかな」と気遣う練習を意図的に
していくことも大切なことなのでは、と思うこのごろです。
個別学習塾びすぽうくのホームページへ
 (色のついているところをクリックしてください)
(色のついているところをクリックしてください)