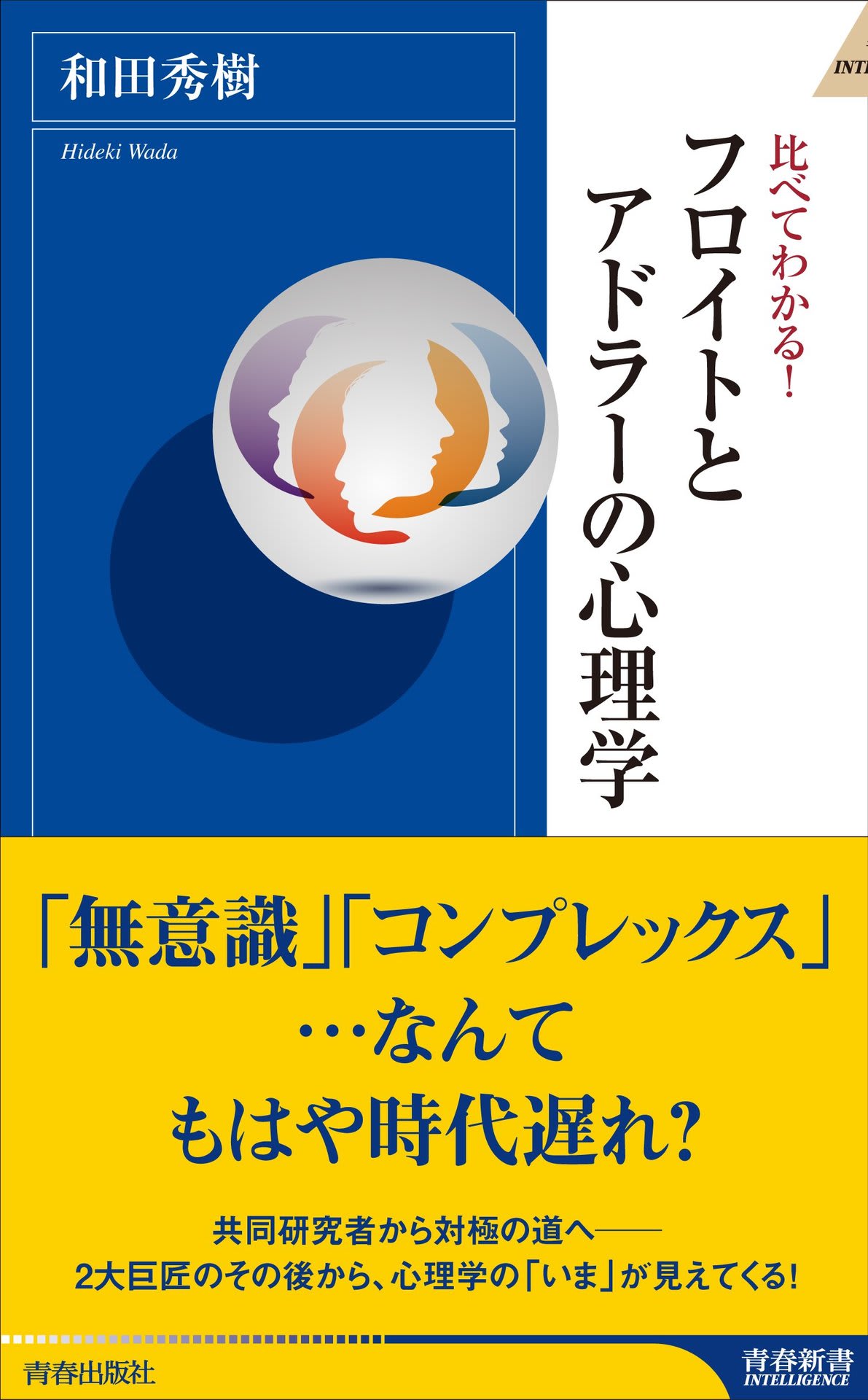
アドラー心理学について解説した本、「嫌われる勇気(岸見一郎、古賀史建)」
が売れているという。書店には他にもアドラー心理学関係の本が何冊も並んでいて
世の中アドラー心理学ばやりのようである。
半年ほど前、私は「嫌われる勇気」をたまたま本屋で見つけてそのタイトルに惹かれて
買った一人である。
「嫌われる勇気」を読んでアドラー心理学とはどんなものなのかおおよそはわかったが、
精神分析や心理学といった学問全体の中でどういう位置にあるのかがよくわからなかった。
「比べてわかる!フロイトとアドラーの心理学」は、フロイトは無意識などが人の心を
規定するという「原因論」、アドラーはある心の状態には何か目的があるはずだと考える
「目的論」と説明し、その対比がこの本の主題ではある。
しかし私には、フロイト、アドラーに始まり、現在に至る心理学・精神医学の歴史と全貌が解説されていて、
そこがとてもおもしろかった。
・心の病気や傷を治すための学問には、心を扱う「臨床心理学」と脳を扱う「生物学的精神医学」がある。
前者は心理療法や精神療法を行う。後者は脳の画像診断や薬物療法を主に行う。
・心の病でいちばん軽いのが「神経症」、もっとも重いのが「精神病」で統合失調症と躁うつ病が含まれる。
その中間に位置するのが「ボーダーライン」とか「パーソナリティー障害」「シゾイド」と呼ばれるもの。
・フロイトの精神分析の対象は神経症。しかし、現在は薬が神経症と精神病にそれなりに効くので、フロイトの
出番がなくなった。(フロイトの心理学の芸術や文学への影響ははかりしれないものがあると思う。無意識の
中に自分の秘密が隠されていると考えたら追及したくなるものだ。しかし、心の病に効かないのじゃしょうが
ない。)
・ボーダーラインの治療法として出てきたのが、自我を鍛え直すカーンバーグの方法と、分析家が患者に
愛情を与えて育て直しを行うコフートの方法。前者が対象とするのは重症のボーダーライン、後者が
対象とするのは軽傷のボーダーライン。アメリカでは富裕層の中にも軽いボーダーライン患者が多いので、
コフート型精神分析が主流となった。
・アドラーと同時代に日本で生まれた森田療法は、原因を分析しない、部分より全体を見るという点で共通
している。
・70年代にアメリカでPTSDでトラウマ記憶を思い出させる精神分析が流行ったが、実はこの療法が原因で患者の
心の状態が悪化し、自殺や離婚が増えることが判明し、現在は行われていない。(過去のつらい記憶を思い出す
のは現在の精神の安定に多大なマイナスの影響を及ぼしてしまうということだろう。)
・現在のスタンダートな心理療法には「認知療法」、「行動療法」、「認知行動療法」があり、変えられるものを
変えるという発想で、患者の心のこだわりをほぐし、行動や考え方を変えることでうつ病などを治療する。
アドラーや森田療法にも近い。
・ボーダーラインのなかでもサイコパスとも呼ばれた反社会性パーソナリティー障害は人口の1~3%程度もいる。
治療不可能であり、唯一死刑制度が抑止力になると考えられる。
・抗うつ剤の主流であるSSRIは、服用者の自殺率を高めたり、凶悪な殺人事件を起こすような危険性もある。
大阪の池田小事件や秋葉原通り魔事件の犯人は反社会性パーソナリティー障害ではなく、抗うつ剤の副作用
が影響していると考えられている。
様々な心理療法があるのだから、どれが自分のニーズに合っているのか試行錯誤して探すのが
いいという結論も納得できた。









