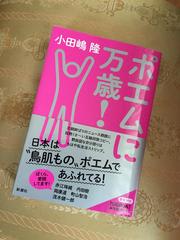一ヶ月ほど前、ダイエットを始めたということを書いた。
体重が70に近くなるとダイエットをして60代前半まで落とす、というのをここ10数年繰り返してるんだけど、年々減りにくくなってきている。
そのため、今までは有酸素運動オンリーで、つまり食事は今まで通り食べながら、体重を落としてきたが、今回はそれプラス筋肉トレーニングも加えたのだ。
で、結果は昨日時点で5キロ減量となった。
ダイエットを始めると同時に体重の記録もつけるのだけど、その推移を見ていただこう。

これを見ると、素直に体重が下がるのではなく、途中何度も上がったり下がったりしながら少しづつ減っているのがわかる。
僕は元々、そんなに太ってたわけではないので、そこまで体重にこだわる必要はないんだけど、やるからには結果が出るほうがいい。
筋トレの効果はどれだけあったのかわからない。
少なくとも、筋トレのおかげでウエストが引き締まったとか、胸板が厚くなったとか、たくましそうな腕になったなんてことは一切ない。
ただ、体脂肪率は16パーセント台だったのが15パーセント台にはなった。
もうあと2キロくらい落として、体脂肪率は14パーセント台にしたいと思う。
なので、もうちょっと続けます。
体重が70に近くなるとダイエットをして60代前半まで落とす、というのをここ10数年繰り返してるんだけど、年々減りにくくなってきている。
そのため、今までは有酸素運動オンリーで、つまり食事は今まで通り食べながら、体重を落としてきたが、今回はそれプラス筋肉トレーニングも加えたのだ。
で、結果は昨日時点で5キロ減量となった。
ダイエットを始めると同時に体重の記録もつけるのだけど、その推移を見ていただこう。

これを見ると、素直に体重が下がるのではなく、途中何度も上がったり下がったりしながら少しづつ減っているのがわかる。
僕は元々、そんなに太ってたわけではないので、そこまで体重にこだわる必要はないんだけど、やるからには結果が出るほうがいい。
筋トレの効果はどれだけあったのかわからない。
少なくとも、筋トレのおかげでウエストが引き締まったとか、胸板が厚くなったとか、たくましそうな腕になったなんてことは一切ない。
ただ、体脂肪率は16パーセント台だったのが15パーセント台にはなった。
もうあと2キロくらい落として、体脂肪率は14パーセント台にしたいと思う。
なので、もうちょっと続けます。