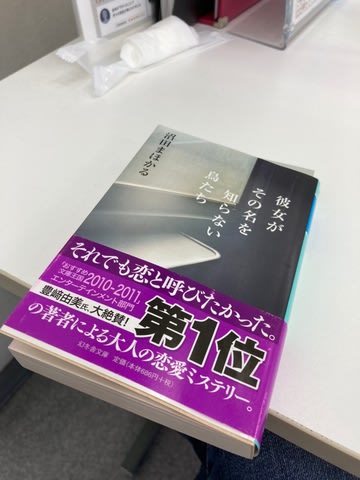
少し前だけどナオちゃんのオススメで、沼田まほかるの「彼女がその名を知らない鳥たち」を読んだ。
すぐに内容に引き込まれて3日くらいで読破して、その結末に衝撃受けた。
沼田まほかるは前に「ユリゴコロ」というのを読んだ。
暗くて不気味で猟奇的な前半と、複雑な愛の形を表現した後半、それまで読んだことない質感のある作品でとてもよかった。
ついでに映画版も見たけど、前半の不気味な雰囲気がよく表現されてたと思う。
さて「彼女がその名を知らない鳥たち」、この題名からどういう内容なのかは全く想像出来ない。
主人公の十和子はいわゆるダメ人間である。
主人公と同棲する陣治、これまたちょっと種類は違うけどダメ人間である。
主人公の元カレの黒崎、これもまた上記の二人とはまた違うタイプのダメ人間で、後に主人公が惚れる水島もまたダメ人間という、主な登場人物全員なんらかのダメ人間なのだ。
十和子は生活の全てを陣治に頼りきってるくせに、この男のことが大嫌いだと思ってる。
毎日、これでもかと罵詈雑言を並べ立て、自分は仕事も家事もしない。
陣治は、女性から見て「結婚したくない男ナンバーワン」みたいな男で、下品、不潔、見栄っ張り、低収入、そして見た目もダサいオッサンだけど、十和子に対する愛だけはホンモノである。
黒崎はハンサムでハイセンスだけど、自分の出世のためなら女をモノのように扱い、ときには暴力も振るう、ダメ人間というより、人間のクズ。
水島も黒崎と同タイプだけど、ちょっとはマシか。
愛とはなんなのか、幸せとはなんなのかというのを改めて考えさせられる。
そして十和子が本当の愛に気がついたとき、それはもう遅すぎたのだ。
悲しすぎる結末にショックを受ける。
映画版もオススメとのことなので、また見たいと思う。
















