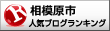チェックポイント3つ目の品川神社を参拝した後、なぜか迷子になってしまいまして…。
まあ、無理から品川本陣跡にも寄ろうと思ったのが敗因なのですが。
品川本陣跡は、現在聖蹟公園になってます。


説明板発見:品川本陣跡(聖蹟公園)
江戸時代の本陣は、宿場で大名や旗本などが休息や宿泊するところで、品川宿には始め南北品川宿に一軒つづありましたが、江戸中期には北品川宿のみとなりました。
大名などが宿泊すると本陣には大名の名を記した簡札をたて、紋の入った幕をめぐらしました。
明治維新後、京都から江戸へ向かった明治天皇の宿舎にもなったところです。」うん。この説明板、読みにくい。木製なのがイカンのか?加工の問題か??
さて、時刻は既に14時20分。迷子の時間が痛かった~。先を急がねば…。
途中、品川宿交流館本宿お休み処に立ち寄りました。

ここには品川宿の資料があって、中にある東海道品川宿まち歩きマップはとてもよく出来ているのでぜひ手に入れて下さい。ン~と、これ、いくらだったっけ??確か100円ちょいだったような…。メモし忘れたかな??
先を急ぎます。2階には資料展示がありましたが、時間がないからまた今度です。

旧東海道を下ると、すぐに橋に行き合いました。品川橋です。
説明板発見:品川宿の今昔
この辺りは江戸の昔、「東海道五十三次一の宿」として、上り下りの旅人で大変賑わいました。また、海が近く漁業もさかんなところでした。今でも神社仏閣が多く、当時の面影がしのばれます。
品川橋は、旧東海道の北品川宿と南品川宿の境を流れる目黒川に架けられ、江戸時代には境橋と呼ばれていました。また別に行き合い橋・中の橋とも呼ばれていたようです。最初は木の橋でしたが、その後石橋になり、そしてコンクリート橋から現在の鋼橋へと、時代の移り変わりとともに、その姿を川面に写してきました。」以上。
橋を渡り南品川へ。

しばらく直進すると、街道松の広場に出会います。
説明板発見:品川宿の松
この松は、旧東海道品川宿のシンボルとなる「街道松」として、東海道が取り持つ縁で、二十九番目の宿場があった静岡県浜松市の有賀慶吉氏より品川宿に寄贈された樹齢約80年の黒松です。
ナナメに傾いた幹は、風雨に耐えながら旅人を見守った当時の松並木をしのばせる見事な枝振りです。
松の名称は、寄贈された有賀氏より「品川宿の松」と命名されました。
また約150メートル南の「南品川二丁目児童遊園」には、三島市より同じ主旨で寄贈された「街道松」があります。(平成5年3月吉日)
説明板に出て来た児童遊園です。

上の画像に見える海鼠壁の建物はトイレ。江戸風味がきいてます。
この公園からすぐにある和菓子屋さんに、面白自販機がありました。

ちなみにこのお店の一押しはこちら。
 閻魔いなりです。
閻魔いなりです。


せっかくなので1個買ってみた。食べ歩きし易いように、紙に挟んで渡してくれましたが、時間がなくて結局家まで持ち帰ってしまいました。ちなみに、どの辺が閻魔いなりなのか?というと、唐辛子を効かせて辛く仕上げてました。
さて、閻魔はどこから来たのか?というと。4つ目のチェックポイントの長徳寺さんです。これがトップ画像なのです。
画像からわかるように現在工事中。
長徳寺さんは恭敬山と号する時宗の寺で、寛正4年(1463)の創建と伝えられています。元は、今の品川小学校校庭(北品川3-9-30)辺りにありましたが、寛永14年(1637)東海寺建立に際し、末寺の常光寺のあったこの地に移ってきました。
本尊は阿弥陀如来です。この寺には、初代将軍徳川家康から14代徳川家茂までの朱印状が残っており、区指定文化財となっています。(コピーより)
品川宿文化財ウォークラリー開催のおかげか、閻魔堂は工事中ですが、中を見る事が出来ました。
嬉しい~。おそらくこのお堂は普段入口を閉じてあって、気軽に中に入る事は出来ない模様です。そしてここにも解説員が配置されてます。ありがたい~。
「今日は、六道絵もごらんいただけるようになっています」
この六道絵が素晴らしかった!何が凄いって、寛永2年(1849)に寄進された軸なのに、色彩が今も鮮やかに残ってるのです。惜しむらくは、六道だから6枚の軸で納められたと思うのですが、現存するのは5まいだけ。どこかで1枚行方不明になった模様です。
六道とは、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上のいずれかに行くとされていますが、その六道のそれぞれの世界が描かれています。善を勧め、悪を戒めるための、地域の民間信仰のあり方を示したものです。(コピーより)
トップ画像の閻魔堂は、元は東光地現大龍寺にありました。堂の中には像の高さ88センチの木造閻魔王座像が祀られています。制作年代は不明ですが、鎌倉時代のものと伝えられています。正月の16日と7月16日には、地獄の釜のふたが開く日といわれ、参詣する人が多く賑わったそうです。<コピーより>
さて時刻は既に14時45分になっています。文化財ウォークラリーの受付時刻が14時から15時15分の間なので、予定より遅れ気味です。
イカンなあ~。品川神社の後迷子になったのと、お休み処品川交流館で時間を費やしたのが敗因です。先を急ごう。
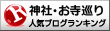 神社・お寺巡り ブログランキングへ
神社・お寺巡り ブログランキングへ
まあ、無理から品川本陣跡にも寄ろうと思ったのが敗因なのですが。
品川本陣跡は、現在聖蹟公園になってます。


説明板発見:品川本陣跡(聖蹟公園)
江戸時代の本陣は、宿場で大名や旗本などが休息や宿泊するところで、品川宿には始め南北品川宿に一軒つづありましたが、江戸中期には北品川宿のみとなりました。
大名などが宿泊すると本陣には大名の名を記した簡札をたて、紋の入った幕をめぐらしました。
明治維新後、京都から江戸へ向かった明治天皇の宿舎にもなったところです。」うん。この説明板、読みにくい。木製なのがイカンのか?加工の問題か??
さて、時刻は既に14時20分。迷子の時間が痛かった~。先を急がねば…。
途中、品川宿交流館本宿お休み処に立ち寄りました。

ここには品川宿の資料があって、中にある東海道品川宿まち歩きマップはとてもよく出来ているのでぜひ手に入れて下さい。ン~と、これ、いくらだったっけ??確か100円ちょいだったような…。メモし忘れたかな??
先を急ぎます。2階には資料展示がありましたが、時間がないからまた今度です。

旧東海道を下ると、すぐに橋に行き合いました。品川橋です。
説明板発見:品川宿の今昔
この辺りは江戸の昔、「東海道五十三次一の宿」として、上り下りの旅人で大変賑わいました。また、海が近く漁業もさかんなところでした。今でも神社仏閣が多く、当時の面影がしのばれます。
品川橋は、旧東海道の北品川宿と南品川宿の境を流れる目黒川に架けられ、江戸時代には境橋と呼ばれていました。また別に行き合い橋・中の橋とも呼ばれていたようです。最初は木の橋でしたが、その後石橋になり、そしてコンクリート橋から現在の鋼橋へと、時代の移り変わりとともに、その姿を川面に写してきました。」以上。
橋を渡り南品川へ。

しばらく直進すると、街道松の広場に出会います。
説明板発見:品川宿の松
この松は、旧東海道品川宿のシンボルとなる「街道松」として、東海道が取り持つ縁で、二十九番目の宿場があった静岡県浜松市の有賀慶吉氏より品川宿に寄贈された樹齢約80年の黒松です。
ナナメに傾いた幹は、風雨に耐えながら旅人を見守った当時の松並木をしのばせる見事な枝振りです。
松の名称は、寄贈された有賀氏より「品川宿の松」と命名されました。
また約150メートル南の「南品川二丁目児童遊園」には、三島市より同じ主旨で寄贈された「街道松」があります。(平成5年3月吉日)
説明板に出て来た児童遊園です。

上の画像に見える海鼠壁の建物はトイレ。江戸風味がきいてます。
この公園からすぐにある和菓子屋さんに、面白自販機がありました。

ちなみにこのお店の一押しはこちら。
 閻魔いなりです。
閻魔いなりです。

せっかくなので1個買ってみた。食べ歩きし易いように、紙に挟んで渡してくれましたが、時間がなくて結局家まで持ち帰ってしまいました。ちなみに、どの辺が閻魔いなりなのか?というと、唐辛子を効かせて辛く仕上げてました。
さて、閻魔はどこから来たのか?というと。4つ目のチェックポイントの長徳寺さんです。これがトップ画像なのです。
画像からわかるように現在工事中。
長徳寺さんは恭敬山と号する時宗の寺で、寛正4年(1463)の創建と伝えられています。元は、今の品川小学校校庭(北品川3-9-30)辺りにありましたが、寛永14年(1637)東海寺建立に際し、末寺の常光寺のあったこの地に移ってきました。
本尊は阿弥陀如来です。この寺には、初代将軍徳川家康から14代徳川家茂までの朱印状が残っており、区指定文化財となっています。(コピーより)
品川宿文化財ウォークラリー開催のおかげか、閻魔堂は工事中ですが、中を見る事が出来ました。
嬉しい~。おそらくこのお堂は普段入口を閉じてあって、気軽に中に入る事は出来ない模様です。そしてここにも解説員が配置されてます。ありがたい~。
「今日は、六道絵もごらんいただけるようになっています」
この六道絵が素晴らしかった!何が凄いって、寛永2年(1849)に寄進された軸なのに、色彩が今も鮮やかに残ってるのです。惜しむらくは、六道だから6枚の軸で納められたと思うのですが、現存するのは5まいだけ。どこかで1枚行方不明になった模様です。
六道とは、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上のいずれかに行くとされていますが、その六道のそれぞれの世界が描かれています。善を勧め、悪を戒めるための、地域の民間信仰のあり方を示したものです。(コピーより)
トップ画像の閻魔堂は、元は東光地現大龍寺にありました。堂の中には像の高さ88センチの木造閻魔王座像が祀られています。制作年代は不明ですが、鎌倉時代のものと伝えられています。正月の16日と7月16日には、地獄の釜のふたが開く日といわれ、参詣する人が多く賑わったそうです。<コピーより>
さて時刻は既に14時45分になっています。文化財ウォークラリーの受付時刻が14時から15時15分の間なので、予定より遅れ気味です。
イカンなあ~。品川神社の後迷子になったのと、お休み処品川交流館で時間を費やしたのが敗因です。先を急ごう。