シイタケは長年やっています。しかし、それで生計をたてているわけではないので、いいかげんなやり方です。きのこが出たいときに出るようにしていて、ごく自然にまかせています。というと、良さそうに聞こえますが、面倒くさいから放ったらかしにしているだけです。
今年の冬は、あまりにも大きくなったクヌギの木を何本も切ってもらいました。切ったのはシイタケで生計を立てている人です。彼は、菌を埋め込んだ木、つまりホダ木を、時期が来た頃に水槽に一端入れます。そして、水分をたっぷり含ませた上で、キノコがでるようにします。そのため、あまり太い木は使えません。重くて持ち上がらないからです。
そのために、枝先と太い幹の部分は置いて行かれてしまいました。それは私が大部分を短く運べる程度に気って、積み上げていますが、彼がそれ以上は必要がないと言う、彼にしては太めの部分をひろって、ホダ木にしました。その数およそ60本。打ち込んだ菌が3箱です。1箱にいくつコマが入っていたか忘れましたが、たぶん500だったかと、、。

それに、林の中にヤマザクラもあったものですから、これにはナメコを打ち込みました。ナメコはシイタケより神経質なのか、ちょっと難しそうです。一昨年に一度トライしましたが、一度は出ました。その後は、これからの結果待ちです。
普通、木は12月から2月頃までの間に切ります。もっと早くても良いという話も聞きます。菌を埋め込むのは私は3月末から4月の上旬頃までの間に行っています。
このホダ木を積み上げ、ときどき上から散水しています。異常な乾燥を防ぐためです。上に念のために寒冷紗(かんれいしゃ)を乗せています。これを梅雨があけるくらいまで積み上げておきます。その後、横木に斜めに立てかけることにします。家の裏の、薄暗いとこだし、蚊がたくさんいるところなので、いいかげんになってしまって、真夏を過ぎてから立てかけることもありますが、大丈夫です。
2年くらい経つと、見事なおいしいシイタケがでます。シイタケは、原木さえ手に入れば、あとは日陰においておくだけで、めんどうなことはないので、栽培はいいかげんな私には合っているような気がします。
せっかく出てくれたキノコも、油断してしばらく見に行かないと、お化けのように大きくなってしまって、傘の裏側が赤色に変色してしまっていることが度々です。もったいないのですがー。
ついでに、ホダ木に使ったクヌギ、ナラ、ヤマザクラは木を切っても株が残ります。その株からまた芽が出て、成長して大きな木になりますので植林は不必要です。










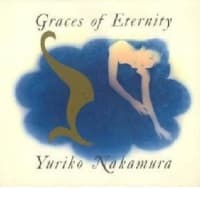










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます