▲水野忠邦
●江戸時代(仁孝天皇 徳川家慶)
Senior shogunal councilor Mizuno Tadakuni starts Tempo Reforms.
いやよいテンポ 水野(みずの)さん。
1841年 天保の改革 水野忠邦 株仲間の解散
1841年に大御所徳川家斉が死去すると、水野忠邦は大塩平八郎の乱やアヘン戦争など、体制を揺るがす国内外の厳しい問題に対応するため、天保の改革を断行。
株仲間の解散や人返しの法などを相次いで実施した。
さらに、上知令を出し、財政の安定や対外防備の強化をはかろうとしたが諸大名や旗本の反対にあい、忠邦は失脚。改革はわずか2年でおわった。
A crackdown on various forms of popular culture accompanying the Tenpo Reforms effectively silenced some writers and publishers, especially that produced koshokugabon (book of pornography), and served as an admonishment to others, such as an accusation against Sunshui TAMENAGA; as a result, ninjobon lost its vigor and creative force, and gokan (literally, bound-together volumes of illustrated books) appeared in numbers larger, to make up for that decline of ninjobon.
天保の改革によって特に好色画本が禁圧され、為永春水らが罪に問われるなど戯作者・版元に圧力が加えられると、人情本は衰退し、その穴を埋めるように合巻の刊行点数が増大した。
散歩は/上智に/引(ひっ)返し/水飲み解散 日光の威張り家慶/神水(しんすい)倹約!/タメ口気炎
(将軍家慶の日光社参(43)・印旛沼干拓)(天保の薪水給与令・倹約令)(人情本の為永春水弾圧・棄捐令)
(三方領知替え)(上知令(あげちれい(じようちれい)((43))(人返しの法)(水野忠邦・株仲間解散)
[ポイント]
1.水野忠邦による天保の改革では、上知令・株仲間解散・三方領知替え問題・人返しの法があった。
[解説]
1.1841(天保12)年、大御所徳川家斉の死後、12代将軍徳川家慶のもとで老中水野忠邦(1794~1851)を中心に幕府権力の強化をめざして天保の改革をおこなわれた。
2.ついで江戸の人別改めを強化し、百姓の出稼ぎを禁じて、江戸に流入した貧民の帰郷を強制する人返しの法を発し、天保の飢饉で荒廃した農村の再建をはかろうとした。この強制で、無宿者や浪人らも江戸を追われ、江戸周辺の農村の治安悪化を引きおこすことになった。
3.また物価騰貴の原因は、十組問屋などの株仲間が上方市場からの商品流通を独占しているためと判断して、株仲間の解散を命じた。幕府は江戸の株仲間外の商人や、江戸周辺の在郷商人らの自由な取引による物価引下げを期待したのである。しかし物価騰貴の実際の原因は、生産地から上方市場への商品の流通量が減少して生じたもので、株仲間の解散はかえって江戸への商品輸送量をとぼしくすることになり、逆効果となった
4.一方、幕府は、相模の海岸防備をになわせていた川越藩の財政を援助する目的から、川越・庄内・長岡3藩の封地をたがいに入れ換えることを命じたが、領民の反対もあって撤回された。川越藩が豊かな庄内藩へ、庄内藩が越後長岡藩へ、越後長岡藩が川越藩へ移るもので、三方領知替(さんぽうりようちが)えと呼ばれる。幕府が転封を決定しながらその命令が徹底できなかったことは、幕府に対する藩権力の自立を示す結果となった。
5.さらに水野忠邦は、1843(天保14)年に上知令を出し、江戸・大坂周辺のあわせて約50万石の地を直轄地にして、財政の安定や対外防備の強化をはかろうとした。他地域に代替地は用意されたが、譜代大名や旗本に反対されて上知令は実施できず、改革の失敗は改めて幕府権力の衰退を示した。
〈2016立教大・現心社コミュ福
19世紀前半には、こうした国内問題に加えて対外問題もあいまって、幕府の弱体化が進んだ。この事態に対処するために老中( ワ )を中心に天保の改革と呼ばれる改革が実施されたが、充分な効果をあげることはできなかった。」
(答:ワ水野忠邦)〉
〈2016関西学院大学・全学部
問7a.享保の改革の上げ米は、大名に1万石につき100石を上納させ、かわりに参勤交代を緩めるもので、寛政の改革で廃止されるまで続けられた。
b.上知令は江戸・京都周辺を直轄地として財政の安定と対外防衛の強化を図るものであったが、大名や旗本の反対にあい水野忠邦は老中を退いた。」
(答a×1722に開始したが享保の改革中の1730年に廃止、b×京都→大坂)〉
〈2016早大・法:
「問10 下線部「1843年には、c天保の無利子年賦返済令が出ている」のcと関連した、天保の改革の経済改革に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選べ。
あ 新田開発を目指し、商業資本に依拠して実施した印旛沼の干拓事業は、利根川の氾濫で失敗した。
い 幕府領の年貢増収をはかって、土地・収穫高の再調査を命じる御領所改革を実現した。
う 農村再建を図るため、江戸に流入した下層民を強制的に帰農させる「人返しの法」を実施した。
え 江戸・大坂十里四方の知行地を幕府直轄領にする上知令を、大名・旗本の反対に抗して遂行した。
お 幕政に重要な川越藩松平家強化のため、同家を庄内に、庄内藩酒井家を長岡に、長岡藩牧野家を川越に移した。」
(答:う ※あ・い・え×水野忠邦の失脚で中止、お×庄内藩の農民による激しい反対にあい中止)
〈2016明大・文
史料B
一 [ b ]のもの身上相仕舞(しんじようあいしま)い、[ c ]人別に入(い)り候儀、自今以後決して相成らず。
一 近年御府内へ入り込み、[ d ]等借請居(かりうけお)り候者の内ニハ妻子等もこれ無く、一期(いちご)住み同様のものもこれ有るべし。左様の類(たぐい)ハ早々[ e ]へ呼戻し申すべき事。(「牧民金鑑」)
注)身上相仕舞い…所帯をたたむこと、御府内…江戸、一期…一生涯
問6 空欄b・cに入る語として正しい組み合わせを、次の1~4のうちから一つ選べ。
1b-宿場 c-江戸
2b-在方 c-江戸
3b-江戸 c-在方
4b-在方 c-宿場
問7 空欄d・eに入る語として正しい組み合わせを、次の1~4のうちから一つ選べ。
1d-田畑 e-屋敷
2d-裏店 e-屋敷
3d-裏店 e-村方
4d-屋敷 e-村方
問8 史料Bに示された政策の説明として正しいものを、次の1~4のうちから一つ選べ。
1 この政策は、社会不安の要因である下層町人の人口減少を目的としていた。
2 この政策は、江戸・大坂周辺の大名・旗本領を幕府の直轄地にすることを目的としていた。
3 この政策により、町入用(町費)の節約分の7割を積み立て、災害や飢饉に備えさせた。
4 この政策により、初めて住民の宗旨と戸籍が調査され、それを記録した帳簿が作成された。
(答:1)
問9 史料Bの政策が出された時期の出来事として誤っているものを、次の1~4のうちから一つ選べ。
1 幕府は67年ぶりに日光社参を実行したが、大出費による財政悪化を招いた。
2 幕府は庶民の風俗を厳しく取り締まり、歌舞伎の江戸三座を浅草のはずれに移転させた。
3 北町奉行の遠山金四郎は江戸市中の改革をめぐり、南町奉行の鳥居耀蔵と対立した。
4 幕府は川越・庄内・長岡の3藩の領地を入れ替える転封を実行し、幕府の力を示した。
(答:4)
問10 史料Bの政策が出された前後の時期のことがらI~Ⅲについて、古い順にならべたものとして正しいものを、次の1~4のうちから一つ選べ。
Iオランダ国王の開国勧告
Ⅱモリソン号事件
Ⅲ天保の薪水給与令
1Ⅲ-Ⅱ-I 2I-Ⅲ-Ⅱ
3Ⅱ-Ⅲ-Ⅰ 4Ⅱ-I-Ⅲ」
(答:問6→2、問7→3、問8→1、問9→4×庄内藩の農民の反対などで実施できず、問10→3 ※Bは「人返しの法」について書いている)
〈2016慶大・経済B方式
問3 下線部C天保の改革に関する以下の問に答えなさい。
次の資料は、天保の改革の一環として幕府が発した法令の一部である(必要に応じて文章の一部を省略し、表現を変更した)。幕府がこの法令を発した意図を〔解答欄B〕の所定の欄の範囲内で説明しなさい。
菱垣廻船積問屋どもより、是迄年々金一万二百両ずつ冥加上金納め致し来たり候所、…以来上納に及ばず候、尤も向後右仲間株札は勿論、此外にも都て問屋仲間ならびに組合などと唱え候義は相成らず候
[資料出所]『江戸町触集成』
〔解答例〕物価騰貴の原因は、株仲間による商品流通独占によるとして、株仲間外の商人や在郷商人らの自由な取引による物価引下げを期待し株仲間の解散を命じた。(70字)〉
[ポイント]
1.天保の改革期に、天保の薪水給与令・倹約令・棄捐令が出され、人情本の為永春水の処罰、将軍家慶の日光社参がおこなわれ、印旛沼干拓が試みられた。
[解説]
1.忠邦は享保・寛政の改革にならい、まず将軍・大奥もふくめた断固たる倹約令を出して、ぜいたく品や華美な衣服を禁じ、庶民の風俗もまたきびしく取り締まった。高価な菓子・料理なども禁じたほか、江戸の211軒あった寄席を15軒に減らし、江戸の歌舞伎(三座)を浅草のはずれに移転させ、役者が町を歩く時には編笠をかぶらせた。また1842年、人情本作家の為永春水らも処罰(手鎖50日)した。
2.印旛沼の堀割工事による干拓にも、再度取組みがなされたが、忠邦が失脚すると、工事は中止された。
3.アヘン戦争の結果を知った幕府は、異国船打払令を緩和し、1842年、天保の薪水給与令を出した。
4.また物価騰貴は、旗本や御家人の生活も圧迫したので、幕府は、1843年に、棄捐令を出し、あわせて札差などに低利の貸出しを命じた。このような生活と風俗へのきびしい統制と不景気とがかさなり、人びとの不満は高まっていった。
5.1843(天保14)年には、将軍家慶が67年ぶりに日光社参を実行して幕府権力の起死回生をはかろうとしたが、大出費による財政悪化と、夫役に動員された農民たちの不満をもたらすだけの結果となった。
〈2016明大・文
問9 史料Bの政策が出された時期(天保の改革)の出来事として誤っているものを、次の1~4のうちから一つ選べ。
1 幕府は67年ぶりに日光社参を実行したが、大出費による財政悪化を招いた。
2 幕府は庶民の風俗を厳しく取り締まり、歌舞伎の江戸三座を浅草のはずれに移転させた。
3 北町奉行の遠山金四郎は江戸市中の改革をめぐり、南町奉行の鳥居耀蔵と対立した。
4 幕府は川越・庄内・長岡の3藩の領地を入れ替える転封を実行し、幕府の力を示した。」
(答:4×庄内藩の農民の反対などで実施できず)〉
〈2012関西学院大・済国際総合
問5.下線部e天保の改革で行なわれた施策として、誤っているものを下記より選びなさい。
ア.倹約令を出し、華美な衣服などを禁じ、風俗の取締を行なった。
イ.商品流通の独占を回避するために、人返しの法を定めた。
ウ.諸藩の専売制を禁じた。
エ.将軍の権威を示すため、日光社参を行なった。」
(答:イ×江戸に流入する貧民などに対する人口抑制策)〉
【ベック式!日本文化史ゴロ合わせ暗記術】
【ベック式!魔法の日本史実況中継 (古代編)】
【ベック式!魔法の日本史実況中継 (中世編)】
【ベック式!魔法の日本史実況中継 (近世編)】
【ベック式!魔法の日本史実況中継 (近・現代編)】

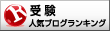
受験 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ
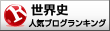
世界史 ブログランキングへ



















