 ドッペルゲンガー Doppelgänger
ドッペルゲンガー Doppelgänger
自分自身の姿を自分で見る幻覚の一種。自己像幻視。
さて、いよいよ開始する読者企画、ドッペルゲンガー。この企画については色々と前ふりがあるんだけど、なにしろ今回とりあげる女子バレーと「冬のソナタ」は旬、というか腐りやすいネタなので(笑)、とりあえず速攻で特集。
※すでに2004年のネタなので速攻もへったくれもないことをおわびします。
……アテネ予選は人気大爆発。巨人戦を蹴散らして視聴率30%ゲット。まことにおめでたい。でも、わたしはほとんどその中継を見ることはなかった。面白そうではある。実際見ればエキサイトするんだろう。メンバーを見渡してもかなりレベル(何の?)は高いし。それではいったい何故?
答は「余計な連中が出ているから」。今回はNEWSだっけか。視聴率のためなんだろうけど、なんでジャニーズのプロモーションにスポーツが奉仕しなければならないんだっ!
 ま、それはともかくドッペルゲンガー。似ている度合いによってわたくしが勝手に判定します。採点は1~5。単位はドッペル(Dp)。今つくりました(笑)。栄えある第1号はかのプリンセスメグ(誰だこんなニックネームつけたの)栗原恵。そっくりなのはわたしは見てないんだけど「冬のソナタ」のヒロイン、ユジン役のチェ・ジウだそうです。うーんこれを平均の3ドッペルにしておこうか。
ま、それはともかくドッペルゲンガー。似ている度合いによってわたくしが勝手に判定します。採点は1~5。単位はドッペル(Dp)。今つくりました(笑)。栄えある第1号はかのプリンセスメグ(誰だこんなニックネームつけたの)栗原恵。そっくりなのはわたしは見てないんだけど「冬のソナタ」のヒロイン、ユジン役のチェ・ジウだそうです。うーんこれを平均の3ドッペルにしておこうか。
次号はバレーボール篇第2セット。










 温暖化
温暖化 そのCGに比べてドラマが弱いと非難する向きも多いようだ。でもわたしはそちらにも夢中だった。だってあの「遠い空の向こうに」の
そのCGに比べてドラマが弱いと非難する向きも多いようだ。でもわたしはそちらにも夢中だった。だってあの「遠い空の向こうに」の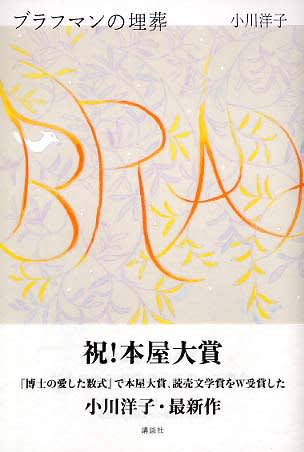 装幀も含め(装画は
装幀も含め(装画は




