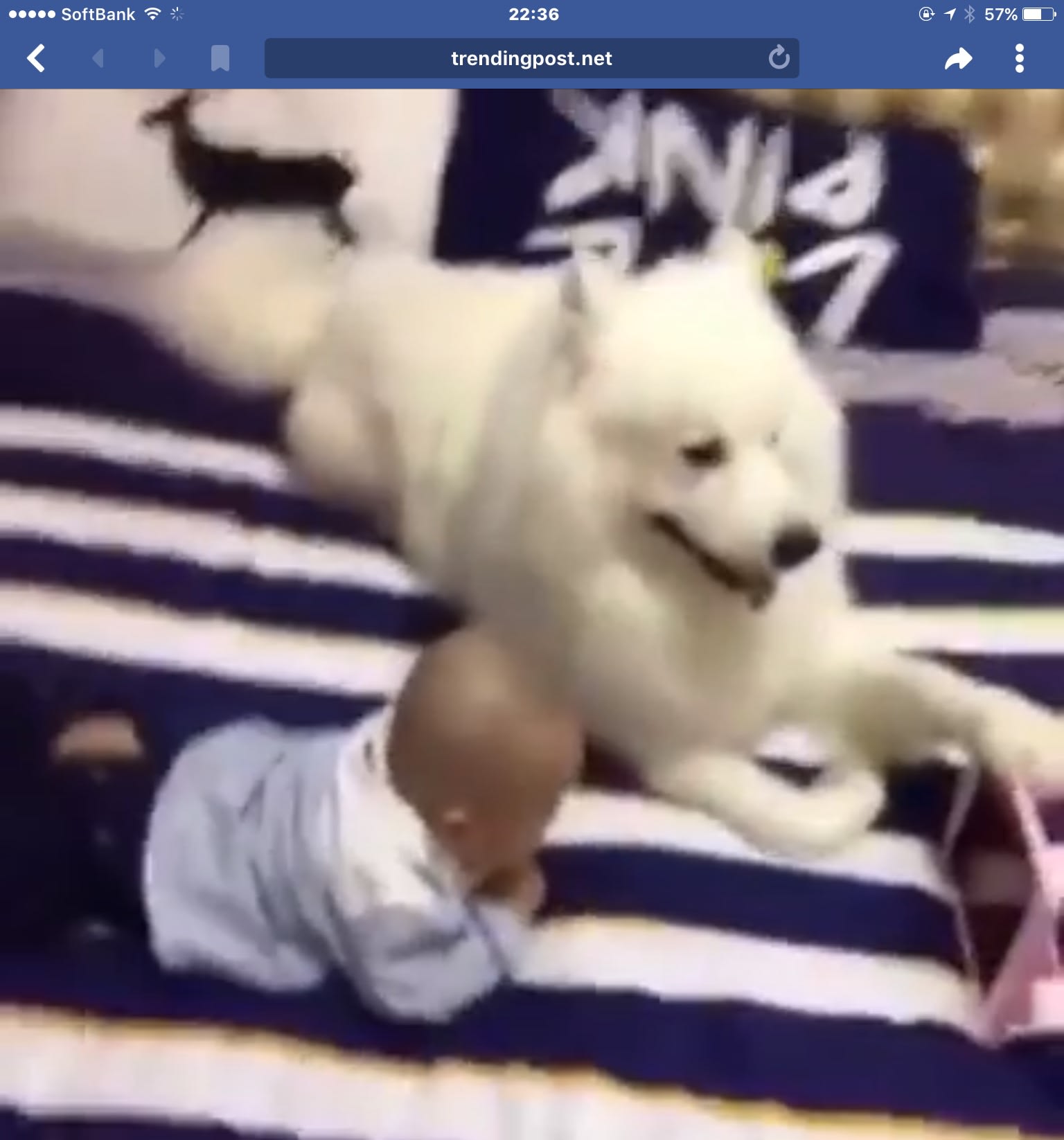昨日の続きです、不破さんの「この注を見て、私がまず感じたのは、」の続きです。
《 マルクスは、1865年に地代論に関連して日本問題を研究したあとも、日本での動きに引き続き注意をはらっていたのだな、ということです。この「通商報告書」(昨日の引用文のこと)は、そのすぐあとの「輸送費」のところで、イギリスやニューヨークから上海までの船荷運賃の問題でも参照されていますから、マルクスにとって、東アジアの経済事情を知る貴重な情報源の一つだったのでしょう。「神奈川」、つまり今日の横浜が、『資本論』の草稿に登場していた、というのも、興味がひかれる事実でした。
その「神奈川」の開港は、1859年(安政六年)六月のことでした。いったい、幕末の「神奈川」に、在庫論の観点からマルクスの関心をひくようなどんな事態が起きていたのか? 神奈川開港後の貿易事情については、例のオールコック『大君の都』で、こんな叙述にぶっかりました。
「開港後最初の1ヵ年間に通商の面で実際に達成されたことにかんしていうと、日本は中国製品と競争して、有利に本国市場〔イギリス市場のことーー不破〕へもたらすことができるような品質と価格の茶と絹を供給しうるということがはっきり確認された。過去12ヶ月間に輸出された約一万五千箱の茶と三千梱を上回る絹とは、本国市場における販売価格とその利益からして、それらが十分かかる競争の仲間入りができるということを証明した。……〔次年度には〕三千梱は一万八千梱に増大した……」(『大君の都』岩波文庫・中、121ページ)。
生糸輸出の急増はさらに続きます。幕府が輸出制限の措置をとったため、1861年(文久元年)には少し落ち込みますが、イギリスなどの抗議でこの処置が撤回されると、これまで以上の勢いで増加しました。『横浜市史』によると、神奈川港からの生糸出荷額は、1860年の259万ドルから1865年の1461万ドルへと、五年間に5.6倍にも急増はしました(山崎隆三「幕末維新期の経済変動」、『岩波講座 日本史 13』による)。日本の生糸生産がこれだけ急増する輸出量をまかないうるということは、買いつけにあたったイギリス商人には意外な出来事でした。綿製品などの売り込みがこの輸出増に追いつけないで、開港いらいの数年間は、「神奈川港」では、大幅な輸出超過がつづきました。これが逆転するのは生糸輸出が減退する1867年(慶応三年)以後のことです。そのために、資金調達に苦労するなどの「誤算」も、イギリス商人の側に起きたのでしょう。
「通商報告書」によると、イギリス側は、生糸の供給量のこの急増を、「巨大な在庫」があったため、と思いこんだようです。オールコックも、生糸の在庫ではないが、日本では、国内需要がかぎられていたから、大量の繭が加工されないまま放置されていた、つまり、生糸の原料の在庫が巨大だったからだとの解説をくわえています。「外国貿易用のこの主要産物〔茶ーー不破〕は、追加栽培しなくても従来輸出された量を無限に増加しうると信ずべきあらゆる理由が存している。日本人みずからが、国内消費以外に需要がないから、すべての葉がつみとられたことはなく、また絹の方もすべての繭が糸車に巻かれることはない、といっている」(『大君の都』中、121ページ)。
しかし、実際の事情は、この説明とはまったく違っていました。ある計算によると、開港後の三年間の日本の生糸輸出は年平均121万5000斤でしたが、これにたいし生産額は開港前の平年産額で112万5000斤にすぎず、国内生産量のほとんど全部かそれ以上を輸出していたとされます。まさに、全国で生産される生糸の出荷が神奈川に集中していたわけで、そのために、京都の西陣など全国各地の機業地は生糸の不足と糸価の急騰で大打撃をうけた、というのが実情でした。幕末日本の貿易事情はこんなことだったようですが、ともかくマルクスは、『資本論』のなかで、日本の状況を追い続けていたのです。》