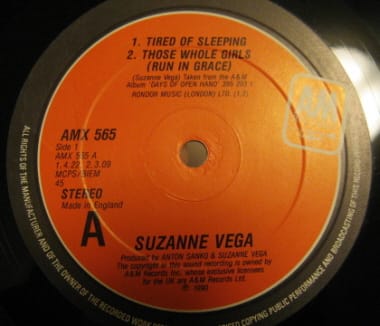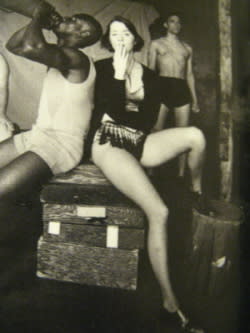私にとっての日々「より異なる地点へと」向かっていったニューウェイヴ/テクノは1986年末を持って終わった。
他の一般音楽の中に溶解していったような感じであった。
そこには、二年浪人した末の葛藤が精神分裂症と同じ症状として現れ、自分の中のコントロールが効かなくなり、自分の体内が自分を殺しに来るという妄想として現れ苦しみの末、自害しようとしたが失敗に終わり・・・病院通いが始まり、弛緩剤によるヘロヘロな状態に麻痺されていたのが、1986→1987年への峠の時期だったのが、重なっている。
これは私個人の私的状況だったが、そこから自分にとって終わってしまった音楽について、積極的には聴かず(それは妄想を助長するため)、雑誌も買わず、音楽シーンともサヨナラを告げた。
それ以降、雑誌を見たり・チャートを見たり・リアルタイム性のある音楽シーンを無理して追い掛けたり・・・そういう行動から「降りた」。
偶然との出会いというものが、その後の自分の音楽の集積となる。
ある種の呪縛からの開放。
***
とはいえ、日本に居る以上、音を避けて通るわけにもいかず、遠目で見ながら、時折、ラジオから流れていた、過去お世話になったミュージシャンの動向は気がかりではあった。

トーマス・ドルビーは1984年に「ザ・フラット・アース」を発表後、なかなか新作を出さなかった。
浪人の頃には、映画「ハワード・ザ・ダック」のサウンドトラックに創った『ドンド・ターン・アウェイ』がとても好きで聴いていた。
この曲では、スティーヴィー・ワンダーが吹くハーモニカが素晴らしくグッと来た。
また「ドルビーズ・キューブ」というユニット?らしき名義で出した『キューブは貴方とともに』も聴いた。
この曲には、ファンクの影響が強く、目立って優れた曲では無かったが、カセットにエア・チェックして聴いていた。
彼の3枚目のオリジナル・アルバムは、1988年に発表された。
気になってFMの特集を聴いたが、ピンと来ないのと・がっかり感と・・・そして「やっぱりニューウェイヴは明らかに崩壊したんだな」と確信した。
レコード盤のジャケットを見て、まず「一体、何をやってんだ!」という落胆と怒りがあった。

【サード・アルバム「エイリアン・エイト・マイ・ビュイック」】
***
どうやらドラマ仕立てにしたらしく、宇宙人が自分の愛車を飲み込んでしまった、とのことで、裏ジャケットには、ハンバーガーショップから出てきて置いていた車の所に行ったら車の本体が消えていて、ポテトやコーラを持って唖然とするトーマス・ドルビーのコミカルな姿。
「誰もこんなことを、君に望んでいないよ」そう自分は言いたかった。
知的でメロディアスな音楽を創り出し、憧れだったトーマス・ドルビーの姿は、もうそこには無かった。

いくらUFO好きの自分でも、彼がこの時点で明らかにアメリカ受けの視点で、こういった下世話なジャケットと、フェラーリがどうしたこうした・・・と大して出来の良くない曲を並べている様は、完全に彼自身が持っていた資質を殺していると思ったし、イギリス・ニューウェイヴィーの恥だと思った。
「お前までもが寝返り、裏切ったのか」そういう想いで一杯になった。
そこから相当な間、彼のこのアルバムを「そういうもんだ」と思って、悪夢として見捨ててきた。
***
再び聴くに至るのは、90年代以降のこと。
と言ってもA面から聴く自分は、その段階で、何度かのトライで、即パスしていた。
素晴らしい曲があると発見したのは、2000年以降のこと。
B面に「The Ability To Swing」と「Budapest By Blimp」を発見。

特に「Budapest By Blimp」の素晴らしさは、このジャケットさえ無ければ、音だけ聴くことが出来たら、もっと早く発見出来たかもしれない。
しかし、音楽というのも一期一会。
会えなかったのには、ちゃんと理由があって、そこから離れた地点で出会えたのも、何かがあるのだろう。
1988年当時ラリっていた自分とは全く異なる時代と状況の中で、今の自分の中では「Budapest By Blimp」は、自分好みの名曲と言える。
トーマス・ドルビーの面目躍如。
彼にしか書けないこういう曲を中心として、アルバムを創れば良かった。
しかし、それも時代の流れの中での彼のその時の判断だったのだから、仕方が無かったのだろう。
THOMAS DOLBY 「Budapest by Blimp」
街路の曲がり角で、君の名を呼ぶ 流れてくる僕ら二人の調べ・・・
小さな手が僕をつかむ 炎のように 月の満ち欠けのごとく、蒼白く
カフェで、ショッピング・モールで、君の幻を見る
幻は黄昏の露の上に、霧と消える
しかし本と写真は同じものとは言えないさ
あの列車はもうすぐに出発してしまう
・・・・・保守主義者の、ブダペスト
柱や宮殿の上でもどこででも、君の手を握っていよう、霧が晴れるまで・・・
僕がどんなに遠く彷徨ってきたかを理解するより
もっと強く抱きしめているのがいいと思う
悲劇を目の当たりにしてもなお、偉大なる幻想の死を知るのはあまりにつらいから
僕らはその宝を嘲り、その輝きを掠め取った
学校では教えられなかったんだ
・・・・・多分、忘れることのほうが簡単なのよ
私が旅立つ理由を知るよりはね
過去から剥ぎ取ったページなの
列車は離れて行くわ、この霧から
・・・・・保守主義者の、ブダペスト
さて、紳士淑女の皆さん、ご紹介したいものがあります
どうぞ、とくとご覧あれ
このしわくちゃの地図とダイヤグラムは、歴史書から破いた1ページ
時の中で凍りついた、掛け替えのない古代の遺物
ユダヤの灰の上に築かれているのが分かるかい
君の好奇心を満足させようか?
華麗なる美は、ズールー族の血で署名されたんだよ
まったく上げ足歩調どころか、びっこ引いてるじゃないか
…保守主義者の、ブダペスト
他の一般音楽の中に溶解していったような感じであった。
そこには、二年浪人した末の葛藤が精神分裂症と同じ症状として現れ、自分の中のコントロールが効かなくなり、自分の体内が自分を殺しに来るという妄想として現れ苦しみの末、自害しようとしたが失敗に終わり・・・病院通いが始まり、弛緩剤によるヘロヘロな状態に麻痺されていたのが、1986→1987年への峠の時期だったのが、重なっている。
これは私個人の私的状況だったが、そこから自分にとって終わってしまった音楽について、積極的には聴かず(それは妄想を助長するため)、雑誌も買わず、音楽シーンともサヨナラを告げた。
それ以降、雑誌を見たり・チャートを見たり・リアルタイム性のある音楽シーンを無理して追い掛けたり・・・そういう行動から「降りた」。
偶然との出会いというものが、その後の自分の音楽の集積となる。
ある種の呪縛からの開放。
***
とはいえ、日本に居る以上、音を避けて通るわけにもいかず、遠目で見ながら、時折、ラジオから流れていた、過去お世話になったミュージシャンの動向は気がかりではあった。

トーマス・ドルビーは1984年に「ザ・フラット・アース」を発表後、なかなか新作を出さなかった。
浪人の頃には、映画「ハワード・ザ・ダック」のサウンドトラックに創った『ドンド・ターン・アウェイ』がとても好きで聴いていた。
この曲では、スティーヴィー・ワンダーが吹くハーモニカが素晴らしくグッと来た。
また「ドルビーズ・キューブ」というユニット?らしき名義で出した『キューブは貴方とともに』も聴いた。
この曲には、ファンクの影響が強く、目立って優れた曲では無かったが、カセットにエア・チェックして聴いていた。
彼の3枚目のオリジナル・アルバムは、1988年に発表された。
気になってFMの特集を聴いたが、ピンと来ないのと・がっかり感と・・・そして「やっぱりニューウェイヴは明らかに崩壊したんだな」と確信した。
レコード盤のジャケットを見て、まず「一体、何をやってんだ!」という落胆と怒りがあった。

【サード・アルバム「エイリアン・エイト・マイ・ビュイック」】
***
どうやらドラマ仕立てにしたらしく、宇宙人が自分の愛車を飲み込んでしまった、とのことで、裏ジャケットには、ハンバーガーショップから出てきて置いていた車の所に行ったら車の本体が消えていて、ポテトやコーラを持って唖然とするトーマス・ドルビーのコミカルな姿。
「誰もこんなことを、君に望んでいないよ」そう自分は言いたかった。
知的でメロディアスな音楽を創り出し、憧れだったトーマス・ドルビーの姿は、もうそこには無かった。

いくらUFO好きの自分でも、彼がこの時点で明らかにアメリカ受けの視点で、こういった下世話なジャケットと、フェラーリがどうしたこうした・・・と大して出来の良くない曲を並べている様は、完全に彼自身が持っていた資質を殺していると思ったし、イギリス・ニューウェイヴィーの恥だと思った。
「お前までもが寝返り、裏切ったのか」そういう想いで一杯になった。
そこから相当な間、彼のこのアルバムを「そういうもんだ」と思って、悪夢として見捨ててきた。
***
再び聴くに至るのは、90年代以降のこと。
と言ってもA面から聴く自分は、その段階で、何度かのトライで、即パスしていた。
素晴らしい曲があると発見したのは、2000年以降のこと。
B面に「The Ability To Swing」と「Budapest By Blimp」を発見。

特に「Budapest By Blimp」の素晴らしさは、このジャケットさえ無ければ、音だけ聴くことが出来たら、もっと早く発見出来たかもしれない。
しかし、音楽というのも一期一会。
会えなかったのには、ちゃんと理由があって、そこから離れた地点で出会えたのも、何かがあるのだろう。
1988年当時ラリっていた自分とは全く異なる時代と状況の中で、今の自分の中では「Budapest By Blimp」は、自分好みの名曲と言える。
トーマス・ドルビーの面目躍如。
彼にしか書けないこういう曲を中心として、アルバムを創れば良かった。
しかし、それも時代の流れの中での彼のその時の判断だったのだから、仕方が無かったのだろう。
THOMAS DOLBY 「Budapest by Blimp」
街路の曲がり角で、君の名を呼ぶ 流れてくる僕ら二人の調べ・・・
小さな手が僕をつかむ 炎のように 月の満ち欠けのごとく、蒼白く
カフェで、ショッピング・モールで、君の幻を見る
幻は黄昏の露の上に、霧と消える
しかし本と写真は同じものとは言えないさ
あの列車はもうすぐに出発してしまう
・・・・・保守主義者の、ブダペスト
柱や宮殿の上でもどこででも、君の手を握っていよう、霧が晴れるまで・・・
僕がどんなに遠く彷徨ってきたかを理解するより
もっと強く抱きしめているのがいいと思う
悲劇を目の当たりにしてもなお、偉大なる幻想の死を知るのはあまりにつらいから
僕らはその宝を嘲り、その輝きを掠め取った
学校では教えられなかったんだ
・・・・・多分、忘れることのほうが簡単なのよ
私が旅立つ理由を知るよりはね
過去から剥ぎ取ったページなの
列車は離れて行くわ、この霧から
・・・・・保守主義者の、ブダペスト
さて、紳士淑女の皆さん、ご紹介したいものがあります
どうぞ、とくとご覧あれ
このしわくちゃの地図とダイヤグラムは、歴史書から破いた1ページ
時の中で凍りついた、掛け替えのない古代の遺物
ユダヤの灰の上に築かれているのが分かるかい
君の好奇心を満足させようか?
華麗なる美は、ズールー族の血で署名されたんだよ
まったく上げ足歩調どころか、びっこ引いてるじゃないか
…保守主義者の、ブダペスト