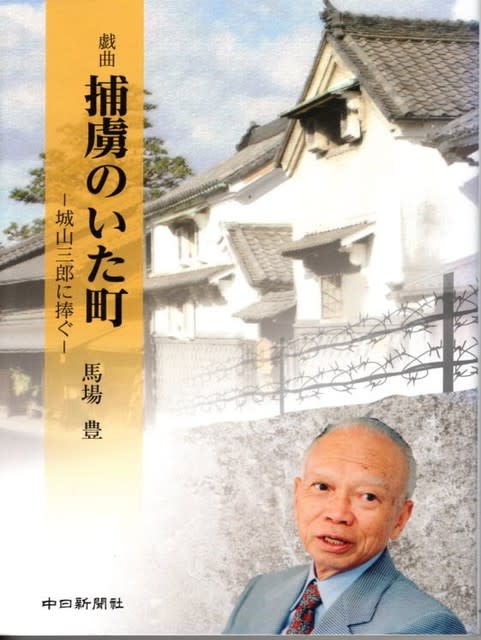年金者組合の方から緑区のお城の紹介をしてほしい、支部ニュースで連載してくれないか、という依頼がありました。年金者組合というのは、年金をもらっている方々が、正当に年金がもらえるようにと制度の拡充の為に活動している組合です。そればかりではなく、カラオケ、卓球、俳句、歌声、絵画など集まって趣味の世界を充実させている団体のようです。
せっかくなので、お受けすることにしました。緑区のお城と言ってもほとんどは桶狭間の戦い関連のものです。今川方の鳴海城、大高城、それに対抗して織田方の丹下砦、善照寺砦、中島砦、鷲津砦、丸根砦とまあ、これくらいでしょうか。これらを順に紹介していけたらいいかなあと思います。
第1回 鳴海城
桶狭間の戦いで今川側の武将岡部元信が守った城
鳴海城は、名鉄鳴海駅から歩いて10分弱のところにあります。今は城跡公園になっています。

この城は根古屋城とも言い、1390年代に築城されたそうです。もともとは織田側のお城でしたが、1560年の桶狭間の闘いでは、今川側の武将岡部元信(もとのぶ)が守っていました。この岡部元信は、今川義元が討たれたとの知らせを受けても、最後まで織田勢とたたかい、義元の首をもらい受けるという条件でようやく城を明け渡したそうです。岡部元信の後は佐久間信盛(のぶもり)、正勝(まさかつ)が城主となりましたが、1590年廃城となりました。作町は佐久間という名前の名残だそうです。

公園はちょうど本丸にあたります。公園南側に曲輪や切岸の跡が見受けられます。そしてこの公園をぐるりと一周している道は、その形から堀だったと考えられます。北にある東福院には城門の梁を使用しているという山門があります。

せっかくなので、お受けすることにしました。緑区のお城と言ってもほとんどは桶狭間の戦い関連のものです。今川方の鳴海城、大高城、それに対抗して織田方の丹下砦、善照寺砦、中島砦、鷲津砦、丸根砦とまあ、これくらいでしょうか。これらを順に紹介していけたらいいかなあと思います。
第1回 鳴海城
桶狭間の戦いで今川側の武将岡部元信が守った城
鳴海城は、名鉄鳴海駅から歩いて10分弱のところにあります。今は城跡公園になっています。

この城は根古屋城とも言い、1390年代に築城されたそうです。もともとは織田側のお城でしたが、1560年の桶狭間の闘いでは、今川側の武将岡部元信(もとのぶ)が守っていました。この岡部元信は、今川義元が討たれたとの知らせを受けても、最後まで織田勢とたたかい、義元の首をもらい受けるという条件でようやく城を明け渡したそうです。岡部元信の後は佐久間信盛(のぶもり)、正勝(まさかつ)が城主となりましたが、1590年廃城となりました。作町は佐久間という名前の名残だそうです。

公園はちょうど本丸にあたります。公園南側に曲輪や切岸の跡が見受けられます。そしてこの公園をぐるりと一周している道は、その形から堀だったと考えられます。北にある東福院には城門の梁を使用しているという山門があります。