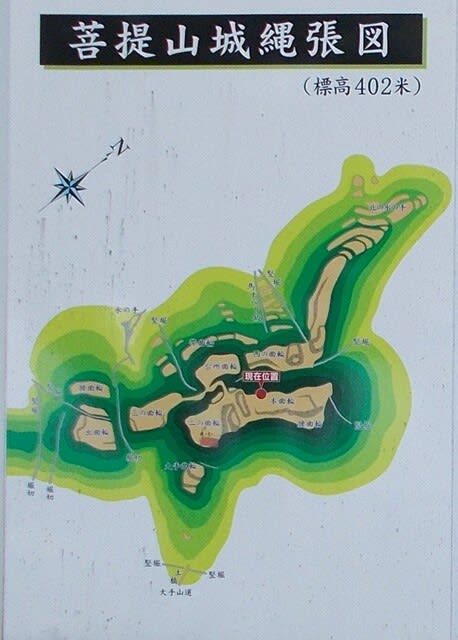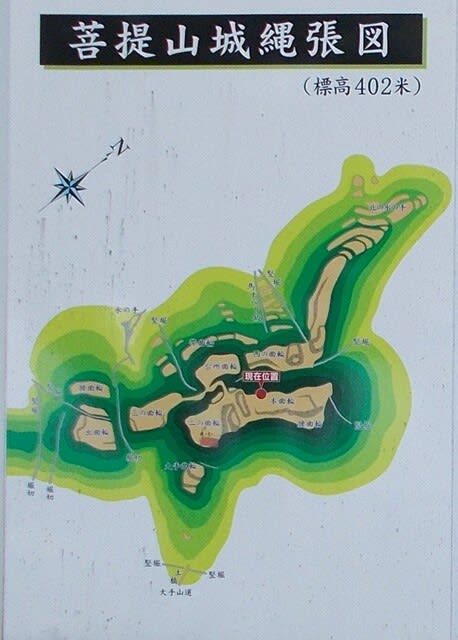3月22日に松尾山に登りましたが、松尾山城の詳しい様子は紹介していなかったので、改めて紹介します。
なお、2017年に関ヶ原に行ったときに松尾山に登り、ブログで紹介していますので、参考まで。
関ヶ原古戦場(8) 岐阜県
山城として
松尾山城は、現地案内によれば、応永年間(1394~1428)に小守護(守護代の家臣?)富島氏が城を築いたとあります。また、元亀(げんき)元年(1570)には浅井長政が織田信長に対する前線基地として樋口直房(ひぐちなおひさ)をこの城に入れたそうです。しかし樋口直房は調略により織田信長方に寝返り、松尾城には信長の家臣不破光治(ふわみつはる)があらたに配されました。ところが、中井均氏によると、現在の城郭遺構を考えた場合それ以降の改修があったのではないかと言います。

本丸の掲示板(城の歴史を記載している)
関ケ原の戦いの城として
中井氏によれば、この城は関ヶ原の戦いにおいて毛利輝元(もうりてるもと)の城(つまり西軍の本拠地)として、石田三成が大垣城主伊藤盛正(いとうもりまさ)に築かせたそうです。慶長5年(関ヶ原の戦いの年)8月10日に築城を命じ、そのまま守備につかせることにしたそうです。しかし、9月14日、石田三成の意思を無視した形で小早川秀秋(こばやかわひであき)が、守備していた伊藤盛正を追い出して陣を構えたということです。関ケ原の戦いは、翌15日に開戦します。

小早川秀秋(ウィキペディアから)
腰曲輪
松尾山城の本丸にたどり着くちょっと手前に腰曲輪があります。曲輪の周りには土塁が巡り、先端が段々になっています。そしてその先を堀切で切っています。こうした曲輪がこの曲輪の南の方にも見られます。城の東側を守る役割をしていたようです。

腰曲輪
本丸
【土塁】本丸でまず目につくのは周囲をぐるっと土塁が巡らされていることです。これだけでもただの陣ではないと分かります。

本丸
【眺望】さらに、ここから関ヶ原を一望することができます。小早川秀秋がここで戦況を見ながら、裏切るかどうか迷っていて、徳川家康の「問い鉄砲」で裏切ることを決意したというのは江戸時代の軍記物(ぐんきもの)の話で、実際は合戦が始まると同時に裏切り行為に及んだようです。

本丸から関ヶ原を望む(当時木は切られていて、なかったものと思われます)
【枡形虎口】本丸の南側に枡形虎口(ますがたこぐち)があります。枡形虎口は戦国時代の後の方で造られることが多いです。この松尾山城の本格的な改修が関ヶ原合戦の前あたりだと考えられているのは、この虎口があることが一つの理由だと思います。

本丸の枡形虎口
【竪堀】本丸から北の方に一本竪堀(たてぼり)が入っています。これも戦国時代の後期に造られることが多い構造物です。したがって、この竪堀も関ヶ原の戦いに関してのものと思われます。

本丸北の竪堀(撮影したところより下方にも延びていました)
松尾山城 つづく