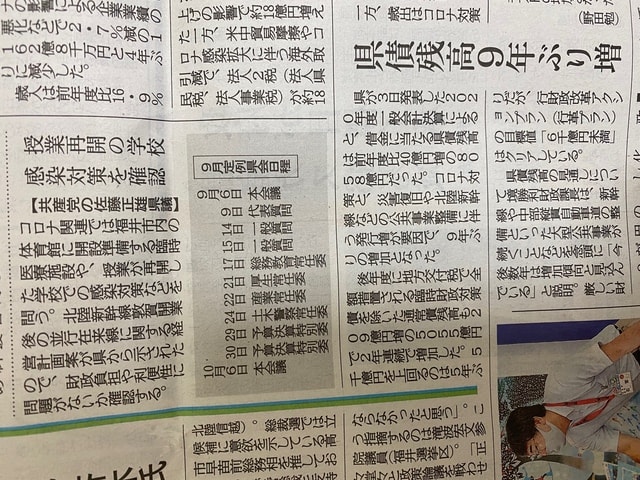2021年6月28日 福井県議会総務教育常任委員会 総務部関係審査での佐藤正雄委員の質疑を紹介します。
核燃料税について
◯佐藤委員 第53号議案であるけれども、核燃料税についてであるが、前回の核燃料税の改定のときにもいろいろ問題提起をさせてもらったが、こういう税金の取り方というのは、ほかの産業の分野にはない特殊な税金を企業に対して課税するやり方なわけである。関西電力とも日本原電から了解を得たという報告はされているが、関西電力は発電所を営業運転されている。日本原電は発電所を営業運転できていないという状況である。発電所を営業できていない日本原電についても課税額を上げるというのは、これは妥当性はあるのだろうか。
◯税務課長 今まで核燃料税の基本的な考え方として、財政需要を説明申し上げたかと思うが、原発が稼働している稼働していないにかかわらず、安全対策等必要であって、そういった意味で財政需要があるというところで、設計をしている。
◯佐藤委員 そうすると、発電所は要するに平たく言えば企業として利益を上げていない、上げていようがいまいが課税はするのだと、増税するのだということになると、行く行くは福井県、例えば関西電力も原子力発電が全て廃止作業に入って、発電収入がなくなる、原子力の事業収益がなくなるというときにも同じ発想でいかれるということなのか。
◯税務課長 要するに原子力発電所を設置して営業されるというところで、私ども運転と廃炉は一体であるという言い方をさせていただいているけれども、もともと運転を始めてから廃炉になるまでを一連の原子力発電所の設置運営と捉えているので、それも含めて、やはり財政需要としてはみていきたいと考えている。
◯佐藤委員 であるから、ほかの産業には見られない特殊な税金のかけ方ではないかと、最初に主張したのはそういうことなわけである。こういう形で関西電力に課税するのがいいとか悪いとかというのは別にして、収入を上げない事業者に対する課税というのはいかがなものかというのを、私は思う。
それともう一つは、これは例えばプルトニウム燃料を使って、より危険な原子力発電をする、プルトニウム発電の場合はプルサーマル使用済み燃料がまだどこにも持ち出すことができないから、今のままでは未来永劫福井県内に留め置かねばならないと、こういうことになるわけであるけれども、そういうプルサーマル発電を拡大すれば拡大するほど税収が上がっていくと。要するに単価というか、燃料代が高いから上がっていくというやり方になってるわけである。であるから、結果的には福井県の気持ちとしてはプルサーマル発電を拡大して、税収に貢献してほしいと。今は例えば高浜原子力発電所だけだけれども、大飯原発でもやってくれないかと。そういうふうに逆に危険な発電を拡大するということに、税収が上がるということによって福井県政を歪めるということにならないか。
◯税務課長 制度設計に当たっては、核燃料の価格差があるというところを、殊さらそういうことで捉えているわけではなくて、今回の見直しに当たっても、価額割というのはどうしても稼働状況に応じて変動するというところもあって、むしろそれ以外のところの引上げということで、安定的な税収を確保するということで見直しをするところもある。MOX燃料の価格が高いとか、そういったことを考慮しているわけではない。
◯佐藤委員 この件はもう終わるけれども、搬出促進割を上げても結果的には搬出に対する強力なプレッシャーにあまりなってないわけである、であるから、そういう点では甚だ税の効果も疑問だということは指摘しておきたいと思う。
福井県立大学の学長、理事長職のあり方
それからもう一点、よろしいか。第60号議案、第61号議案は県立大学についてなのだが、出資と定款の一部変更、これ異議はないが、ちょっとマスコミの報道なのだけれども、理事長から離職というか、そういう願いが出されているという報道があった。それで、福井県立大学は理事長と学長という、経営と学問というような体制になっていると思うのだが、これはいろんなこの間、理事長職の在り方というのは検討されたのだろうか。
◯副部長(大学私学) 県立大学には定款があって、その中で理事長の役割、それから学長の役割を定めている。それに基づいて、日々の大学の運営であるとか、教育というものを進めているという状況である。
◯佐藤委員 そういうことはもちろん分かってるわけであるが、県の幹部職員であった方が理事長になられるというパターンが多いわけである。今回もそういうことで、途中で辞められるというような報道がある。そうなるかどうか分からないが。改めて理事長職の在り方というのを、せっかく県議会にこういう議案を出されるのであれば、在り方について再検討されたのかということをお尋ねする。
◯副部長(大学私学) 今回、委員の指摘の事例を捉まえて、在り方について検討したということはない。
◯佐藤委員 これは要望であるけれども、変な言い方であるけれども、理事長職と学長職と2つがどうしても必要なのかどうかというのは、いろいろ議論があってもいいかなという、個人的にはそう思う。もちろんそれぞれの役割、さっき言った経営と学問という役割を分担してされてるということはもちろん理解してはいるけれども、そういうことも含めて、今後検討されてはいかがかなというように思う。これは要望である。
公衆衛生分野の職員増員を
◯佐藤委員 部長報告2ページのところの一番下に、全国最少水準の職員数を基本として、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策などに人員を配置してきたとある。以前も厚生常任委員会のときに、保健師の数とかあるいは県の衛生環境研究センターの職員数とか、そういうのはどうしてもいわゆる行政改革の流れの中で、減らすとかそういう流れになってきたことは事実なので、やっぱりこういう状況を受けて、公衆衛生分野の職員の増員も必要ではないかということをお願いしたことがあるのだが、これはその後県庁内ではそういう専門職を増やすとか、増強するという話にはなっているのか。
◯人事課長 専門職という関係でいくと、今回児童相談所のほうになるが、こちらの虐待防止対応などで体制強化として、8名の増員を行っているところである。保健師についても、しっかりと欠員の補充であったりとか、そういったところで採用のほうをしっかり採っていきたいというふうに考えている。
◯佐藤委員 それは引き続き、衛生環境研究センターなんかの職員も含めてしっかりと目配りをしていただきたいと思う。
それと、健康福祉部だけではなくて、県庁全体がこれだけ1年以上も新型コロナの問題で対応、対応と、しかも土日なしに記者会見とかいろいろあるということは、部長とか副部長が記者会見すれば、2人だけ出勤すればいいというわけでもないだろうから、当然職員の人も何人も出勤されて対応されているだろうと思うが、これだけ1年半近くにわたって続いてるとかなり疲弊してきてるのではないかなというように思うのである。そういう点ではいわゆるAIの活用とか、実績があって業務を減らしたということがあったけれども、そうはいっても人手がかかるいろんな業務がある。以前だったら例えばマスクを配ろうというときに、お店に県の職員が交代で詰めて、マスク購入をサポートすると、そういうお仕事を県の職員がされたりしているし、今ならワクチン接種で現場のお手伝いをする。いろいろあると思うのだが、そういうのをもう少し、県の職員だけではなくて、ある意味ではボランティアでOBの方も含めて、単純作業の部分を少し動員というかお願いをして、現職の県の職員の1年半以上に続いてる疲弊感を少しフォローしていくということなんかは、考えられたらいかがだろうか。
◯総務部長 職員の業務の負担感というところであるけども、指摘いただいたとおり、コロナで1年以上各職員これまでにないような対応を求められているというところがあって、個々の職員含めて超勤の状況などについては、私ども人事担当部局としても、常日頃からよく見るようにはさせていただいているところである。その上で、ほかのところでやっていただけるとか、お手伝いできるところあるかとか、そういう形に庁内での仕事の分担というところもさせていただいているのがまず一つ。
その上で、委員指摘いただいた外の力の活用という点についても、新たに事業を行うときに、いわゆる外に予算的なものも含めてお願いできないかというところなどについては、一つ一つやらせていただいていて、そういった業務量が過剰にならないように、いろんなことを活用しながらやらせていただきたいというふうに思っている。
◯佐藤委員 いつまで続くか分からないけども、いずれにしても相当続いて、かなり疲れもたまっている状況であろうと思うので、その辺外部の力、OBの力をボランティア等で活用できるところはぜひ検討していただきたいと思う。
県立大学の拡大路線について
それから、県立大学でちょっと質問するが、確かに知事は正確じゃないかもしれないけど、一般質問の答弁で、人文系学部の設置も検討するというようなことをおっしゃったのである。これは具体的にどういうことなのか。
◯副部長(大学私学) 知事がお答えしたのは、現在県立大学の第3期中期計画の中に、次世代の地域リーダーを養成する学部の創設というのを掲げていて、それがまさしく文系の受皿になり得るということで、それについては現在学内でほかの大学と競合しないかとか、いろんな観点からその中身を検討しているということである。
◯佐藤委員 今、大学院なんかも新たに拡充する計画があるのか。
◯副部長(大学私学) 大学院については、その計画の中で、大学院看護学部の博士後期課程、今ちょうど修士まで作ったので、その後期課程をどうするかというのが検討課題として上がっている。
◯佐藤委員 要するに拡張路線である、この創造農学科も先端増養殖学科も拡張路線といえば拡張路線であるけども、しかし学部となると、学科とは違って文科省の大学設置・学校法人審議会の審査を通らなければいけないということで、ハードルが非常に高いというようにお聞きしているし、学部についても県立大学の中ではいろいろ人材、要するに博士課程作れば当然それの授業を受け持つ教員も必要になるわけであるから、非常に今のスタッフの状況で、大学院博士課程どうなのかという意見も出てるというようにお聞きしているのである。
であるから、思いはいろいろ、こういうのを作って福井県の将来を見据えてこうだとかいう思いはあるのだろうが、現場のスタッフとかが追い付いていかないと、何もならないということにもなるわけである。その辺はどういうふうにお考えなのか。
◯副部長(大学私学) 委員指摘のように、そこは非常に重要なポイントであって、やはり学内でしっかりやっていこうという意思決定をしていただくことが重要だと思う。やっぱり、世の中地域のニーズであるとか、大学としてそれをしっかりやっていける体制をどうしていくか、これはコストなんかも含めて、総合的にやっぱり検討していかなきゃいけないということであるので、ただそういったところについては学内で検討しているという状況である。
◯佐藤委員 学内的なそういう意見なんかに十分配慮いただきたいと思う。
県立高校と私立高校の定数に関して
最後にもう一点確認したいのだが、さっき教育委員会の議論があったのだけれども、これも教育長の本会議での答弁だったと思うが、県立学校のいわゆる志願状況は危機的だと認識しているということで、いろんな高校でも魅力化というのを進めるということで報告があった。この問題を考えるときに、マスコミさんも報道しているけども、私学はどんどん魅力的になってきてる、それは中身が魅力的なのもあるし、校舎、ハード面でも魅力的になってきているという両面があって、ちょっと古い学校よりも新しい私学に行きたいと、立派な校舎に行きたいとか、きれいだわとか、女性なんか特にそういうことにもなってくると思うのである。
そうした場合に、県も私学にも補助金出すし、県はもちろん県の施策でやってもらうということで、これは引き続き進めてほしいのだが、もう一つ問題は、定員問題があると思うのである。いわゆる公私、公立と私立の配分である。以前もここの委員会のときにちょっと言わせてもらったことがあると思うのだが、そこをちょっと一定考えていかないと、入学する生徒の総数はこれからちょっと減り気味になっていくと。そういうときに私学の定員だけはこれまでのままで、あるいは実際には定員よりもさらに多く入学者を迎え入れるという状況が続くと。県立のほうはどんどん定員を減らしたり、統廃合していくと。県立のほうは真面目に定員を守って入学者を取っていくということでは、なかなか実際にはアンバランスというのが生まれてくる面があると思うのである。であるから、県立も私学も両方とも共存共栄でもちろんやるということで、協議会を時々開いてはいると思うのだが、その辺を県としてはもうちょっとしっかりと、定員問題も含めて見ていってもらわないと、この問題の根本解決には至らないんじゃないかなと思うのだが、その辺はどうなのだろうか。
◯副部長(大学私学) 県立と私立の高校の問題であるけれども、私立学校の授業料の無償化というようなことも本格的に始めさせていただいた中で、やっぱり私学のほうにシフトしている、私学を第一希望に志望とする生徒さんが増えてきているという状況が実態である。
そうした中で、私学であるけれども、定員を全体としてみれば超過をしているという状況であるが、一つは私学の努力として、県内の高校生だけではやっぱり定員を確保できないということもあって、スポーツや文化等々に秀でた生徒を全国から一生懸命集めてきて、生徒を確保しているという状況もある。やっぱり県立と私立、それぞれに魅力を高めて切磋琢磨をしていく、そういった中で中学生にとって選択肢を少しでも広げていただくというようなことを、我々としてもしっかり私学サイドとして応援をしていきたいというふうに考えている。
◯佐藤委員 今答弁にあったように、切磋琢磨というのは知事もおっしゃる言葉だと思うのだが、結局私学が魅力的になっていけば、県立もそれに負けじと切磋琢磨して県立もよくなっていくという発想はあると思うのである。そういう面はあると思う。だけど、今言ったようにそもそも校舎の条件が、全くリニューアルして立派なのとぼろい校舎では、なかなか対等な競争にならない。入学定員にしても今言った問題があって、これもなかなか対等な競争にならない。今、スポーツと言われたけれども、要するに県立のほうは働き方改革ということで、教員の労働時間をきちっと管理するというようなことも含めてきちっとやっていくと。私学のほうは、それよりもまだ少し、言葉悪いけど緩い面があるというようなことがあれば、どうしてもお互いに切磋琢磨してって、言葉はいいのだけど、そのとおりになかなかならない面があるわけである。
であるから、私が言ってるのは両方とも共存共栄していかなきゃいけないわけだから、そういうスタンスに立てば、少しやっぱり定数問題とか含めて、県としても立ち入って議論をしていかないと、これは根本的な解決には至らないというか、そういう条件がどんどんどんどん違ったままで県立学校は私学と競争させられるというのでは、ある意味ではちょっと酷だなという面も出てくるのではないかというように思って質問しているので、最後にするからもう一度答弁をお願いする。
◯副部長(大学私学) 長期的には子どもたちの人口が減ってくる。そういった中で、常に私どももやってるけれども、引き続き教育委員会と定員の問題も含めて情報を共有しながら、あるいは協議しながらやっていきたいと思っている。
核燃料税について
◯佐藤委員 第53号議案であるけれども、核燃料税についてであるが、前回の核燃料税の改定のときにもいろいろ問題提起をさせてもらったが、こういう税金の取り方というのは、ほかの産業の分野にはない特殊な税金を企業に対して課税するやり方なわけである。関西電力とも日本原電から了解を得たという報告はされているが、関西電力は発電所を営業運転されている。日本原電は発電所を営業運転できていないという状況である。発電所を営業できていない日本原電についても課税額を上げるというのは、これは妥当性はあるのだろうか。
◯税務課長 今まで核燃料税の基本的な考え方として、財政需要を説明申し上げたかと思うが、原発が稼働している稼働していないにかかわらず、安全対策等必要であって、そういった意味で財政需要があるというところで、設計をしている。
◯佐藤委員 そうすると、発電所は要するに平たく言えば企業として利益を上げていない、上げていようがいまいが課税はするのだと、増税するのだということになると、行く行くは福井県、例えば関西電力も原子力発電が全て廃止作業に入って、発電収入がなくなる、原子力の事業収益がなくなるというときにも同じ発想でいかれるということなのか。
◯税務課長 要するに原子力発電所を設置して営業されるというところで、私ども運転と廃炉は一体であるという言い方をさせていただいているけれども、もともと運転を始めてから廃炉になるまでを一連の原子力発電所の設置運営と捉えているので、それも含めて、やはり財政需要としてはみていきたいと考えている。
◯佐藤委員 であるから、ほかの産業には見られない特殊な税金のかけ方ではないかと、最初に主張したのはそういうことなわけである。こういう形で関西電力に課税するのがいいとか悪いとかというのは別にして、収入を上げない事業者に対する課税というのはいかがなものかというのを、私は思う。
それともう一つは、これは例えばプルトニウム燃料を使って、より危険な原子力発電をする、プルトニウム発電の場合はプルサーマル使用済み燃料がまだどこにも持ち出すことができないから、今のままでは未来永劫福井県内に留め置かねばならないと、こういうことになるわけであるけれども、そういうプルサーマル発電を拡大すれば拡大するほど税収が上がっていくと。要するに単価というか、燃料代が高いから上がっていくというやり方になってるわけである。であるから、結果的には福井県の気持ちとしてはプルサーマル発電を拡大して、税収に貢献してほしいと。今は例えば高浜原子力発電所だけだけれども、大飯原発でもやってくれないかと。そういうふうに逆に危険な発電を拡大するということに、税収が上がるということによって福井県政を歪めるということにならないか。
◯税務課長 制度設計に当たっては、核燃料の価格差があるというところを、殊さらそういうことで捉えているわけではなくて、今回の見直しに当たっても、価額割というのはどうしても稼働状況に応じて変動するというところもあって、むしろそれ以外のところの引上げということで、安定的な税収を確保するということで見直しをするところもある。MOX燃料の価格が高いとか、そういったことを考慮しているわけではない。
◯佐藤委員 この件はもう終わるけれども、搬出促進割を上げても結果的には搬出に対する強力なプレッシャーにあまりなってないわけである、であるから、そういう点では甚だ税の効果も疑問だということは指摘しておきたいと思う。
福井県立大学の学長、理事長職のあり方
それからもう一点、よろしいか。第60号議案、第61号議案は県立大学についてなのだが、出資と定款の一部変更、これ異議はないが、ちょっとマスコミの報道なのだけれども、理事長から離職というか、そういう願いが出されているという報道があった。それで、福井県立大学は理事長と学長という、経営と学問というような体制になっていると思うのだが、これはいろんなこの間、理事長職の在り方というのは検討されたのだろうか。
◯副部長(大学私学) 県立大学には定款があって、その中で理事長の役割、それから学長の役割を定めている。それに基づいて、日々の大学の運営であるとか、教育というものを進めているという状況である。
◯佐藤委員 そういうことはもちろん分かってるわけであるが、県の幹部職員であった方が理事長になられるというパターンが多いわけである。今回もそういうことで、途中で辞められるというような報道がある。そうなるかどうか分からないが。改めて理事長職の在り方というのを、せっかく県議会にこういう議案を出されるのであれば、在り方について再検討されたのかということをお尋ねする。
◯副部長(大学私学) 今回、委員の指摘の事例を捉まえて、在り方について検討したということはない。
◯佐藤委員 これは要望であるけれども、変な言い方であるけれども、理事長職と学長職と2つがどうしても必要なのかどうかというのは、いろいろ議論があってもいいかなという、個人的にはそう思う。もちろんそれぞれの役割、さっき言った経営と学問という役割を分担してされてるということはもちろん理解してはいるけれども、そういうことも含めて、今後検討されてはいかがかなというように思う。これは要望である。
公衆衛生分野の職員増員を
◯佐藤委員 部長報告2ページのところの一番下に、全国最少水準の職員数を基本として、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策などに人員を配置してきたとある。以前も厚生常任委員会のときに、保健師の数とかあるいは県の衛生環境研究センターの職員数とか、そういうのはどうしてもいわゆる行政改革の流れの中で、減らすとかそういう流れになってきたことは事実なので、やっぱりこういう状況を受けて、公衆衛生分野の職員の増員も必要ではないかということをお願いしたことがあるのだが、これはその後県庁内ではそういう専門職を増やすとか、増強するという話にはなっているのか。
◯人事課長 専門職という関係でいくと、今回児童相談所のほうになるが、こちらの虐待防止対応などで体制強化として、8名の増員を行っているところである。保健師についても、しっかりと欠員の補充であったりとか、そういったところで採用のほうをしっかり採っていきたいというふうに考えている。
◯佐藤委員 それは引き続き、衛生環境研究センターなんかの職員も含めてしっかりと目配りをしていただきたいと思う。
それと、健康福祉部だけではなくて、県庁全体がこれだけ1年以上も新型コロナの問題で対応、対応と、しかも土日なしに記者会見とかいろいろあるということは、部長とか副部長が記者会見すれば、2人だけ出勤すればいいというわけでもないだろうから、当然職員の人も何人も出勤されて対応されているだろうと思うが、これだけ1年半近くにわたって続いてるとかなり疲弊してきてるのではないかなというように思うのである。そういう点ではいわゆるAIの活用とか、実績があって業務を減らしたということがあったけれども、そうはいっても人手がかかるいろんな業務がある。以前だったら例えばマスクを配ろうというときに、お店に県の職員が交代で詰めて、マスク購入をサポートすると、そういうお仕事を県の職員がされたりしているし、今ならワクチン接種で現場のお手伝いをする。いろいろあると思うのだが、そういうのをもう少し、県の職員だけではなくて、ある意味ではボランティアでOBの方も含めて、単純作業の部分を少し動員というかお願いをして、現職の県の職員の1年半以上に続いてる疲弊感を少しフォローしていくということなんかは、考えられたらいかがだろうか。
◯総務部長 職員の業務の負担感というところであるけども、指摘いただいたとおり、コロナで1年以上各職員これまでにないような対応を求められているというところがあって、個々の職員含めて超勤の状況などについては、私ども人事担当部局としても、常日頃からよく見るようにはさせていただいているところである。その上で、ほかのところでやっていただけるとか、お手伝いできるところあるかとか、そういう形に庁内での仕事の分担というところもさせていただいているのがまず一つ。
その上で、委員指摘いただいた外の力の活用という点についても、新たに事業を行うときに、いわゆる外に予算的なものも含めてお願いできないかというところなどについては、一つ一つやらせていただいていて、そういった業務量が過剰にならないように、いろんなことを活用しながらやらせていただきたいというふうに思っている。
◯佐藤委員 いつまで続くか分からないけども、いずれにしても相当続いて、かなり疲れもたまっている状況であろうと思うので、その辺外部の力、OBの力をボランティア等で活用できるところはぜひ検討していただきたいと思う。
県立大学の拡大路線について
それから、県立大学でちょっと質問するが、確かに知事は正確じゃないかもしれないけど、一般質問の答弁で、人文系学部の設置も検討するというようなことをおっしゃったのである。これは具体的にどういうことなのか。
◯副部長(大学私学) 知事がお答えしたのは、現在県立大学の第3期中期計画の中に、次世代の地域リーダーを養成する学部の創設というのを掲げていて、それがまさしく文系の受皿になり得るということで、それについては現在学内でほかの大学と競合しないかとか、いろんな観点からその中身を検討しているということである。
◯佐藤委員 今、大学院なんかも新たに拡充する計画があるのか。
◯副部長(大学私学) 大学院については、その計画の中で、大学院看護学部の博士後期課程、今ちょうど修士まで作ったので、その後期課程をどうするかというのが検討課題として上がっている。
◯佐藤委員 要するに拡張路線である、この創造農学科も先端増養殖学科も拡張路線といえば拡張路線であるけども、しかし学部となると、学科とは違って文科省の大学設置・学校法人審議会の審査を通らなければいけないということで、ハードルが非常に高いというようにお聞きしているし、学部についても県立大学の中ではいろいろ人材、要するに博士課程作れば当然それの授業を受け持つ教員も必要になるわけであるから、非常に今のスタッフの状況で、大学院博士課程どうなのかという意見も出てるというようにお聞きしているのである。
であるから、思いはいろいろ、こういうのを作って福井県の将来を見据えてこうだとかいう思いはあるのだろうが、現場のスタッフとかが追い付いていかないと、何もならないということにもなるわけである。その辺はどういうふうにお考えなのか。
◯副部長(大学私学) 委員指摘のように、そこは非常に重要なポイントであって、やはり学内でしっかりやっていこうという意思決定をしていただくことが重要だと思う。やっぱり、世の中地域のニーズであるとか、大学としてそれをしっかりやっていける体制をどうしていくか、これはコストなんかも含めて、総合的にやっぱり検討していかなきゃいけないということであるので、ただそういったところについては学内で検討しているという状況である。
◯佐藤委員 学内的なそういう意見なんかに十分配慮いただきたいと思う。
県立高校と私立高校の定数に関して
最後にもう一点確認したいのだが、さっき教育委員会の議論があったのだけれども、これも教育長の本会議での答弁だったと思うが、県立学校のいわゆる志願状況は危機的だと認識しているということで、いろんな高校でも魅力化というのを進めるということで報告があった。この問題を考えるときに、マスコミさんも報道しているけども、私学はどんどん魅力的になってきてる、それは中身が魅力的なのもあるし、校舎、ハード面でも魅力的になってきているという両面があって、ちょっと古い学校よりも新しい私学に行きたいと、立派な校舎に行きたいとか、きれいだわとか、女性なんか特にそういうことにもなってくると思うのである。
そうした場合に、県も私学にも補助金出すし、県はもちろん県の施策でやってもらうということで、これは引き続き進めてほしいのだが、もう一つ問題は、定員問題があると思うのである。いわゆる公私、公立と私立の配分である。以前もここの委員会のときにちょっと言わせてもらったことがあると思うのだが、そこをちょっと一定考えていかないと、入学する生徒の総数はこれからちょっと減り気味になっていくと。そういうときに私学の定員だけはこれまでのままで、あるいは実際には定員よりもさらに多く入学者を迎え入れるという状況が続くと。県立のほうはどんどん定員を減らしたり、統廃合していくと。県立のほうは真面目に定員を守って入学者を取っていくということでは、なかなか実際にはアンバランスというのが生まれてくる面があると思うのである。であるから、県立も私学も両方とも共存共栄でもちろんやるということで、協議会を時々開いてはいると思うのだが、その辺を県としてはもうちょっとしっかりと、定員問題も含めて見ていってもらわないと、この問題の根本解決には至らないんじゃないかなと思うのだが、その辺はどうなのだろうか。
◯副部長(大学私学) 県立と私立の高校の問題であるけれども、私立学校の授業料の無償化というようなことも本格的に始めさせていただいた中で、やっぱり私学のほうにシフトしている、私学を第一希望に志望とする生徒さんが増えてきているという状況が実態である。
そうした中で、私学であるけれども、定員を全体としてみれば超過をしているという状況であるが、一つは私学の努力として、県内の高校生だけではやっぱり定員を確保できないということもあって、スポーツや文化等々に秀でた生徒を全国から一生懸命集めてきて、生徒を確保しているという状況もある。やっぱり県立と私立、それぞれに魅力を高めて切磋琢磨をしていく、そういった中で中学生にとって選択肢を少しでも広げていただくというようなことを、我々としてもしっかり私学サイドとして応援をしていきたいというふうに考えている。
◯佐藤委員 今答弁にあったように、切磋琢磨というのは知事もおっしゃる言葉だと思うのだが、結局私学が魅力的になっていけば、県立もそれに負けじと切磋琢磨して県立もよくなっていくという発想はあると思うのである。そういう面はあると思う。だけど、今言ったようにそもそも校舎の条件が、全くリニューアルして立派なのとぼろい校舎では、なかなか対等な競争にならない。入学定員にしても今言った問題があって、これもなかなか対等な競争にならない。今、スポーツと言われたけれども、要するに県立のほうは働き方改革ということで、教員の労働時間をきちっと管理するというようなことも含めてきちっとやっていくと。私学のほうは、それよりもまだ少し、言葉悪いけど緩い面があるというようなことがあれば、どうしてもお互いに切磋琢磨してって、言葉はいいのだけど、そのとおりになかなかならない面があるわけである。
であるから、私が言ってるのは両方とも共存共栄していかなきゃいけないわけだから、そういうスタンスに立てば、少しやっぱり定数問題とか含めて、県としても立ち入って議論をしていかないと、これは根本的な解決には至らないというか、そういう条件がどんどんどんどん違ったままで県立学校は私学と競争させられるというのでは、ある意味ではちょっと酷だなという面も出てくるのではないかというように思って質問しているので、最後にするからもう一度答弁をお願いする。
◯副部長(大学私学) 長期的には子どもたちの人口が減ってくる。そういった中で、常に私どももやってるけれども、引き続き教育委員会と定員の問題も含めて情報を共有しながら、あるいは協議しながらやっていきたいと思っている。