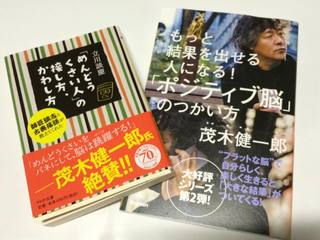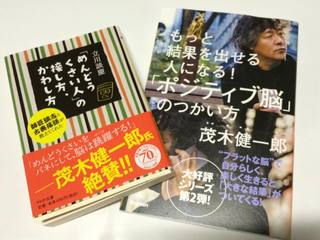
上田市合併10周年記念「脳と落語とふるさとと」立川談慶師匠・茂木健一郎のトークショーが、丸子文化会館であることを師匠のフェイスブックで知り、信州沖縄塾の講演会の続きで楽しんでまいりました。何てったて無料です。その割にホールの入りはいまいちでしたが、そこは師匠、「お盆ですから、客席いっぱいに亡くなった方がいらっしゃいます」なんて。
私が県議の時に地元で岡田落語会を開催して、2回来ていただきました。最新刊「めんどくさい人との接し方、かわしかた」を購入してサインをお願いしたところ、私の名前を憶えていただいていて書いていただき恐縮しました。
翌日の師匠のフェイスブックと私のコメントです。

こんな時間に目覚めてしまった。
いま上田。
昨日は茂木健一郎先生とのトークショーを故郷で企画してもらった。俺が「禁酒番屋」で一席やらせてもらった後、茂木先生のトーク。これはまさに「脳漫談」という先生の独壇場とも言うべきジャンルだなあと、熊本でのイベント以来思っていたがまさにその思いを強くした。先生の話から、
「人間何が幸いするかわからない」
これは真理なんだと確信。
終わって、二人トークショー。先生にうちのお袋をいじってもらって盛り上がる。
この会場であるセレスホールは、前座時代、二つ目昇進披露、真打ち昇進披露と三回もうちの師匠には来てもらっている場所だ。
「亡くなった人の魂は、生前訪れた場所に舞い戻る」そうだ。昨日の楽屋にもなんとなく師匠の匂いがしていた。
「あんな奴にもこんなにお客がいるとはな」
と、真打ち昇進の時、師匠は満員の客席を前にしてそう言ったっけ。
「よく、こんなに集めたな」
「いえいえ、師匠目当てに来る客ですよ」
「そうか?」
笑う師匠。
以来、俺はうちの子供に「虎の威を借る狐」の具体例としてこの話をしている。
サイン会の後の地酒の会で、茂木先生を囲んでうまい酒を飲みながら、地元の同級生らと語らう。
ふと気付いた。
「そっか、お盆なんだ」
今日は俺が生まれ育った丸子町という小さな町が上田と合併してからの10周年の記念イベントの一環として開催されたのだが、この世から消えた「丸子町」が、魂となって戻ってきた日だったのだ。
空いた席にも、師匠、うちの親父などなどを始め、小さい頃から俺を可愛がってくれたいまは亡き祖父母、そして近所のみなさんの顔がちらほら見えたような気がした。やはりお盆なんだ。ここは血のつながる故郷なんだ。黄泉の国からお暇を頂戴して、生きている人間たちを元気づけようと帰ってきたのだ。
今日は、さいたまから一人でやってくる次男坊を上田で迎えて、親父と兄貴のお墓参り。この残暑厳しい折に、亡き人々の魂を慰める習慣を編み出した先人たちの知性に手を合わせたくなる。帰省ラッシュに接する度にご先祖様という縦の系譜の有り難みを悟る。
いつぞや親戚のおじさんがしみじみ言っていた。
「うちの一族は、みんな不器用なお人好しばかりだ」と。血は争えない。ほんとそう思う。
みなさん、素敵なお盆休みをお過ごしください。

同じく茂木健一郎さんのフェイスブックと私のコメントです。

無茶振りの効用
昨日、立川談慶師匠 @dankeitatekawa とお話していて、立川談志師匠の「無茶振り」の話になった。いろいろとほんとうに無茶なリクエストに応えているうちに、次第に、やりぬく力、推理する力がついていったという。
談志師匠は、生前、「俺の悪口を言えば、30分は持つだろう」と言われていたそうで、弟子たちが将来、落語家として生活できる、そのネタを用意していた、ということかもしれない。いずれにせよ、無茶振りが談慶師匠を育てた。
有森裕子さんには、小出義雄監督の「無茶振り」の話をうかがったことがある。30キロ走った後で、いきなり、「今日は1万メートルのタイムトライアルをやるぞ」などと宣言されたのだという。大抵の選手は、「それは無茶だ」と抵抗する。
しかし、有森さんは、素直に走った。考えてみれば、マラソンのオリンピックの本番は、一回だけ。その日に体調がどうなっているかわからないし、天候もわからない。30キロ走った後で、1万メートルのタイムトライアルを走る、くらいの負荷があっても、当然と言える。
無茶振りが、精神や体力を鍛えて、本番に強い精神を育てることは間違いない。ただ、立川談志師匠や、小出義雄監督のように経験や見識があるから成立したのかもしれないわけで、ヘタにやれば、今ではパワハラやブラックなんとかになりかねない。
無茶振りの効用はあるとして、今有効なのは自分で自分に無茶振りすることだろう。少し無理、とても無理、と思われることを自分に課して、やってみる。キツかったら、少し緩める。そうやって負荷を調整して、自分を伸ばす。
私自身、自分で自分に課す無茶振りが好きである。無茶振りしか、人生の伸びしろを広げる方法はないようにも思う。だから、立川談慶師匠や有森裕子さんの話をうかがうと、へえ、と面白くて、人間の可能性は計り知れないな、と考える。