
(新潮社刊。)
すごい本が出た。ノンフィクションライター最相葉月(さいしょうはづき)による『セラピスト』がそれである。
最相葉月は2006年『絶対音感』というノンフィクションによって世に出た。私も読んだが、途中からつまらなくなり、大部さに投げ出してしまった。
このたびの『セラピスト』はおそらく「カウンセリング(心理療法)って効くのかよ」という最相の素朴な疑問から取材に入ったのだと思われる。彼女はまず臨床心理士の故木村晴子から「ジャーナリストが心理療法を知りたいのなら、まず自分自身を知らなくてはなりません」と言われ、大学院の心理学科に入学する。
河合隼雄の箱庭療法や中井久夫の絵画療法を糸口に取材が続くのだが、それらへの理解は舌を巻くほどに正確で深い。私は1975年から2年間、中井のシュライバー(面接の筆記者)に付いたが、最相の記述はまるでそれらを当時から見ていたかのごとくに生き生きとしていて、何も加えられず何も省かれていない。
そして自分自身がクライエント(依頼者、患者)となって、心理療法のキモを理解していく。そして、セラピストとクライエントの間に行われるのは、セラピストが自らの全人格を賭した作業であり、「効くのかよ」という問いを超えた営みであることを知る。本書には書かれていないが、中井の言う(最良の治療は)「医者を処方する」ことだという理解に最相は達したようだ。
最相は「治るということは、必ずしもいいことではないのですよ」という河合の言葉に納得してしまう。だから本書には、カウンセリング(心理療法)が効くとも効かないとも結論は出されていない。だが、取材に取り掛かったときの筆者と、本書を上梓したときの筆者が明らかに変化していることが分かる。
最後に最相自身がある心の病であったことが明らかにされる。少なくとも彼女は本書を書くことによって生きやすくなったことは確かである。取材対象への理解といい大量の文献の咀嚼力といい、最相が精神科医となったとしたら、一流のそれになれるだろう。
彼女の力量が随所に感じ取れる。この本はどんなプロのセラピストが書いた本より公平中立で分かりやすいから、一読をお薦めする。
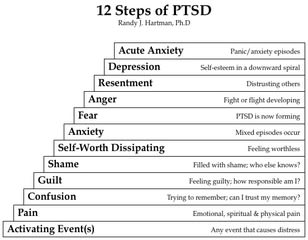













 (文芸社刊。)
(文芸社刊。)




 (新潮社刊。)
(新潮社刊。)