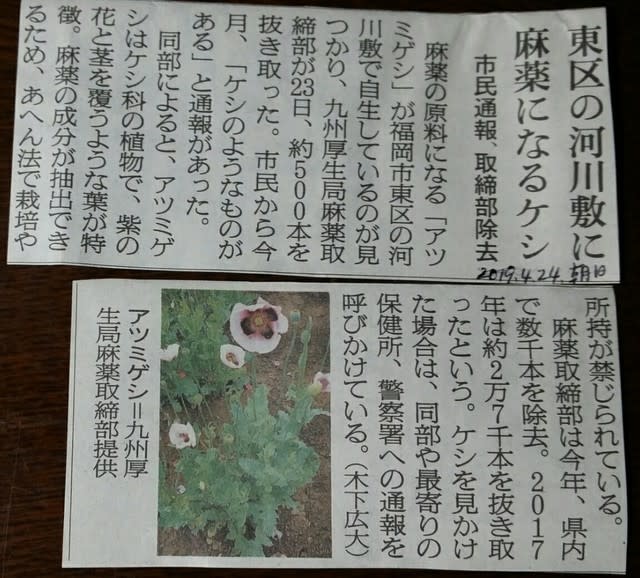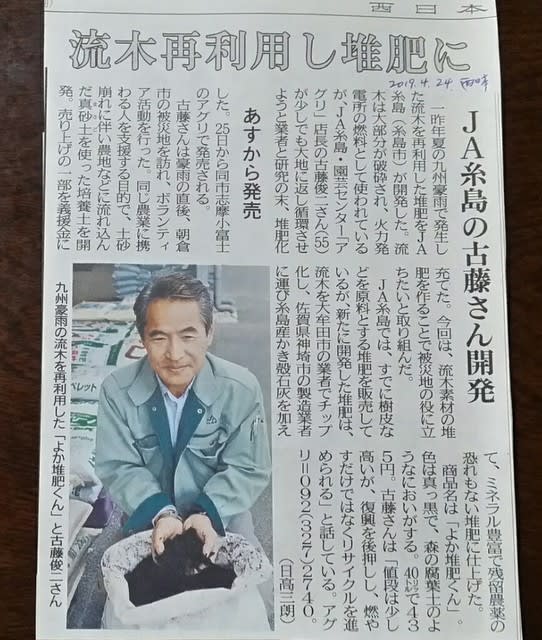大牟田夏祭り《大蛇山》の準備が始まっています。
新栄町の龍山會より大蛇山祭りの参加者募集が発せられています。
ふるってご参加ください‼
【参加者募集のお知らせ】
新栄町龍山會では令和元年(2019年)の大蛇山参加者を募集しています。
参加条件は中学生以上ってだけ。住んでいる地域も一切関係ありません。
詳しくはこのページで確認してください。
*この投稿をシェアして頂けるとありがたいです♪
https://ryuzankai.com/info001/

新栄町の龍山會より大蛇山祭りの参加者募集が発せられています。
ふるってご参加ください‼
【参加者募集のお知らせ】
新栄町龍山會では令和元年(2019年)の大蛇山参加者を募集しています。
参加条件は中学生以上ってだけ。住んでいる地域も一切関係ありません。
詳しくはこのページで確認してください。
*この投稿をシェアして頂けるとありがたいです♪
https://ryuzankai.com/info001/