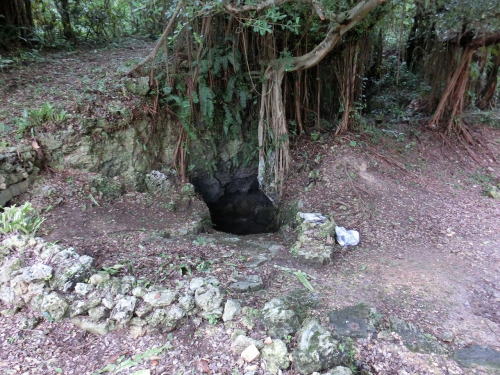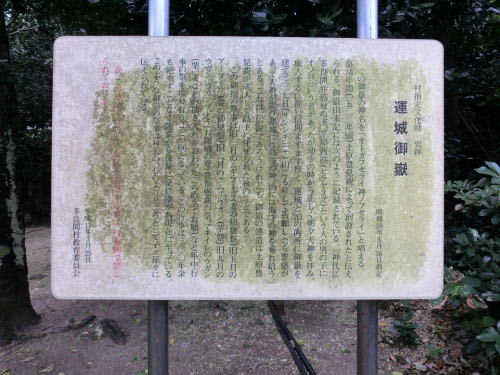右上から ( 北原白秋 ・ 木下杢太郎 ・ 吉井勇 ・ 左上から与謝野 寛 ( 鉄幹 ) ・ 平野万里 )

天草にある下田温泉の小高い丘の上に 「 五足の靴 」 の碑がある。
「 五足の靴 」 とは、明治の終りに九州を旅した5人の文学青年たちが
東京の新聞社に書き送った紀行文の題名である。
明治40年 ( 1907 ) の夏、新詩社主宰の与謝野 寛 ( 鉄幹 、 35歳 ) と、
その同人である北原白秋 ( 早大文科23歳 ) 、吉井勇 ( 早大文科23歳 ) 、
木下杢太郎 ( 太田正雄、東大医科23歳 ) 、平野万里 ( 東大工科23歳 ) の 「 5人の詩人 」 が、
東京から九州へと旅立ち、途中で白秋のふるさとである福岡の柳川に立ち寄り、
長崎から暴風の荒海を、船で天草の富岡へ渡ります。
上陸後、天草西海岸沿いを旅しながら、紀行文を更に書き綴って行くのである。
5人は大江天主堂で、あこがれのガルニエ神父 ( フランス ) に会い、
キリシタンのゆかりの秘蔵の 「 クルス 」 を見せてもらう。
牛深で一泊して 「 五足の靴 」 旅の最大の目的を果たし終えるのである。