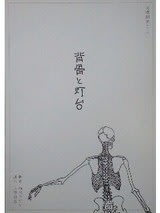
小説家の見た妄想が綴られていく、とでも言ったほうがわかりやすいだろう。頭の中で現実と空想がごっちゃになってしまい、どこまでが本当のことで、どこからが自分の創作だったのか、すらわからなくなっていき、繰り返される出来事は、いつも微妙にずれていき、煮詰まってしまい、ぐちゃぐちゃになり、またそれを反故にして、一から書き直していくうちに、何が何だかわからなくなっていく。
夢の中の出来事すら、それに混ざっていき、いつもの人たちが、まるで現実とは違う役割を演じて自分の前にいたりする。それが夢の中なら、とてもすっきり納得できたりする。誰にでもそんな経験があるはずだ。
この芝居は単なる夢オチにはならない。これは作家の頭の中に生じた現実であり、約2時間に凝縮された彼女の世界自体の物語なのだ。
とあるバーにやってきて、そこでひとりパソコンと向き合う。新作小説を書いている。店に中には彼女とマスターしかいない。彼女は気付くと居眠りしていたみたいだ。しかし、目を醒ましたはずなのに、そのときには、どこが現実だかわからない世界に迷い込んでいる。
作品の中の人物や夢の中の人物が役割を変えながらここにやってくる。マスターと2人で話しながら、小説を書いていたら、その小説が視覚化されて、舞台上に登場してきたりもする。
何でもありの芝居である。だけれども夢の論理としての一貫性があるから、芝居はぐたぐたのいいかげんにはならない。ある種の緊張感を持続させたままラストまで見せてくれる。演出の上原日呂さんが当日パンフで書いているようにある種の「いい加減」さが誠実に表現されている。とてもうまい匙加減になっている。
夢の中の出来事すら、それに混ざっていき、いつもの人たちが、まるで現実とは違う役割を演じて自分の前にいたりする。それが夢の中なら、とてもすっきり納得できたりする。誰にでもそんな経験があるはずだ。
この芝居は単なる夢オチにはならない。これは作家の頭の中に生じた現実であり、約2時間に凝縮された彼女の世界自体の物語なのだ。
とあるバーにやってきて、そこでひとりパソコンと向き合う。新作小説を書いている。店に中には彼女とマスターしかいない。彼女は気付くと居眠りしていたみたいだ。しかし、目を醒ましたはずなのに、そのときには、どこが現実だかわからない世界に迷い込んでいる。
作品の中の人物や夢の中の人物が役割を変えながらここにやってくる。マスターと2人で話しながら、小説を書いていたら、その小説が視覚化されて、舞台上に登場してきたりもする。
何でもありの芝居である。だけれども夢の論理としての一貫性があるから、芝居はぐたぐたのいいかげんにはならない。ある種の緊張感を持続させたままラストまで見せてくれる。演出の上原日呂さんが当日パンフで書いているようにある種の「いい加減」さが誠実に表現されている。とてもうまい匙加減になっている。

























