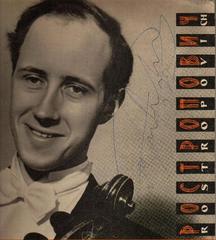で、どうやら機関紙もとい気管支まで風邪が入ったらしく今日は殆ど外出しなかったのだが、そのおかげで音楽を(多少無理やりだが)聴けている。ショスタコばかり聴いていて、マルケORTFのショス1を見ていたらそういえば譜面があったと持ち出して楽器を手にとってみる。体のことを言ってもしょうがないのだがとにかく病みついた体に檄を入れるために楽器は有効なこともある。
だが。
なんじゃこりゃ。
人間のさらう譜面じゃない。
最後のページを見て思った。
・・・どこが最後なんだ。
ショスタコはメカである。メカ好きにはたまらないだろうが、五線の上で半音を駆使されても困るし、断片的なフレーズが連なるだけではとても、よくわからないっす。だめだこりゃ。
マラ9の冒頭を弾いておしまい。体調悪くなった。
だが。
なんじゃこりゃ。
人間のさらう譜面じゃない。
最後のページを見て思った。
・・・どこが最後なんだ。
ショスタコはメカである。メカ好きにはたまらないだろうが、五線の上で半音を駆使されても困るし、断片的なフレーズが連なるだけではとても、よくわからないっす。だめだこりゃ。
マラ9の冒頭を弾いておしまい。体調悪くなった。