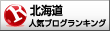「原発の地下建設推進”地下式原子力発電所政策推進議員連盟”発足へ」だそうです。
http://surouninja.seesaa.net/article/203488846.html
宇宙人、鳩山由紀夫もメンバーだという。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20100602/229378/
鳩山さん いつから農業始めます? 土地「高く」貸しますよ。
http://blogs.yahoo.co.jp/sulmari_21/31451912.html
詳しくはこちら↓。
地下立地 (原子力百科事典 財団法人高度情報科学技術研究機構)
http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_Key=02-02-01-06
2.2 地下立地 地下立地とは、原子力発電所の主要施設を硬い岩盤中に地下空洞を掘削し、収納する方式をいう。原子炉を収納する地下空洞の形状により立型方式(円筒空洞あるいは開削立坑)と横型方式(トンネル型空洞)に分類される。さらに、地下空洞内に原子炉建屋を含む主要な原子炉施設の一部を収納する部分地下式、全部を収納する全地下式に分類される。これらの区分を概念的に図1に示す。なお、立型方式の内、開削立坑式は岩盤の天井ドームがなく、地上より立坑を掘削し原子炉建屋を立坑中に完全に格納するタイプのものを言い、原子炉建屋の一部が地上に現れるタイプの在来立地方式とは区別する。 地下立地は原子炉建屋等の重要施設の基礎を岩盤とすることは在来立地と共通であるが、重要な施設が岩盤内に建設されることから、それらの耐震安定性、安全評価、建設・保守など種々の点で大きく異なる。
「地下原発」の検討再開(高市さなえコラム 自由民主党参議院議員)
前略 当時の資源エネルギー庁長官の私的諮問機関だった「地下立地方式原子力発電所検討委員会」が長官に報告書を提出し、その報告書の結論が「山腹に空洞を掘って施設をすっぽり埋め込む地下立地方式の原子力発電所は、安全、採算面で問題なし」というものだった旨を報じる記事でした。後略
「山腹に空洞を掘って施設をすっぽり埋め込む地下立地方式の原子力発電所」と書かれています。
原子力発電では、2/3のエネルギーを、復水器から海水へ捨てています。
山中に巨大なクーリングタワ(冷却塔)を建てようというのでしょうか?
地下式原子力発電所政策推進議員連盟 (アラブ・MENA・イスラム経済「観測」)
http://yokita.blog58.fc2.com/blog-entry-131.html
やはり、海の近くのようです。事故が起きたら手の付けようがなくなると思いますが…
地下立地式原子力発電所について、以下にかなり詳細に書かれています。
地下構造体の施工方法及び該方法によって得られる地下構造体並びに地下立地式原子力発電所
http://www.ekouhou.net/%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%A7%8B%E9%80%A0%E4%BD%93%E3%81%AE%E6%96%BD%E5%B7%A5%E6%96%B9%E6%B3%95%E5%8F%8A%E3%81%B3%E8%A9%B2%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%BE%97%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%A7%8B%E9%80%A0%E4%BD%93%E4%B8%A6%E3%81%B3%E3%81%AB%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E7%AB%8B%E5%9C%B0%E5%BC%8F%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80/disp-A,2009-24368.html
利点
(1)地形や地表の土地利用形態に左右されない
(2)気象条件に左右されない
(3)耐震性に優れる
(4)事故時の放射線遮蔽効果、FP(核分裂生成物)格納性が高い
(5)内圧、外的飛来物などに対する強度が高い
(6)景観保護
(7)施設の廃棄処分の面で利点を有する可能性がある
欠点
(1)地下構造物はその信頼性評価や構造物の監視可能性の面で問題がある
(2)立地可能な岩盤条件が限定される
(3)付加的地下水対策の必要性
(4)施設の拡充や計画変更、工法等に対する制約がある
(5)工費と工期の増大につながる
原子力発電所で炉心溶融の過酷事故が発生した場合、放射性核種の周辺への拡散を防止させる封じ込め機能(コンテインメント)を確実なものとすることが重要であることは1986年の露国チェルノブイリと1979年の米国スリーマイル島の2例の事故被害の差で証明されている。1951年以来、総計で1500回余の地下核実験が米国、ロシア、フランス、イギリス、中国、インド、パキスタン、北朝鮮で実施されているが、一部を除いて地下核実験場周辺の放射能被害は重大な問題とされてはいない。
地下立地式原子力発電所であれば、過酷事故発生時の放射性核種放出源と地表との間の拡散経路が限定されることから、放射性核種の拡散を防止あるいは遅延させ得る封じ込め手段を講ずることがより容易となる。
しかし現状では、前記の欠点や、地下に大断面の所要空間を施工するための工法や耐震構造設計、過酷事故発生を想定した放射性核種拡散低減あるいは拡散遅延構造についての具体的な見通しが明確ではないなどの課題が未解決であることから、世界的にみても地下立地式の原子力発電所の建設は進んでいない現状である。
これらの課題を解決できれば、前記のように多くの利点を有する地下立地式原子力発電所の施工が可能となる。
革新的原子炉の研究開発(日本原子力研究所 小川 益 郎 2002.1.10)
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/kakusinro/siryo/kakusin01/siryo4_2.htm
2.4 分散型小型炉(図5)
(1)開発の意義
分散型小型炉は、舶用炉の技術開発を通して蓄積された一体型軽水炉の技術に基づく小型炉で、熱供給専用、または小規模発電用に使用する小型炉として、地域やビルの熱利用と電力供給を行い、需要地に近接して立地することを目指している。
(2)現 状
これまでに、千人規模のオフィスビルへの熱供給を目的とし、ビルの地下室に設置する熱出力1MWの超小型炉、および地域熱供給用として人口10万人規模の地域熱供給用に、都市の大深度地下(深度約50m)に立地する熱出力100MWの原子炉概念検討を行っている。また、熱供給システム概念、地下立地上の安全性、建設コスト等について検討を行い、技術的及び経済的な成立性の見通しを得ている。
(3)展望と課題
今後は、熱利用システムとして空調・給湯の他に、浄水、海水脱塩システム等の検討を行う計画である。なお、これらの分散型小型炉は、離島や地域を対象とした小規模発電/熱供給システムとしても期待できる。
なお、オフィスビル等で利用する分散型小型炉が、既に実用化されている化石燃料を使用するコジェネシステムの代替システムとして受容されるためには、システムとして高い安全性・利便性、放射性廃棄物問題等の社会的受容性に加え、経済性のさらなる向上を図る必要がある。
頁の最後に図があります。
都内のビルの地下に沢山作ればよいだろうと思います。
海のものとも山のものともつかないようです。
地下式原子力発電所はこの事だろうか?
「地下立地方式の実績は日本ではまだないが、欧米では研究炉、商用原子力発電所など現在までに閉鎖されたものも含めると6つの例がある。中でもフランスのSENAショーズA発電所(PWR原型炉)は電気出力30万kWの部分地下式(原子炉建屋は地下、タービン建屋は地上)の商業炉として有名であったが、現在は停止され遮蔽隔離中である」との事。