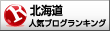国民の3%に満たない約260万人の農家が日本の食料の大半を支えている。かつて自給自足が当たり前だった日本は,食料に関しては消費者ばかりの国になってしまった。
日本と諸外国の食料自給率の推移(社会実情データ図録)
農地争奪と食料安全保障(外務省)
■加速するグローバルな農地争奪 ■増え続ける人口と食料問題 Etc.
中国、食料確保急ぐ 豪・アフリカに相次ぎ大型農地(日経)
伝統的な農業国である中国が、オーストラリアやアフリカに大型の農地を確保するなど、官民を挙げて食料安全保障の強化に向けて対応を急いでいる。都市化に伴って農地面積が急速に縮小し、いずれ世界人口の増加で食料需給が逼迫すれば対応できない可能性が出てきたためだ。
じじぃの「食糧危機・世界の農地を買い漁る中国・韓国!資源戦争(老兵は黙って去りゆくのみ)
穀物価格再上昇で新たな食糧危機が懸念される今、アフリカや東欧の農地を外国企業が囲い込む「ランドラッシュ」と呼ばれる争奪戦が激化している。多くは国の後押しを受けた進出である。韓国は国内需要の4分の1を賄う食糧基地を国外に建設しようとロシア等に大農場を建設している。リビアは原油の供給と引き替えにウクライナに大規模な農地を確保した。一昨年の食糧危機で穀物市場のもろさを知った輸入国は、自ら国外に農地を確保する危機管理を始めた。今後の人口爆発と、新たに開拓できる農地の限界を見越した中国やインドも農地確保に乗り出している。進出国と現地住民の間に摩擦も起き始め、マダガスカルでは、全農地の半分を韓国企業に提供しようとした政府が、暴動で転覆する事態となった。「新植民地主義」との批判を受けながらも、進展するランドラッシュ。このままでは締め出されると焦る最大の輸入国・日本は、将来の食をどう確保するのか。慢性的な食糧不足の時代に備える国家の戦略に迫る。
自民:公約に農村所得倍増 耕作放棄地フル活用(毎日)によると、
農地を集約、大規模化して経営効率を高めるとともに、農家が生産だけでなく加工や販売を手掛ける「6次産業化」を進め、農業関連の収入を倍増する−−。稲作の平均作付面積が1ヘクタール程度の現状では、農業所得は平均110万円に過ぎないが、10ヘクタール以上の農家の所得は500万円を超える。自民党は耕地面積について「平均10ヘクタールを視野」と掲げ、農家の経営基盤を強化する。 そうだ。
北海道ではほとんどが10ヘクタール以上だ。
■6次産業化
「6次産業化」は一部有効だとは思うが、我々消費者は加工品ばかり食べるわけではない。
米は米として買いたいし、野菜もそうだ。すでに加工食品は充分流通している。都市近郊の極一部の農家は、農家民宿や農家レストラン等、グリーツーリズムなど可能かもしれないが、どれだけ需要があるだろうか?少し考えてみればわかる。肉や魚もそうだ。
六次産業化の落し穴(コミュニティオーガナイザー若見まさあきの 「ぶなの木漏れ日の下で」)
■耕作放棄地をフル活用するというが、北海道の耕作放棄地は僅か1~2%だ。
耕作放棄地の現状(マーケティング&マニュアル・ゼミ)規模を大きくして効率化できる放棄地がどのくらいあるのか?「放棄」されたからには、それだけの理由があるはずだ。
■ブランド化 ブランド化を否定するわけではありません。持続可能な価格で買わせていただければと思います。
TPP議論の中…輸出に活路を見いだす農家(日テレ)
「ブランド化」よく言われる事だ。TVは全国捜し歩いて見つけてくる。
経済が急成長する台湾の富裕層に目をつけ、04年からコメの輸出を始めた。「玉木米」としてブランド化して売り出すことで、日本で売るよりも2倍から3倍高い価格で売っているという。 それはそれで頑張ってもらいたい。
しかし、富裕層ではない私はブランド米などとても食べられないし、どれだけの輸出できるだろうか?
北海道にも「ほしのゆめ」「ななつぼし」「ゆめぴりか」など美味しい米はたくさんあるが、「ゆめぴりか」は、知り合いから戴いた1度しか食べていない。
最近は果物もブランド化が進み高価になり毎日バナナだ。 白老牛も食べた事がない。 国産鶏ムネ肉(2Kg真空パック680円)を食べている。美味くてヘルシーだ。
今日は、卵白でふっくら!鶏むね親子丼(ためしてがってん)を試してみよう。 これらも円安でもうすぐ値上りするだろう。
日本の農業がこのままで良いなどと言っているわけではない。このままだとあと10年もすれば、担い手不足で耕作放棄地が激増するだろう。
農政=NO政 もうたくさんだ!