ドストエフスキーの小説が長いものとなっている理由として,僕は登場人物の数が多いこと,そしてそうした数多くの登場人物が交わす会話の分量が多いことを上げました。これはいわば小説の内部に原因を求めたといえます。『21世紀 ドストエフスキーがやってくる』の中で,貝澤哉が,僕が知らなかった別の観点からこの事情を説明しています。
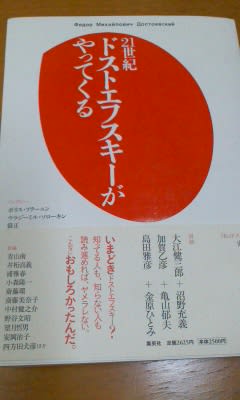
ドストエフスキーが小説を書いていた時代,ロシアの識字率というのは,多く見積もっても20%を超えていませんでした。つまり小説を読むことができるという人は,それだけでインテリとみなすことができたのです。そしてロシアは広大な国家ですから,そうしたインテリというのも各地に分散していました。このために,町で書店を営むということはほぼ不可能でした。よってこの時代の小説は,単行本として読まれるということがあまりなかったのです。
各地のインテリには書物に対する渇望はありました。それに応えるべく,文芸誌のようなものが多く発行され,これらは書店を通してではなく,宅配で売られました。このためにこの時代は雑誌の編集者の方が作家より立場が強く,実際にドストエフスキー自身も雑誌の編集に携わっています。そして小説の多くはこうした雑誌に掲載されました。
この時代,ドストエフスキーに限らず,ロシアの小説はおそろしく長いものが多いのですが,そこにはこういった要因があったようです。買い手であるインテリの要求に応えるためには雑誌は可能な限り厚くする必要が編集側にあり,作家はそれに応えるために小説自体を長くしたのです。一話で完結するわけではなく,何冊かに分けて発表されるとなればなおさらだったでしょう。
確かにこういった外的要因に強いられて,ドストエフスキーの小説も長編が多くなったのまもしれません。登場人物の多さとか,会話の分量の多さなども,むしろ必要性に迫られたからだと考えることもできそうです。
それでは第一部定理二六で必然ということばが用いられるとき,それはどのような意味でいわれているのかということが問題になってきます。もしもこれが自由との関連において用いられているのなら,それは積極的であるといえる要素を構成することが可能です。しかしもしも強制との関連でいわれているのだとしたら,それは積極的であると規定することができる要素を構成するということは不可能であるということになります。
結論からいえば,僕はこれを自由との関連で解釈するべきであると考えています。ただ,これを説明するためには,もしもこれが強制との関連で必然的といわれているなら,この定理はどのように解釈されることになるのかということを考えておいた方が分かりやすいと思うので,先にそちらの方を考えておくことにしましょう。
第一部定理二六をひとつの命題としてみるならば,この問題というのは,必然的ということが,何についていわれているのかという問いとほぼ同列に扱うことができると僕は思っています。そこでもしもこの必然的ということが,強制との関連でいわれていると仮定するならば,それは作用に決定される物についていわれているのです。第一部定義七と照らし合わせたときに,この定理でいわれている神の決定というのを,強制と関連付けて理解することは,第一部定理一七系二からしてできません。ですからこのことは間違いないといっていいでしょう。
ところが,この解釈は,少なくともスピノザが意図しているところとは異なります。なぜなら,第一部定理二六証明の①の部分というのは,物が作用に決定されているということが積極的なもののためであるといっているからです。これはここまでの考察に関連させていうならば,物が作用に決定されているということのうちに,それが積極的であるとみなし得るような要素が含まれているのでなければならないということを,スピノザが主張しているということになるからです。したがってここでいわれている必然的ということを,強制との関連で理解するということは,スピノザの主張に明らかに反しているということになるのです。
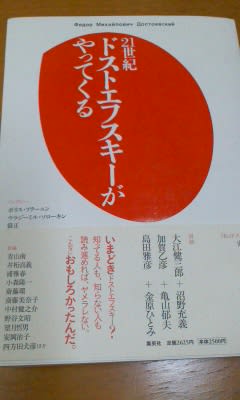
ドストエフスキーが小説を書いていた時代,ロシアの識字率というのは,多く見積もっても20%を超えていませんでした。つまり小説を読むことができるという人は,それだけでインテリとみなすことができたのです。そしてロシアは広大な国家ですから,そうしたインテリというのも各地に分散していました。このために,町で書店を営むということはほぼ不可能でした。よってこの時代の小説は,単行本として読まれるということがあまりなかったのです。
各地のインテリには書物に対する渇望はありました。それに応えるべく,文芸誌のようなものが多く発行され,これらは書店を通してではなく,宅配で売られました。このためにこの時代は雑誌の編集者の方が作家より立場が強く,実際にドストエフスキー自身も雑誌の編集に携わっています。そして小説の多くはこうした雑誌に掲載されました。
この時代,ドストエフスキーに限らず,ロシアの小説はおそろしく長いものが多いのですが,そこにはこういった要因があったようです。買い手であるインテリの要求に応えるためには雑誌は可能な限り厚くする必要が編集側にあり,作家はそれに応えるために小説自体を長くしたのです。一話で完結するわけではなく,何冊かに分けて発表されるとなればなおさらだったでしょう。
確かにこういった外的要因に強いられて,ドストエフスキーの小説も長編が多くなったのまもしれません。登場人物の多さとか,会話の分量の多さなども,むしろ必要性に迫られたからだと考えることもできそうです。
それでは第一部定理二六で必然ということばが用いられるとき,それはどのような意味でいわれているのかということが問題になってきます。もしもこれが自由との関連において用いられているのなら,それは積極的であるといえる要素を構成することが可能です。しかしもしも強制との関連でいわれているのだとしたら,それは積極的であると規定することができる要素を構成するということは不可能であるということになります。
結論からいえば,僕はこれを自由との関連で解釈するべきであると考えています。ただ,これを説明するためには,もしもこれが強制との関連で必然的といわれているなら,この定理はどのように解釈されることになるのかということを考えておいた方が分かりやすいと思うので,先にそちらの方を考えておくことにしましょう。
第一部定理二六をひとつの命題としてみるならば,この問題というのは,必然的ということが,何についていわれているのかという問いとほぼ同列に扱うことができると僕は思っています。そこでもしもこの必然的ということが,強制との関連でいわれていると仮定するならば,それは作用に決定される物についていわれているのです。第一部定義七と照らし合わせたときに,この定理でいわれている神の決定というのを,強制と関連付けて理解することは,第一部定理一七系二からしてできません。ですからこのことは間違いないといっていいでしょう。
ところが,この解釈は,少なくともスピノザが意図しているところとは異なります。なぜなら,第一部定理二六証明の①の部分というのは,物が作用に決定されているということが積極的なもののためであるといっているからです。これはここまでの考察に関連させていうならば,物が作用に決定されているということのうちに,それが積極的であるとみなし得るような要素が含まれているのでなければならないということを,スピノザが主張しているということになるからです。したがってここでいわれている必然的ということを,強制との関連で理解するということは,スピノザの主張に明らかに反しているということになるのです。















