2015年8月4日 富山県
宇奈月温泉早朝散歩
ホテル主催の早朝散歩に参加(ガイド付き)



▲引湯管用トンネル

▲とちの湯







宇奈月ダム


旧トロッコ電車の路線跡


山彦橋






新山彦橋を通過するトロッコ電車:山彦橋より撮影

山彦橋


cosmophantom
2015年8月4日 富山県
宇奈月温泉早朝散歩
ホテル主催の早朝散歩に参加(ガイド付き)



▲引湯管用トンネル

▲とちの湯







宇奈月ダム


旧トロッコ電車の路線跡


山彦橋






新山彦橋を通過するトロッコ電車:山彦橋より撮影

山彦橋


cosmophantom
2015年8月3日 富山県
宇奈月温泉
富山県黒部市
黒部峡谷の玄関口にあり、富山県随一の規模(収容人員3500名)を誇る温泉郷。黒部川上流の黒薙温泉から引湯して、1923(大正12)年に開湯以来、多くの文人墨客から愛されてきた歴史があります。日本一の透明度ともいわれ、黒部川の清流を思わせる無色透明の湯は、肌にやさしいアルカリ性単純泉。源泉温度は90度以上と高く、体の芯から良くあたたまります。とやま観光ナビ
▼ 富山地方鉄道宇奈月温泉駅



▲温泉噴水

▼黒部峡谷鉄道


▼黒部川電気博物館




▲黒部専用鉄道電気機関車(EB5号型)

▲山田 胖(ゆたか)翁之像
黒部峡谷の電源開発や温泉引湯、鉄道敷設などを通してかつて無人だった地が温泉地として繁栄する礎を築いた土木技師


▲富山地方鉄道

▲引湯管







cosmophantom
2015年8月3日 富山県
鐘釣駅⇒宇奈月駅(黒部峡谷鉄道)








▲ 東鐘釣山:お寺の鐘を伏せたような形をしていることから、この名前が付いた。鐘釣という地名はここから。



▲ 残雪


▼ 黒部川第二発電所
黒部峡谷の中で最も視野がひらけた黒部川本流と猫又谷合流点に位置する。出力は7万2000kW。昭和6年(1931)に軌道が猫又から小黒部まで延長されたことに伴い、昭和11年(1936)に竣工した。建物は建築家・山口文象氏の設計によるもの。「富山の建築百選」「日本のモダン・ムーブメントの建築100選」に選定されるなど、戦前のモダン建築の白眉として名高い。猫又駅対岸に、車窓から外観が見える。るるぶ



































▲ 石仏



▲ サル橋(中央):よく見ると手摺がない







▼新柳河原発電所




湖面橋


▲ 新山彦橋

cosmophantom
2015年8月3日 富山県
鐘釣(かねつり)
富山県黒部市
付近にある釣り鐘の形をした山の名に由来している。
黒部峡谷トロッコ電車の見どころのひとつ。宇奈月駅から乗車約60分のところにあり、周辺には「黒部万年雪」や「鐘釣河原」「鐘釣露天風呂」がある。




万年雪



▲かつて御神体として信仰された岩山



▲ 玉アジサイ:多分初めて・・・・

▲ 足湯 有料でした・・・


▲ このスコップは河原露天風呂で使用するもの

▲ 急な階段を下り河原露天風呂へ

▲ 岩風呂 ふむ 野性味ありすぎ!!

▲ 河原露天風呂 想像より多くの人が楽しんでいた。

▲三尊仏

※ トロッコに乗り宇奈月駅へ
cosmophantom
2015年8月3日 富山県
黒部峡谷鉄道
黒部峡谷の電源開発に伴い、その輸送手段として、電源開発が上流に延びるとともに軌道を延長してきた黒部軌道は、昭和12年に現在の終点の欅平まで開通しましたが、当初は電力会社の専用鉄道として、建設用の資材や作業員輸送に重点がおかれていました。しかし、当地方は自然峡谷美を誇る秘境であり、探勝を希望する一般の人が絶えないため、やむを得ず生命の保証をしないことを前提に便乗の取扱いをしておりました。その後、黒部峡谷の自然を求めるお客様の増加と地元の方々の強い要望から、昭和28年11月に地方鉄道法による営業の免許を受け、昭和46年5月には黒部峡谷鉄道として発足し、現在にいたっております。黒部峡谷トロッコ電車ホームページより
宇奈月駅⇒鐘釣駅
おもちゃの様なトロッコ電車に乗り、宇奈月駅から鐘釣駅へ。鐘釣を散策し、再び宇奈月駅へ。宇奈月駅・鐘釣駅間は約1時間!トロッコ電車は黒部川等を上流に向かい沿うように走り黒部峡谷の景観を楽しまさせてくれる。鐘釣の更に先には黒部ダムがある。




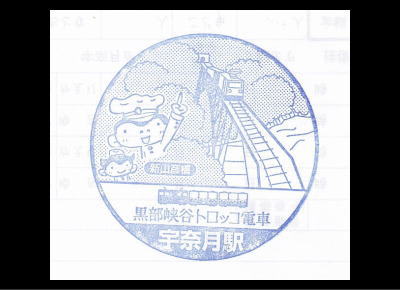

奥 新山彦橋 手前 旧山彦橋








新柳河原発電所:宇奈月ダム資料館「大夢来館」




後曳橋


▲ 水通橋

▲宇奈月ダム


▲黒部川第二発電所

トロッコ電車は冬期は閉鎖される。渓谷の積雪は深いため、発電所の作業員などはこのコンクリートで造られた歩道を利用するとのこと





2015-08-07 06:04:47
cosmophantom
2015年6月21・22・23日
山陰・山陽2015
▼2015年6月21日

▲ 蒜山高原SA:岡山空港より足立美術館へ

▲足立美術館(島根県安来市古川町)

▲玉造温泉(泊)
▼2015年6月21日

▲旧大社駅

▲出雲大社前駅(一畑電車)

▲出雲大社

▲松江城(島根県松江市)

▲塩見縄手(島根県松江市)

▲三朝温泉(鳥取県東伯郡三朝町)
▼2015年6月23日

▲鳥取砂丘(鳥取県鳥取市)

▲備前焼窯元明光窯(岡山県赤磐市仁堀東)

▲倉敷川畔伝統的建造物群保存地区(岡山県倉敷市)

岡山空港より羽田へ
cosmophantom
2015年6月23日 岡山県
倉敷川畔伝統的建造物群保存地区
江戸時代初期の寛永19年(1642年)、江戸幕府の天領に定められた際に倉敷代官所が当地区に設けられ、以来備中国南部の物資の集散地として発展した歴史を持つ。倉敷川の畔から鶴形山南側の街道一帯に白壁なまこ壁の屋敷や蔵が並び、天領時代の町並みをよく残している。1969年に倉敷市の条例に基づき美観地区に定められ、1979年(昭和54年)に県内2件目の重要伝統的建造物群保存地区として選定された。Wikipedia


▲ 今橋
児島虎次郎がデザインしたもので、菊の紋と龍の彫刻が彫られています。 また、橋げたの形を半円にして、水面に映る半円の影と合わせて、満月を見ることが出来るように工夫されています。くらしき観光.comより
大原美術館前の倉敷川に架かる橋で大正15年(1926年)の天皇訪問に合わせ建造。児島虎次郎氏デザインで、大原孫三郎氏の干支にちなんで20体の竜が彫られています。くらしき地域資源ミュージアムより


▲ 倉敷川

▲ 大原美術館 ▼ 1930年(昭和5年)に日本で最初の近代西洋美術館



▲ 旧大原家住宅 ▼ 重要文化財
旧大原家住宅は寛政7年(1795)に主屋の建築が着工され,その後座敷部分が増築され, その先には広い庭が続いています。また,主屋の後ろには蔵が建ち並び, 防火の役目も果たしています。主屋は本瓦葺,厨子二階建てで,屋根は一見入母屋造に見えますが,実際には切妻造りで妻側に付庇を設けた庇付き切妻屋根となっています。また倉敷窓,倉敷格子といった倉敷独特の意匠も備えています。蔵は土蔵造りで,外壁は腰に瓦を張りつけ,目地を白漆喰で盛りあげる『なまこ壁』で仕上げられ,そのコントラストは非常に美しく,倉敷の町並みの景観を特徴づけています。倉敷市ホームページより
▼旧大原家住宅の裏手倉庫群


▲ 有隣荘
大原家別邸となる有隣荘は、1928年(昭和3年)に 大原孫三郎が、病弱な妻を気遣い「家族の為に落ち着いた住まいを」と建設されました。



▲ 中橋

▼ 倉敷考古館
1950(昭和25)年、江戸時代の土蔵作り米倉を改装して開館。今では考古館の建物は、倉敷を象徴する倉として、ポスターや切手をはじめ、様々なデザインにも使用されており側面壁の貼り瓦の美しさも注目を集めています。 倉敷観光WEB

























▼ 倉敷民芸館
江戸時代末期の米倉を改装したもので、白壁と黒の貼り瓦が美しいコントラストを描いています。館内には古今東西の民芸品約700点が展示されています。東京の日本民藝館についで2番目に開館したという歴史を持っています。 倉敷観光WEB






▼ 倉敷案内観光所
大正5年(1916)、倉敷町役場として建てられた木造洋風建築が特徴。登録有形文化財に指定されている。中橋のたもとにあり、現在は観光案内所と無料休憩所になっている。 るるぶ







▲ 加計美術館











cosmophantom
2015年6月23日 岡山県
倉敷考古館
岡山県倉敷市
1950(昭和25)年、江戸時代の土蔵作り米倉を改装して開館。今では考古館の建物は、倉敷を象徴する倉として、ポスターや切手をはじめ、様々なデザインにも使用されており側面壁の貼り瓦の美しさも注目を集めています。 倉敷観光WEB






cosmophantom
2015年6月23日 岡山県
中国銀行倉敷本町支店
岡山県倉敷市本町(現在、中国銀行倉敷支店倉敷本町出張所として営業中)
第一合同銀行の倉敷支店として,大正11年に竣工したルネサンス風の建物です。総社市出身の薬師寺主計が設計しました。彼は大原美術館や有隣荘など,大原家関連の建物の多くに関わった建築家です。 鉄筋コンクリート造り(一部木造)の2階建てで,屋根は寄棟,小屋組はトラス組です。外壁は御影石洗い出しで仕上げられ,腰壁は御影石貼りになっています。正面に6本,側面に3本の円柱をあしらい,屋根は銅板一文字葺きで,前後の屋根上には3つの屋根窓が設けられています。営業室は2階まで吹き抜けになっており,壁と天井は洗練されたデザインの漆喰レリーフで飾られています。当初の姿から増改築・修理工事を経ておりますが,今日も現役の銀行として使用されており,外観・内部ともに保存状態が良好な建物です。 倉敷市ホームページより







cosmophantom