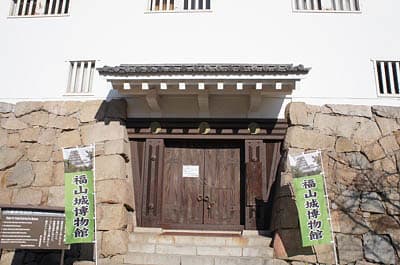2015年12月27日 広島県
竹原 重要伝統的建造物群保存地区
広島県竹原市
平安時代、京都・下鴨神社の荘園として栄えた歴史から、「安芸の小京都」と呼ばれる竹原。そのシンボルといえるのが、落ち着いた風情を漂わす国の重要伝統的建造物群保存地区にも選定された町並み保存地区です。製塩地として飛躍的に発展した江戸時代、豊かな経済力を背景に頼春水・春風・杏坪の兄弟、また、頼山陽ら、多くの優秀な学者を輩出しました。塩田と町人文化の隆盛が生んだ重厚な家々は、今日まで往時の姿を伝えています。 ひろしま観光ナビ



















竹鶴酒造
「竹鶴」醸造元の竹鶴酒造は、元々「小笹屋」として製塩業を営んでいました。 その後、享保18年(1733年)に酒造業を開始しました。日本のウイスキーの父と称される竹鶴政孝も竹鶴家の生まれです。 竹鶴酒造のホームページより






松坂家住宅


















---








▲春風館:頼山陽の叔父で頼春風の邸宅。武家屋敷風の長屋門と門構えをもつ建物でドマを持っています。頼春風(1753~1825)は医学と儒学を大阪で学び、安永2年(1773)故郷に戻り医業を開業しました。安永末年(1780)には塩田経営に乗り出し、天明元年(1781)には春風館を建築。紺屋は叔父伝五郎にゆずりました。 建物の奥には祠堂の茶室を持ち内装は奇屋風の意匠に統一されています。また、安政元年(1854)に焼失し、安政2年(1855)再建され現在、国の重要文化財に指定されています。ひろしま観光ナビ









---
竹楽
江戸末期の文政~安政期(1827~1856)に町年寄りであった菅超右衛門の家と伝えられる。この建物の特徴は母屋の屋根が3段である。文政年間(1861~)には呉服屋「いずみや」があり明治9年の文書では吉井平吉郎と手島平作の名前が見え、のち呉服屋(村上氏)となる。江戸末期頃の建物は本瓦葺、片側入母屋(ねずみ漆喰壁)、母屋の北側に間口3間奥行き6間の本瓦葺妻入の土蔵がある。土蔵の下部はナマコ壁、庇のある鉄格子の小窓、母屋の南側に瓦葺白壁の塀が続き大型町屋の格調を高めた建物。 竹楽ホームページより




---
▼竹原市歴史民俗資料館
昭和の初期、図書館として建てられたレトロモダンな洋風建築。もともとは江戸時代中期の儒学者、塩谷道碩の旧宅跡で、頼山陽の叔父、春風が志を受け継いで学問所にしていたところです。館内には、当時赤穂の塩とともに名を馳せ、町に繁栄をもたらした製塩業の歴史や資料などが展示されています。 ひろしま観光ナビ






ニッカウヰスキーの創業者・竹鶴政孝の生誕120年を記念して、生誕地の竹原市に政孝、リタ夫妻の銅像が建てられた。2015年6月
---




頼推清旧宅
惟清は山陽の祖父で名を又十郎といい、晩年は亨翁と号しました。紺屋を営むかたわら馬杉亨安のもとで和歌を学び著書に「吾妻紀行」「高角紀行」「芳野紀行」などがあります。その子春水・春風・杏坪は、備後国の儒者菅茶山が「兄弟三人同気宇」と讃えたほどの俊才ぞろいで、長男の春水の子山陽も、よき理解者であった叔父の春風をしばしば訪れています。建物は重層屋根、入母屋造、本瓦葺きの母屋と道路に接する離れ座敷からなり、双方とも塗りごめ造です。 ひろしま観光ナビ








▲恵美須堂(胡堂):本町通りの北側に位置する胡堂は、大林宣彦監督の映画『時をかける少女』でもお馴染みのスポット。建築は、前室付、一間社流造りで、竹原の小祠中、最大の規模を持っており、最も古く、江戸時代中期のものと考えられる。 るるぶ
---

▲照蓮寺






酒蔵交流館:江戸末期に建てられた酒蔵の一角を改造した酒蔵交流館は、太い柱や天井のはりが130年余りの伝統を物語り、ほんのりと酒の香りが漂っています。 きてみんさい竹原






光本邸:光本邸は、江戸時代に建てられた「復古館」の離れ座敷で、後年光本家が居住し、後に竹原市に寄贈された建物である。 きてみんさい竹原














---









2016-03-23 05:52:38
☆cosmophantom