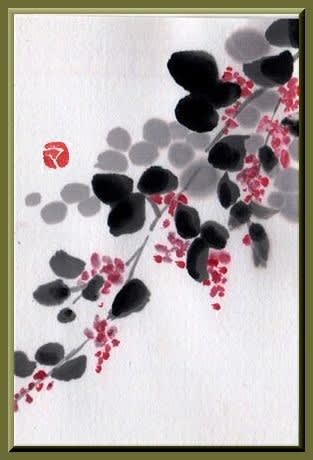秋の気配が漂い始めて体調が少しよくなると、膝の痛みも軽くなってきました。
国見からの帰途に立ち寄った豊後高田の昭和の町では、懐かしい日々を思い出す品々が、過ぎ去った年月を刻んでひっそりと並んでいました。
最後の遠出かと、車の縁があると昔よく出かけた思い出の地を巡っています。20年近くが経過していると、かつての思い出の渡船場は跡形もなく、角島には長い橋が架かっていて、潮流が明瞭に色を異にする不思議も今は鮮明ではなくなり、棚田の風景を飽かず眺めた岬の先には、長いお稲荷さんの鳥居の列が出現していたりです。
好天に恵まれ、以前は自分で車を運転して訪れていた西長門への旅を、今回は甥が案内してくれました。今はさすがに疲れが溜まっていますので、ランダムに写真での展示とします。










国見からの帰途に立ち寄った豊後高田の昭和の町では、懐かしい日々を思い出す品々が、過ぎ去った年月を刻んでひっそりと並んでいました。
最後の遠出かと、車の縁があると昔よく出かけた思い出の地を巡っています。20年近くが経過していると、かつての思い出の渡船場は跡形もなく、角島には長い橋が架かっていて、潮流が明瞭に色を異にする不思議も今は鮮明ではなくなり、棚田の風景を飽かず眺めた岬の先には、長いお稲荷さんの鳥居の列が出現していたりです。
好天に恵まれ、以前は自分で車を運転して訪れていた西長門への旅を、今回は甥が案内してくれました。今はさすがに疲れが溜まっていますので、ランダムに写真での展示とします。