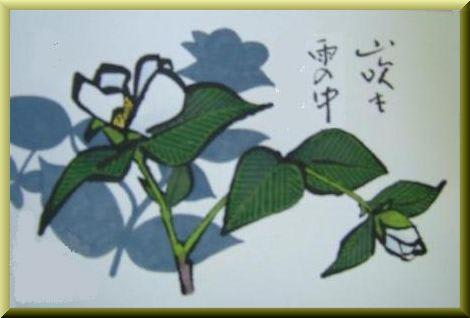昨年末から予約をして楽しみに待っていた東長寺本殿前での薪能拝見が実現しました。午後は雨の予報を案じていましたが無事に終了しました。
梅若流家元の玄祥師がシテ空海をつとめられました。地謡には顔馴染みの九州の同門の歴々が並んでおられました。
東長寺は1205年前、唐から帰国した空海が、上陸の地博多に最初に創建した真言宗では日本最古の霊場です。菩提寺として、二代と三代の福岡藩主黒田公のお墓がある古刹です。九州八十八ヶ所108霊場の第一番札所でもあります。
今回、境内に五重塔が建立された落慶法要の三日間にわたる催しの最期の本公演ガ昨日25日でした。

6時半の開演は、まず東長寺51代住職藤田紫雲師と梅若玄祥師のプレトークから始まりました。住職が、寺の沿革と、民衆と共に生きた空海の事績を語られ、玄祥師は声明が入る今回の曲目に関して、それが不可欠なことを解説され、その意味を興味深く拝聴しました。
ついで、ほら貝を吹き鳴らして僧侶達17人が入場し、最初の声明が高らかに唱えられると、本殿前の見所の場は一種独特なものに包まれました。
その後の篝火への点火の儀も、本殿五間の扉のうち開け放たれている中央の扉の奧から、仏前の灯明が運ばれて、ロウソクの火が移されました。
どう展開するのかと思っていた演能は、声明との不思議な融和のなかで、荘厳に進行してゆきました。
特にシテが何時ものような揚幕からではなく、格子越しにゆらいでいた透影が、やがて本殿の中央から、石窟を思わせる出で登場し、空海が受けた荒れる海上での渡海の苦難を表現、中入りなしに楽の舞が舞われ、揚幕から、前に灯明を捧げた貧しい女が、今度は孔雀明王の本来の姿となって清浄な中にも華麗な姿で登場、救済したのは自分であると名乗り「即ち貧女は玉冠玉衣 清浄瑠璃の翼を羽ばたき、」「羽衣」の天女を思わせる孔雀明王の舞を奏でます。
能楽堂や劇場照明での公演とは全く雰囲気の異なる陰影で、背景も、松が描かれた鏡板ではない仏殿が背景です。篝火の照明だけで、日没後の薄闇が刻々に色を深め移ろう中で、高野山で入定した空海がうつし身の姿を見せて舞う幻影に引き込まれていました。
時間の経過につれて、五重塔の丹の色合いが周囲の木立の色にも同化していき、何年も其処にあったかのように思われ、本来のお能はこのような時間と空間で演じられたのだと、今更のようにしみじみ実感したことでした。
立見席も含めて満席の盛会でしたが、席もS席11列の中央と申し分なく、幽玄の世界に時の経つのを忘れた2時間でした。
後半登場の21人の僧侶による声明の響、能の中の「ノウマクサンマンダァバァサラダァ、・・・」の真言も、合唱の迫力で真に迫り、華麗な孔雀明王の舞も,冠に揺れた孔雀の羽と白一色の装束の美しい幻影の揺曳をいつまでも反芻しつつ帰宅の途につきました。
”あらすじ”は
こちらでご覧になれます。
空海(シテ) 梅若玄祥
貧女・孔雀明王(ツレ) 観世喜正
観賢僧正(ワキ) 宝生 閑
従僧(ワキツレ) 宝生欣也
御厨誠吾
老能力(アド) 山本則重














 6時半の開演は、まず東長寺51代住職藤田紫雲師と梅若玄祥師のプレトークから始まりました。住職が、寺の沿革と、民衆と共に生きた空海の事績を語られ、玄祥師は声明が入る今回の曲目に関して、それが不可欠なことを解説され、その意味を興味深く拝聴しました。
6時半の開演は、まず東長寺51代住職藤田紫雲師と梅若玄祥師のプレトークから始まりました。住職が、寺の沿革と、民衆と共に生きた空海の事績を語られ、玄祥師は声明が入る今回の曲目に関して、それが不可欠なことを解説され、その意味を興味深く拝聴しました。


 浪花いばらが盛りです。ネットでご教示いただいた薔薇の原種の一つです。
浪花いばらが盛りです。ネットでご教示いただいた薔薇の原種の一つです。