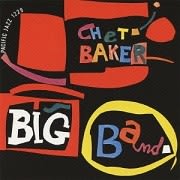本場アメリカと日本で評価の違うジャズマンはたまにいます。今日ご紹介するバディ・リッチもその代表格の1人ですね。本国での彼は"キング・オヴ・ドラム”と呼ばれるジャズドラム界最大のスター。30年代のスイング時代から若き天才ドラマーとして活躍を始め、その後はビッグバンドを率いて80年代まで活躍しました。特にアメリカではテレビショーにも頻繁に出演し、お茶の間でも知られる存在だったようです。
その一方、日本でのリッチの評価はお世辞にも高いとは言えません。さすがに名前ぐらいはジャズファンなら知らない人はいないでしょうが、発売しているCDも全体のごく一部ですし、ジャズ偉人特集にもあまり出てこないですね。日本で人気のジャズドラマーと言えば、まずアート・ブレイキー、ついでマックス・ローチ、エルヴィン・ジョーンズと言った感じでしょうか?60年代以降だとトニー・ウィリアムズも評価が高いですね。全体的に日本のジャズファンの中では"ジャズの主流は黒人"と言う考えが根強くあり、白人ドラマーの彼は少し損をしているところはあります。
かく言う私もリッチについて熱く語るほどの蘊蓄は持っていないのですが、それでも彼のビッグバンド作品はいくつか持っています。有名なのは60年代以降のパシフィック・ジャズ盤「ビッグ・スウィング・フェイス」「マーシー、マーシー」等ですが、今日取り上げるのは1959年にマーキュリー・レコードに吹き込んだ「リッチクラフト」です。確か15年ほど前に今はなき梅田のワルティ堂島で入手した紙ジャケットCDです。
参加メンバーは合計18人。全員列挙はしませんが、トランペットにハリー・エディソン含め5人、トロンボーンにジミー・クリーヴランド、ウィリー・デニス、ビリー・バイヤース、エディ・バートの4人、テナーサックスにベニー・ゴルソンとアル・コーン、アルトサックスにフィル・ウッズとアール・ウォーレン、バリトン・サックスにスティーヴ・パーロウ、リズムセクションはジョン・バンチ(ピアノ)、サム・ハーマン(リズムギター)、フィル・レシン(ベース)、そしてリッチと言う布陣です。アレンジャーは元ベイシー楽団のアーニー・ウィルキンスが務めています。

全9曲。全て3~4分程度の短い演奏ですが、シャープでキレのいいビッグバンドサウンドが堪能できます。ただ、このアルバムの難点は各楽器のソロの記載がないこと。日本語の解説はおろか英語のオリジナルジャケットにもありません。製作者の意図としてはそんな細かいことを気にせずにバンド全体のサウンドを楽しめ!ということなんでしょうが、ジャズファンとしては気になるところ。テナーのベニー・ゴルソンとアル・コーンの聞き分けは容易ですし、フィル・ウッズやハリー・エディソンのソロも聴き馴染みがあるので何となくわかりますが、トロンボーン4人の区別については正直お手上げです。ただ、あえて言うならウィリー・デニスがこの後もリッチのスモールコンボ作品に引き続き参加していますので、彼がソロを取っている可能性が高いかも?
1曲目は有名スタンダードの"Indiana"。テーマメロディをハリー・エディソンが得意のミュートトランペットで吹き、続いてはトロンボーン(ウィリー・デニス?)がソロを取ります。2曲目はアーニー・ウィルキンス作のタイトル曲”Richcraft"。アップテンポのスイングナンバーで、こちらも軽快なトロンボーンソロから始まり、続いてベニー・ゴルソン→アル・コーンとテナーソロをリレーします。3曲目"Sweets Tooth"もウィルキンスのオリジナル。ベイシー風のミディアムスローでまずはトロンボーンがカップミュートでソロを取り、続いて”スイーツ”の異名で知られるハリー・エディソンがソロを聴かせます。4曲目"Clap Hands! Here Comes Charley"はあまり知らない曲ですが、20年代に書かれたスタンダードだそうです。勢いのあるホーンセクションをバックにフィル・ウッズが切れ味の鋭いアルトを聴かせ、次いでエディソン?のハイノートトランペット→アル・コーンと続きます。5曲目”Yardbird Suite"はご存じチャーリー・パーカーの名曲で、ここでは彼の後継者フィル・ウッズが目の覚めるようなソロを披露し、エディソンのミュート・トランペットが後を受けます。
6曲目(B面1曲目)は"Cherokee"。定番のスタンダードですが、アーニー・ウィルキンスの卓越したホーンアレンジに乗せてゴルソン→トランペット→ウッズとソロをリレーし、最後はリッチの圧巻のドラミングで締めくくります。ズバリ本作のハイライトと言って良い名演でしょう。7曲目"I Want A Little Girl"は唯一のバラードで、まずトランペットがソロを取りますが、これは解説曰くジミー・ノッティンガムらしいです。その後アル・コーン→ジョン・バンチのピアノと続きます。8曲目”Fron The Sticks"は作品中最もリッチのドラミングにスポットライトが当たったナンバー。ゴルソン→エディソンのソロに続き、後半はリッチが怒涛のドラムソロを披露します。ラストは"Song Of The Islands"と言うほのぼのしたメロディの曲で、元々ハワイアン・ソングらしいです。アルトがソロを取りますがフィル・ウッズっぽくないので元ベイシー楽団のアール・ウォーレンでしょうか?リッチは全編で迫力あるドラミングを披露しますが、"From The Sticks"を除けば長々とソロを取る場面はなく、どちらかと言うとリーダーとして的確なドラミングで全体をコントロールする役割に重きを置いています。内容的にも粒揃いの曲ばかりで、ビッグバンド好きなら間違いなく楽しめる1枚と思います。