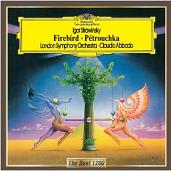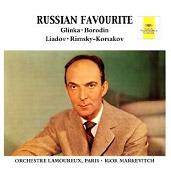前回に引き続きロシア音楽のオムニバスで、イーゴリ・マルケヴィチがフランスのラムールー管弦楽団を指揮して録音したものをご紹介します。マルケヴィチは国籍的にはフランスになるのでしょうが、出生はウクライナということでロシア音楽にも造詣が深かったようですね。収録曲は全6曲。グリンカの「ルスランとリュドミラ」序曲、ボロディンの「中央アジアの草原にて」、リャードフの交響的絵画「ヨハネ黙示録から」、リムスキー=コルサコフの「ロシアの復活祭」、「五月の夜」序曲、「金鶏」組曲です。どちらかと言うとマイナーな曲が多く、通好みの選曲ですね。そのうち最も有名であろうボロディンの
「中央アジアの草原にて」は以前にもUPしたので省略します。
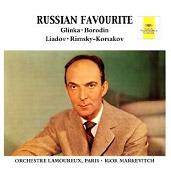
まず、グリンカの「ルスランとリュドミラ」序曲から。グリンカは“近代ロシア音楽の父”と呼ばれている人で、それまでクラシック不毛の地だったロシアで始めて後世に残る作品を生み出した作曲家だとか。この曲は同名のオペラの序曲ですが、今では本編から独立して単独の管弦楽作品として演奏機会も多いようです。19世紀前半の作品ということでロッシーニをはじめとしたイタリア・オペラの影響を感じさせるエネルギッシュかつ起承転結のはっきりした曲です。続いてアナトーリ・リャードフの「ヨハネ黙示録から」ですが、こちらはめったに収録されることのないレア曲ですね。金管と打楽器を多用したドラマチックな展開の曲ですが、正直さほど魅力的とは思いません。
後半はリムスキー=コルサコフの3作品。「シェエラザード」と前回UPした
「スペイン奇想曲」が圧倒的に有名な彼ですが、他も侮るなかれですよ。「ロシアの復活祭」は冒頭不安げな旋律で幕を開け、その後で弦の奏でる幻想的な主題が現れます。それを何度か繰り返した後、フルオーケストラのド迫力の中間部へ。その後、何度か強弱を繰り返し、盛大なフィナーレへ向かいます。続く「五月の夜」はオペラの序曲ですが、一転して穏やかな曲調。特に中間部の素朴な民謡のような旋律が実に美しいです。ほとんど知られていませんが隠れた名曲と言えるのでは?最後の「金鶏」は同名のオペラを25分強の組曲にまとめたもの。こちらも地味な作品ですが、魅力的な旋律があちこちに散らばっています。1曲目の「ドドン王の眠り」の主題、3曲目「シェマハ女王の踊り」「ドドン王の踊り」の主題が特に親しみやすいですね。