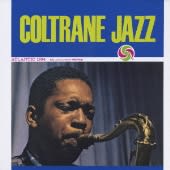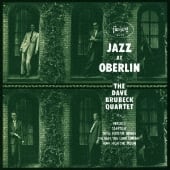
今日ご紹介する「ジャズ・アット・オバーリン」はそんなブルーベックが1953年2月にオハイオ州のオバーリン大学で開催した学園祭ライブの様子を記録したもので、西海岸のレーベルであるファンタジー・レコードから発売されたものです。これまで何度かCDで再発されていましたが、このたび例の「ジャズの100枚」シリーズに含まれていたことから初めて購入しました。メンバーはリーダーのブルーベック(ピアノ)に、相棒で実質的に共同リーダーのポール・デスモンド(アルト)、ベースがロン・クロッティ、ドラムがロイド・デイヴィスという布陣です。後に黄金のカルテットを形成するベースのジーン・ライトとドラムのジョー・モレロはこの時点では加わっていません。全5曲、有名スタンダードばかりのある意味ベタな選曲ですが、ブルーベックとでデスモンドの手によって見事に料理されています。一曲目“These Foolish Things”はウォーミングアップと言った感じですが、二曲目“Perdido”の素晴らしさに最初のノックアウトです。のっけからデスモンドが3分近くにわたってアドリブを繰り広げるのですが、原曲のメロディを完全に崩しながらまるで別の曲を演奏しているかのように次々とメロディアスなフレーズが湧き出てくる様が圧巻です。しかもプレイスタイルも後のクールな印象と違い、かなり熱のこもったもので、デスモンドってこんなに熱かったっけ?と思ってしまいます。後に続くブルーベックのピアノソロもブロックコードを織りまぜたパワフルなものです。
続く“Stardust”は一転してクールなバラードですが、ここでもデスモンドは原曲を大胆にデフォルメさせ、まるで違う曲を演奏しているかのようです。続く“The Way You Look Tonight”と“How High The Moon”も同様で、冒頭にテーマ部分を演奏した後は、デスモンドの天衣無縫のアドリブとブルーベックのアグレッシブなピアノソロが曲に新たな生命を吹き込んでいます。デスモンドと言えば後にダウンビート誌の人気投票で何度も1位を獲得するなど人気を博しましたが、一方でそのソフトなスタイルゆえに自分のことを「世界で最もスローなアルト奏者」と皮肉っていたとか。それが若い頃にはこんな溌剌としていたとは驚きです。ブルーベックもジャズだけでなく現代音楽への造詣も深かったようで、思ったよりトンがった演奏です。ジャズクラブではなく学園ライブなので変なタイミングで拍手が沸き起こったりもしますがそれもご愛嬌。若きブルーベックとデスモンドの予想外にホットなジャズが味わえる傑作です。