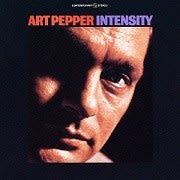先日マーティ・ペイチ「ブロードウェイ・ビット」で予告したとおり、本日はその姉妹盤である”お風呂のペイチ”こと「アイ・ゲット・ア・ブート・アウト・オヴ・ユー」をご紹介します。前作の2ヶ月後の1959年7月に録音されたもので、内容もほぼ同じで西海岸のオールスターを集めたビッグバンドによるスタンダード曲集です。さてこの作品、昔からジャケットが話題ですよね。お風呂上がりの女性の裸がガラス越しに見えそうで見えない、というあたりが男性諸氏に受けたのでしょうか?ただ、私はこのジャケットあまり好きではないです。モデル女性の顔があまりタイプではないと言うのもありますし、何より肝心の音楽の素晴らしさが俗っぽいお色気ジャケットのせいで伝わっていないような気がします。
メンバーですが「ブロードウェイ・ビット」と半分以上かぶります。総勢13人のうちビル・パーキンス(テナー)、アート・ペッパー(アルト)、ボブ・エネヴォルセン(ヴァルヴトロンボーン)、ジョージ・ロバーツ(バストロンボーン)、ヴィンス・デローザ(フレンチホルン)、ヴィクター・フェルドマン(ヴァイブ)、メル・ルイス(ドラム)が引き続き参加のメンバーです。ただ、トランペットはコンテ・カンドリ、ジャック・シェルドン、アル・ポーシノと3人とも入れ替わっており、その他にバリトンサックスにビル・フードが参加。ピアノも前作はペイチが兼務していましたが、今回はアレンジャーに専念したためラス・フリーマンが入り、その他ベースにジョー・モンドラゴンが起用されています。

全8曲。内容も前回と同じくスタンダード中心、ペイチのシャープなアレンジに乗って、各楽器がソロを取ると言う趣向です。ただ、違いは前回がミュージカル曲ばかりだったのに対し、ジャズ曲、特にエリントン楽団絡みの曲が多いのと、特定のソリストにスポットライトを当てた曲が多いのが特徴ですね。エリントン・ナンバーは"It Don't Mean A Thing""What Am I Here For/Cotton Tail""Warm Valley""Things Ain't What They Used To Be"と半分の4曲もあり、ペイチのエリントンへの傾倒ぶりが伺えます。
ただ、ここで特にご紹介したいのは特定のソリストをフィーチャーした曲の方です。まずは2曲目"No More"。ビリー・ホリデイの歌で有名な曲らしいですが、トランペットを大々的にフィーチャーした美しいバラードに仕上がっています。前作同様に曲毎のソリストの記載がないのですが、哀愁漂うトランペットを吹くのはおそらくジャック・シェルドンではないかと推測します。コンテ・カンドリはリーダー作を何枚か持っていますが、こんな乾いた音色ではないはず(アル・ポーシノはよくわからないので除外)。7曲目のエリントン作のバラード"Warm Valley"も素晴らしいですね。ここでダンディズム溢れるバリトンサックスを披露するのはビル・フード。正直あまり馴染みがないミュージシャンですが、なかなか良いソロを聴かせてくれます。"Warm Valley"はジェローム・リチャードソンも「ローミン」で取り上げていましたのでバリトンサックスと相性の良い曲なのかもしれません。
そして何より素晴らしいのがアート・ペッパー絡みの2曲。まずは4曲目、ボビー・ティモンズの"Moanin'"。前年にジャズ・メッセンジャーズがヒットさせた黒人ファンキージャズの聖典をウェストコーストの白人達が取り上げているのが面白いですが、演奏の方も悪くない、どころか良いです。まずはラス・フリーマンの意外とソウルフルなピアノとホーンアンサンブルによるコール & レスポンスの後、ペッパーが独創的なアドリブを披露します。原曲とは全然違うアプローチですがこれがまた様になっています。続く高らかに鳴るトランペットはおそらくコンテ・カンドリでしょう。その後のホーン陣のアレンジも洒落ていてなかなかの名演です。続く"Violets For Your Furs"は歌手のマット・デニスが書いた名バラードでズート・シムズやコルトレーンも名演を残していますが、ここでのペッパーのプレイはそれらをも凌駕する素晴らしさ。澄み切ったアルトの音色と紡ぎ出されるフレーズの美しさに思わず涙が出そうになります。その他の曲はビル・パーキンス、ボブ・エネヴォルセン、ヴィクター・フェルドマンらも加わり、各人が短いソロをつないでいく展開ですが、それらのソロの中でもペッパーのソロは一際輝きを放っており、ウェストコーストの俊英達の中でも傑出した存在だったことがわかります。本作はペイチのアレンジャーとしての手腕を堪能できるだけでなく、ペッパーの天才ぶりをあらためて実感できる1枚です。