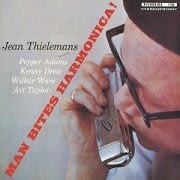本日はセロニアス・モンクです。彼はジャズの歴史に名を遺す”ジャイアンツ”の一人ですが、一方で万人受けするタイプではなく、熱烈なファンもいれば「モンクはパス」と言う人に分かれます。彼の叩きつけるような独特のテンポのピアノはどう考えても華やかさとは程遠く、オスカー・ピーターソンやウィントン・ケリー等の名手と聴き比べると「そもそもモンクってピアノ下手なんちゃうん?」という疑惑を抱かれても不思議はないですよね。実際のモンクは超絶技巧で知られるアート・テイタムから影響を受けており、その気になれば華麗なピアノを弾くこともできたらしいですが、実際に彼のリーダー作でそう言った演奏を聴くことはないです。彼はほとんどの作品で自作曲を演奏しており、複雑怪奇なコード進行を持つ独特のメロディとパーカッシブな演奏スタイルとが相まって唯一無二のモンク・ワールドを作り上げています。
で、私自身のモンクへの評価ですが、日和見的でずるいかもしれませんが「特別好きでもなければ苦手でもない」です。モンクの個性的な自作曲の数々には魅力を感じるものの、一方であの風変わりなピアノを日常的に聴きたいとは思いません。特に何枚かあるソロピアノにはなかなか手が伸びないですね。モンク好きに言わせれば「ソロこそが彼の真骨頂」らしいのですが・・・という訳で私が所有しているモンク作品は全てホーン奏者入りです。以前にご紹介したジャズ・メッセンジャーズとの共同作の他、コルトレーン、ロリンズ、ジェリー・マリガン、チャーリー・ラウズ等と共演相手は作品によって変わりますが、サックスやトランペット等が入ることによりモンクの強烈な個性が中和されて個人的にはちょうどいい感じに落ち着くんですよね。
今日ご紹介する「ミステリオーソ」はジョニー・グリフィンをゲストに迎えたリヴァーサイド盤。1958年8月、ニューヨークのファイヴ・スポット・カフェでのライブを収めたものです。その他の共演者はアーメッド・アブドゥル=マリク(ベース)とロイ・ヘインズ(ドラム)です。なお、本作には同日に録音された「セロニアス・イン・アクション」と言う兄弟盤が存在しますが、個人的には本作の方が出来が良いと思います。なお、ジャケットのヘンテコな絵はイタリアの前衛画家ジョルジョ・デ・キリコの「予言者」と言う有名な作品。モンクの不思議な世界観とよく合っていますね。

さて、肝心のモンクとグリフィンの相性ですがこれがなかなか良いです。そもそもモンクとグリフィンの共演は初めてでなく、前年の「アート・ブレイキーズ・ジャズ・メッセンジャーズ・ウィズ・セロニアス・モンク」には当時ジャズ・メッセンジャーズの一員だったグリフィンも参加していますし、そもそもシカゴNo.1のテナーとして評判を呼んでいたグリフィンを最初にリヴァーサイド社長オリン・キープニューズに推薦したのはモンクだとか。グリフィンはいつもながら熱のこもったアドリブで、相変わらずマイペースのモンクとは全然スタイルが異なるように思えるのですが、実際に聴いてみると違和感なく混じり合っているのがジャズの不思議なところですね。
曲は全6曲。1曲だけスタンダードの”Just A Gigolo”が入っていますが、わずか2分余りの演奏でグリフィンのソロもなく、単なる箸休めでしょう。それ以外は全てモンクの自作曲です。モンクは同じ曲を何度も録音することでも知られていますが、本作でもライブ会場に捧げた”Blues Five Spot”以外は全て既出の曲で、代表曲の1つである”In Walked Bud”をはじめ、”Nutty””Let’s Cool One""Misterioso"と独特のメロディを持ったオリジナルを演奏して行きます。”In Walked Bud”は上述のジャズ・メッセンジャーズ作品、”Nutty”はコルトレーン、”Misterioso”はソニー・ロリンズとも過去に演奏していますので聴き比べて見るのも楽しいですね。