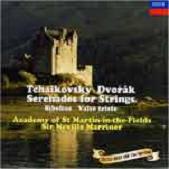本日はリヒャルト・シュトラウスの歌曲「4つの最後の歌」を取り上げたいと思います。この曲はソプラノ独唱とオーケストラのための作品で、84歳の作曲家が死の前年に書いた文字通り“最後の歌”です。リヒャルト・シュトラウスと言えば「ツァラトゥストラはかく語りき」「アルプス交響曲」などカラフルでダイナミックなオーケストラが特徴ですが、この曲は死を目前にした老作曲家が原点に立ち返り、ひたすらメロディの美しさだけを追求したかのような清らかな作品です。
曲は「春」「9月」「眠りにつこうとして」「夕映えの中で」とそれぞれ題が付けられており、最初の3つがヘルマン・ヘッセの、最後がアイヒェンドルフの詩がつけられているそうですが、ドイツ語なので内容はちんぷんかんぷん。ただひたすら曲の天国的な美しさに酔うべし!です。4曲どれも素晴らしいですが、特に「眠りにつこうとして」の最後の部分は、思わず目を閉じて歌の世界に溶け込みたくなるような感動の名唱です。「夕映えの中で」の冒頭のオーケストラも管弦楽の大家シュトラウスならではの美しさです。

CDはエリザベス・シュヴァルツコップのソプラノ、ジョージ・セル指揮ベルリン放送交響楽団のものを買いました。1965年と約半世紀前の録音ですが、未だにこの曲の決定盤として知られています。実は私はもう1枚デイヴィッド・ジンマン指揮の最近の録音のも聴いたことがあるのですが、そこで歌っていたメラニー・ディーナーという歌手とシュヴァルツコップでは確かに歌の上手さが段違いのような気がします。シュヴァルツコップは高音の伸びもさることながら、低音部分や時折聴かせる裏声がゾクッとするものを感じさせますね。
このCDには他にもリヒャルト・シュトラウスの歌曲が12曲納められています。「4つの最後の歌」ほど有名ではありませんが、なかなかいい曲が多いですね。特に「献呈」「東方の三博士」「冬の捧げもの」がお薦めです。
曲は「春」「9月」「眠りにつこうとして」「夕映えの中で」とそれぞれ題が付けられており、最初の3つがヘルマン・ヘッセの、最後がアイヒェンドルフの詩がつけられているそうですが、ドイツ語なので内容はちんぷんかんぷん。ただひたすら曲の天国的な美しさに酔うべし!です。4曲どれも素晴らしいですが、特に「眠りにつこうとして」の最後の部分は、思わず目を閉じて歌の世界に溶け込みたくなるような感動の名唱です。「夕映えの中で」の冒頭のオーケストラも管弦楽の大家シュトラウスならではの美しさです。

CDはエリザベス・シュヴァルツコップのソプラノ、ジョージ・セル指揮ベルリン放送交響楽団のものを買いました。1965年と約半世紀前の録音ですが、未だにこの曲の決定盤として知られています。実は私はもう1枚デイヴィッド・ジンマン指揮の最近の録音のも聴いたことがあるのですが、そこで歌っていたメラニー・ディーナーという歌手とシュヴァルツコップでは確かに歌の上手さが段違いのような気がします。シュヴァルツコップは高音の伸びもさることながら、低音部分や時折聴かせる裏声がゾクッとするものを感じさせますね。
このCDには他にもリヒャルト・シュトラウスの歌曲が12曲納められています。「4つの最後の歌」ほど有名ではありませんが、なかなかいい曲が多いですね。特に「献呈」「東方の三博士」「冬の捧げもの」がお薦めです。