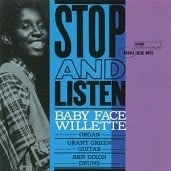ジャズファンならJATPという言葉をどこかで聞いたことがあると思います。Jazz At The Philharmonicの略で、ヴァーヴ・レコードの創設者であるノーマン・グランツが大物ジャズメン達を集めて開いたコンサート・シリーズのことです。メンバーは流動的ですが、代表的な名前を挙げるだけでもレスター・ヤング、ベン・ウェブスター、コールマン・ホーキンス、ベニー・カーター、ジーン・クルーパ、ライオネル・ハンプトン、ディジー・ガレスピー、チャーリー・パーカー等いずれも超のつく大物ばかりです。最も活動が盛んだったのは40年代後半から50年代前半にかけてで、その頃の録音は数も少なく、CD化もあまりされていないこともあって全貌は良く分かりません。そんな中で1957年の秋にシカゴのオペラ・ハウスで行われたコンサートの模様はヴァーヴより複数CD化されており、スタン・ゲッツとJ・J・ジョンソンが共演した「スタン・ゲッツ・アンド・J・J・ジョンソン・アット・ジ・オペラ・ハウス」、エラ・フィッツジェラルドがオスカー・ピーターソン・トリオをバックに歌う「エラ・フィッツジェラルド・アット・ジ・オペラ・ハウス」等があります。今日ご紹介する「モダン・ジャズ・カルテット&オスカー・ピーターソン・トリオ・アット・ジ・オペラ・ハウス」もMJQとオスカー・ピーターソンという人気者同士の組み合わせで、ネイムバリュー的には上記2作に引けを取りません。

ただこの作品、タイトルだけ見ると2つのグループが一緒に演奏するのかと期待しますが、実際は共演盤でもなんでもなく、前半3曲をMJQ、後半5曲をオスカー・ピーターソン・トリオがそれぞれ演奏するだけ。要は人気グループのライヴを2つくっつけただけという安易(?)な企画です。しかも、前半のMJQの部分があまりよろしくない。一応、チャーリー・パーカーの”Now's The Time”やセロニアス・モンクの"'Round Midnight"を演奏していますが、内容的にそこまで特筆すべきところはなし。そもそも私はMJQはそんなに好きではないのですよね。アトランティックの諸作品群の中には良いものもありますけど、これに関しては録音状態も悪いし、演奏にも魅力は感じません。
お薦めは後半のオスカー・ピーターソン・トリオの方です。トリオと言ってもドラムのエド・シグペンを加えた後年のトリオではなく、ギターのハーブ・エリス入りのトリオですね。(本ブログでも以前に「シェイクスピア・フェスティヴァル」を取り上げました。)全5曲ですが、いわゆる定番スタンダードはなく、マイナーな曲を中心にした選曲ですが、どれもクオリティの高い演奏です。1曲目は「雨に唄えば」の作曲者であるナシオ・ハーブ・ブラウンが書いた”Should I”と言う曲。他で聞いた記憶のない曲ですが、実にキャッチーなメロディで、トリオのスインギーな演奏も相まって名曲・名演に仕上がっています。2曲目はラッキー・ミリンダーの書いた”Big Fat Mama”で、こちらはファンキーなブルースです。3曲目はジェイムズ・ハンリーと言う人が書いた”Indiana”。他ではスタン・ゲッツも演奏していますが、ここではピーターソンが超速弾きを披露。それについて行くエリスとブラウンもさすがです。4曲目と5曲目は他のジャズマンのカバーで、クリフオード・ブラウンの”Joy Spring”を落ち着いたミディアム・テンポで、ジェリー・マリガンの”Elevation”を超ハイテンポでそれぞれ料理しています。主役はもちろんピーターソンで、圧倒的なテクニックと抜群のドライブ感でぐいぐい牽引していきますが、時にはソロにそれ以外はリズム・ギターでズンズンズンズンとリズムを刻むハーブ・エリスにも注目です。