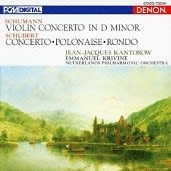本日は再びナクソスからマイナー作曲家シリーズです。最近のブログでもメトネル、モシュコフスキと通好みの作曲家を取り上げましたが、今日ご紹介するヨハン・ハルヴォルセンはさらに輪をかけてマイナーで、ほぼ無名と言って差し支えないかと思います。19世紀末から20世紀初頭にかけて活動したノルウェーの作曲家で、世代的にはグリーグの一世代下にあたります。生前はヴァイオリニストとしても活躍し、また国立歌劇場の指揮者を長年務めるなどノルウェーの音楽界では重要な存在だったようですが、国際的にはほぼ無名に等しいですね。本CDに収録されているヴァイオリン協奏曲はそんなハルヴォルセンの中でもさらにレアな秘曲で、何でも1909年にキャスリーン・パーロウというカナダのヴァイオリニストによって初演されたものの、後にハルヴォルセン自身が楽譜を焼却してしまったそうです。ただ、演奏者であるパーロウが楽譜の写しを持っていたため、それをもとに近年になって再現されたとのこと。そんな秘曲中の秘曲を演奏するのはノルウェーの国際的ヴァイオリニストであるヘニング・クラッゲルード、オケはビャルテ・エンゲセト指揮マルメ交響楽団です。

そんな数奇な運命を辿ったレア曲ですが、内容はなかなか素晴らしく、ナクソスがわざわざCD発売に踏み切ったのもうなずけます。特に第1楽章が素晴らしく、北欧の大地を思わせる雄大なオーケストラに導かれるようにヴァイオリンが鋭利な響きで切り込んできます。中間部の叙情的な旋律も魅力的です。緩徐楽章の第2楽章、歌心たっぷりの第3楽章も申し分ない出来でなかなかの傑作かと思います。こんな隠れた名曲を忘却の彼方から蘇らせてくれたことに感謝したいです。
カップリングは同じく北欧の作曲家であるニールセンのヴァイオリン協奏曲。ニールセンについては過去ブログでも取り上げたようにデンマークの国民的作曲家でヴァイオリン協奏曲は彼の代表作とまでは言えないまでもそこそこ愛好者も多い曲です。本曲もハイライトは第1楽章で、ややアグレッシブな冒頭部の後にヴァイオリンが奏でる美しい旋律、中間部の勇壮な主題と聴きどころたっぷりです。ただ、第2楽章以降はやや取っつきにくいかな。知名度では圧倒的にニールセンの方が上ですが、全体的な内容ではハルヴォルセンの方がより親しみやすいかもしれません。