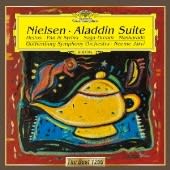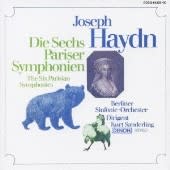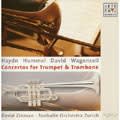前回のニールセンに引き続きネーメ・ヤルヴィ指揮イェーテボリ交響楽団のCDで「ロリポップス」と題された管弦楽小品集をご紹介します。ロリポップは直訳すれば飴玉のことですが、以前に取り上げたトーマス・ビーチャムの小品集も同じ題名でしたのでそちらを意識したのかもしれません。マイナー作曲家の、しかもワルツやオペラ序曲等軽めの曲ばかりで、購入時には正直あまり期待していなかったのですが、なかなか楽しめる内容でした。全12曲ありますが全て名曲と言うわけではありませんのでお気に入りの5曲だけピックアップします。

まずは1曲目。「メリー・ウィドウ」で有名なフランツ・レハールの「金と銀」と言うワルツです。題名通り金銀が散りばめられたようなきらびやかな曲で、ありし日のウィーンの舞踏会の様子が目に浮かびます。フィナーレの盛り上がりが最高ですね。続いて3曲目、有名なワルツでエミール・ワルトトイフェルの「スケーターズ・ワルツ」。名前はドイツ風ですが19世紀後半に活躍したフランスの作曲家だそうです。作曲家自体は今ではすっかりマイナーですが、この曲は有名で色々なところでBGM使としてわれています。私などは子供の頃にやっていたマーガリンのCM♪パンにマリーナ、を思い出します。
お次は5曲目、シャルル・グノーのオペラ「ファウスト」から「ファウストのワルツ」。夢見るような華麗なワルツの調べから後半に向けて怒濤の盛り上がりを見せるあたりが圧巻です。7曲目、エミール・レズニチェクの「ドンナ・アンナ」序曲は恥ずかしながら曲名も作曲家名も全く聴いたことありませんが19世紀末にプラハを中心に活躍したそうです。民族的にはチェコ人のようですが、ドヴォルザークやスメタナらいわゆる国民楽派ではなく、普通のドイツ・ロマン派のようです。この曲は同名のオペラの序曲ですが、疾走感あふれるオーケストレーションと思わず口ずさみたくなるようなう歌心ある旋律が融合した名曲と思います。
最後は12曲目、スウェーデンのヒューゴ・アルヴェーンの「夏至の徹夜祭」。ワルツや序曲ばかり集めた本CDの中では異色ですが、オケがスウェーデンのイェーテボリ交響楽団と言うことでご当地ものを収録したのかもしれません。北欧の短い夏を楽しむ人々の様子を描いた曲で、全編親しみやすい旋律に彩られています。冒頭の部分が「きょうの料理」のテーマ曲に酷似していますが、もちろん時代的にはアルヴェーンの方が先(1901年の作曲)ですので、「きょうの料理」の方がパクリでしょう。序盤のユーモラスで楽しげな雰囲気の後、北欧の夕暮れを思わせるようなやや哀愁感漂う旋律が続き、最後は再び冒頭の主題をフルオーケストラで演奏して華々しく終わります。13分ほどの間に色々な要素がギュッと詰まった名曲中の名曲だと思います。ここで紹介しなかった曲は正直まあまあと言ったところですが、この5曲だけでも買う価値はあると思います。

まずは1曲目。「メリー・ウィドウ」で有名なフランツ・レハールの「金と銀」と言うワルツです。題名通り金銀が散りばめられたようなきらびやかな曲で、ありし日のウィーンの舞踏会の様子が目に浮かびます。フィナーレの盛り上がりが最高ですね。続いて3曲目、有名なワルツでエミール・ワルトトイフェルの「スケーターズ・ワルツ」。名前はドイツ風ですが19世紀後半に活躍したフランスの作曲家だそうです。作曲家自体は今ではすっかりマイナーですが、この曲は有名で色々なところでBGM使としてわれています。私などは子供の頃にやっていたマーガリンのCM♪パンにマリーナ、を思い出します。
お次は5曲目、シャルル・グノーのオペラ「ファウスト」から「ファウストのワルツ」。夢見るような華麗なワルツの調べから後半に向けて怒濤の盛り上がりを見せるあたりが圧巻です。7曲目、エミール・レズニチェクの「ドンナ・アンナ」序曲は恥ずかしながら曲名も作曲家名も全く聴いたことありませんが19世紀末にプラハを中心に活躍したそうです。民族的にはチェコ人のようですが、ドヴォルザークやスメタナらいわゆる国民楽派ではなく、普通のドイツ・ロマン派のようです。この曲は同名のオペラの序曲ですが、疾走感あふれるオーケストレーションと思わず口ずさみたくなるようなう歌心ある旋律が融合した名曲と思います。
最後は12曲目、スウェーデンのヒューゴ・アルヴェーンの「夏至の徹夜祭」。ワルツや序曲ばかり集めた本CDの中では異色ですが、オケがスウェーデンのイェーテボリ交響楽団と言うことでご当地ものを収録したのかもしれません。北欧の短い夏を楽しむ人々の様子を描いた曲で、全編親しみやすい旋律に彩られています。冒頭の部分が「きょうの料理」のテーマ曲に酷似していますが、もちろん時代的にはアルヴェーンの方が先(1901年の作曲)ですので、「きょうの料理」の方がパクリでしょう。序盤のユーモラスで楽しげな雰囲気の後、北欧の夕暮れを思わせるようなやや哀愁感漂う旋律が続き、最後は再び冒頭の主題をフルオーケストラで演奏して華々しく終わります。13分ほどの間に色々な要素がギュッと詰まった名曲中の名曲だと思います。ここで紹介しなかった曲は正直まあまあと言ったところですが、この5曲だけでも買う価値はあると思います。