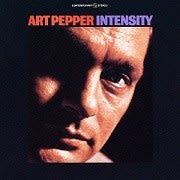1958年にブルーノートからリヴァーサイドに移籍したジョニー・グリフィンは「ジョニー・グリフィン・セクステット」「ウェイ・アウト」「リトル・ジャイアント」とストレートアヘッドなハードバップ作品を次々と発表し、ジャズテナーのスターとしての地位を確立します。ただ、その後はエディ・ロックジョー・デイヴィスとのツインテナー”グリフ&ロック”として活動する一方、ソロ名義では少し変わった作風にチャレンジするようになります。
1961年の「チェンジ・オヴ・ぺイス」はフレンチホルンとベース2本でなおかつピアノレスと言う異色の編成。続く「ホワイト・ガーデニア」は亡きビリー・ホリデイに捧げたストリングス入りの作品です。ただ、正直言ってそれらの試みは成功しているとは言い難く、私的には上記2作は失敗作と言っても良いと思います。今日ご紹介する「ザ・ケリー・ダンサーズ」は「ホワイト・ガーデニア」の次に発表された作品で、ここでもグリフィンはアイルランドや英国のトラディショナルソングを大々的に取り上げており、試み自体はとてもユニークです。ただ、編成自体はシンプルなワンホーン・カルテットと言うこともあり、意外と普通に聴けるジャズに仕上がっています。なお、リズムセクションはバリー・ハリス(ピアノ)、ロン・カーター(ベース)、ベン・ライリー(ドラム)と言う顔ぶれです。

全8曲、うち前半(レコードのA面)4曲は全てトラディショナルソングです。タイトルトラックの"The Kerry Dancers"はアイルランド、2曲目"Black Is The Color Of My True Love's Hair"はスコットランド、3曲目"Green Grow The Rushes"はイングランドの民謡です。youtubeで原曲を検索するとジュディ・コリンズやケルティック・ウーマンが歌ったバージョンが出てくるので、聴き比べてみると面白いと思います。グリフィンはバリー・ハリス・トリオをバックに気持ちよくブロウしており、どの曲も快適なミディアムチューンに仕上がっています。4曲目"The Londonderry Air”は"Danny Boy"の名前で日本人にもすっかりお馴染みのアイルランド民謡。この曲はビル・エヴァンスも「エンパシー」で取り上げていましたが、ここでも美しいバラードに仕上がっています。
後半は民謡縛りから外れ、サラ・キャシーと言う人のオリジナル曲が2曲(”25½ Daze""Ballad For Monsieur")あります。この人のことは良く知りませんでしたが、デトロイト出身の黒人の女性ピアニストだそうです。前者はシンプルなリフのブルース、後者はタイトル通りバラードですがちと地味か?グリフィン唯一のオリジナル曲"Oh, Now I See"もバラードでこちらの方が良いですね。グリフィンのダンディズム香るバラードプレイがシブいです。残る1曲は”Hush-A-Bye"で、サミー・フェインが書いた映画音楽です。hush-a-byeは英語で♪ねんねんころり、という意味があるようですが、グリフィンのバージョンは寝た子も目が覚めるような力強いプレイで、グリフィンのソウルフルなテナーが素晴らしいです。