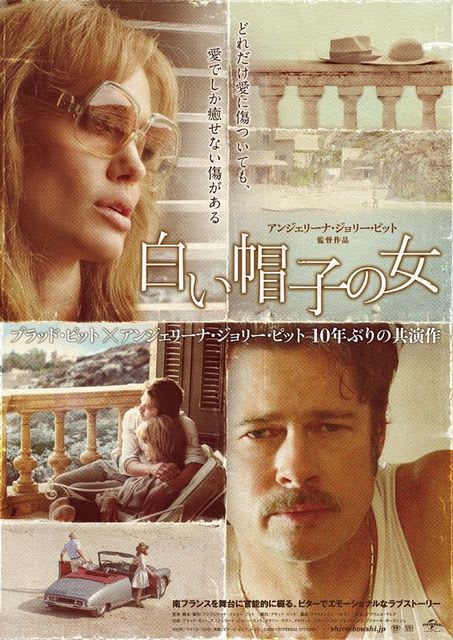切なさに浸る

* * * * * * * * * *
本作、「アカデミー賞、作品賞受賞おめでと~!」
というタイミングで、本日の投稿としたかったのですが、
残念でした・・・!!
なんですかねえ、アカデミー賞はやっぱり社会性がないとダメなのでしょうか。
エンタテイメントだっていいじゃないか!!と私は思うのですが。
なんだか賞の権威付けみたいな意図を感じていや~な感じ。
あ、もちろんムーンライトも素晴らしい作品なのだろうと思い、
期待もしていますが。
さてさて、この日、私は「ナイスガイズ!」と本作の2本立て。
ライアン・ゴズリングの2連発。
やはり勢いにノッている俳優というのはあるのかもしれません。
アクションでも、ピアノでもダンスでも、ぴたりと決まってしまう。
カッコイイですね。
ちなみに私は「ドライヴ」以来のライアン・ゴズリングファンであります。

ミュージカルにはアレルギー反応を起こす方もいるけれど、
私はキライではありません。
特に本作は、ストーリーから音楽への入り方がとても自然なので、
苦手な方でも馴染みやすいと思います。

まずは冒頭シーン。
渋滞しているロサンゼルスの高速道路。
車を降りた人々の歌とダンスが突然に始まるのですが、
なんとも意表をついてカッコイイ!!
物語の始まりのワクワク感を煽ります。
さて、その渋滞した道路で、女優志望のミア(エマ・ストーン)と、
売れないジャズピアニスト・セバスチャン(ライアン・ゴズリング)が、最悪の出会いをします。
2度めの出会いは、素敵なピアノの音色に誘われてレストランに足を踏み入れたミアが、
あの感じ悪い男がそのピアノを弾いているのを目にした時。
でもタイミングが悪くて、ミアは言葉をかけそびれてしまいます。
そして3度めの出会い。
そもそもこの広いロスでこんなに何度も偶然に出会うのは、
それだけでもう奇跡ですけれど・・・。
あるパーティで、ミアは
不機嫌に80年代ポップスを演奏しているセブ(セバスチャンの愛称、この呼び方のほうがいい!!)と再会。
ようやくまともに話をした二人。
女優になりたいミアと、ジャズの店を持って自分の好きな演奏をしたいセブ。
それぞれの夢を持つ二人の心が接近していきます。
・・・が、幸福の絶頂の後には、お定まり、心のすれ違いが・・・
ということで、ストーリーはとてもオーソドックスなラブストーリー。

街を見下ろす夕景のダンス。
プラネタリウムの星々の合間に浮かんでのダンス。
ロマンチックで美しい映像が心に染み渡ります。
本作、スマホも出てくるれっきとした現代の物語なのですが、
何故か一時代前のもののようなノスタルジーを感じます。
なぜかと思うに、音楽がロックじゃない!!
基調はジャズなんですね。
作中ではもうジャズは廃れているなどと言われています。
そこを大事に思うセブだから・・・こういう感じ。
このようにあったのかもしれない人生・・・、
ラストシーンはひたすらに切なく、浸りきってしまうのでした。

ピアノを3ヶ月間一心不乱に練習したというライアン・ゴズリング。
ピアノを弾く手元のシーンまでも一切差し替えなしとのことですが、
本当に素晴らしかった。
今度はIMAXシアターの巨大スクリーンでもう一度見に行こうかなあ・・・
などと思っています。

「ラ・ラ・ランド」
2016年/アメリカ/128分
監督:デイミアン・チャゼル
出演:ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン、キャリー・ヘルナンデス、ジェシカ・ローゼンバーグ、ソノヤ・マズノ
切ないラブストーリー度★★★★★
満足度★★★★★

* * * * * * * * * *
本作、「アカデミー賞、作品賞受賞おめでと~!」
というタイミングで、本日の投稿としたかったのですが、
残念でした・・・!!
なんですかねえ、アカデミー賞はやっぱり社会性がないとダメなのでしょうか。
エンタテイメントだっていいじゃないか!!と私は思うのですが。
なんだか賞の権威付けみたいな意図を感じていや~な感じ。
あ、もちろんムーンライトも素晴らしい作品なのだろうと思い、
期待もしていますが。
さてさて、この日、私は「ナイスガイズ!」と本作の2本立て。
ライアン・ゴズリングの2連発。
やはり勢いにノッている俳優というのはあるのかもしれません。
アクションでも、ピアノでもダンスでも、ぴたりと決まってしまう。
カッコイイですね。
ちなみに私は「ドライヴ」以来のライアン・ゴズリングファンであります。

ミュージカルにはアレルギー反応を起こす方もいるけれど、
私はキライではありません。
特に本作は、ストーリーから音楽への入り方がとても自然なので、
苦手な方でも馴染みやすいと思います。

まずは冒頭シーン。
渋滞しているロサンゼルスの高速道路。
車を降りた人々の歌とダンスが突然に始まるのですが、
なんとも意表をついてカッコイイ!!
物語の始まりのワクワク感を煽ります。
さて、その渋滞した道路で、女優志望のミア(エマ・ストーン)と、
売れないジャズピアニスト・セバスチャン(ライアン・ゴズリング)が、最悪の出会いをします。
2度めの出会いは、素敵なピアノの音色に誘われてレストランに足を踏み入れたミアが、
あの感じ悪い男がそのピアノを弾いているのを目にした時。
でもタイミングが悪くて、ミアは言葉をかけそびれてしまいます。
そして3度めの出会い。
そもそもこの広いロスでこんなに何度も偶然に出会うのは、
それだけでもう奇跡ですけれど・・・。
あるパーティで、ミアは
不機嫌に80年代ポップスを演奏しているセブ(セバスチャンの愛称、この呼び方のほうがいい!!)と再会。
ようやくまともに話をした二人。
女優になりたいミアと、ジャズの店を持って自分の好きな演奏をしたいセブ。
それぞれの夢を持つ二人の心が接近していきます。
・・・が、幸福の絶頂の後には、お定まり、心のすれ違いが・・・
ということで、ストーリーはとてもオーソドックスなラブストーリー。

街を見下ろす夕景のダンス。
プラネタリウムの星々の合間に浮かんでのダンス。
ロマンチックで美しい映像が心に染み渡ります。
本作、スマホも出てくるれっきとした現代の物語なのですが、
何故か一時代前のもののようなノスタルジーを感じます。
なぜかと思うに、音楽がロックじゃない!!
基調はジャズなんですね。
作中ではもうジャズは廃れているなどと言われています。
そこを大事に思うセブだから・・・こういう感じ。
このようにあったのかもしれない人生・・・、
ラストシーンはひたすらに切なく、浸りきってしまうのでした。

ピアノを3ヶ月間一心不乱に練習したというライアン・ゴズリング。
ピアノを弾く手元のシーンまでも一切差し替えなしとのことですが、
本当に素晴らしかった。
今度はIMAXシアターの巨大スクリーンでもう一度見に行こうかなあ・・・
などと思っています。

「ラ・ラ・ランド」
2016年/アメリカ/128分
監督:デイミアン・チャゼル
出演:ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン、キャリー・ヘルナンデス、ジェシカ・ローゼンバーグ、ソノヤ・マズノ
切ないラブストーリー度★★★★★
満足度★★★★★