登録はしたけれど・・・
* * * * * * * *
世界中に広がり、「ソーシャルネットワーク」の映画でも評判となったフェイスブックですが、
日本ではまだ活用度はイマイチのように思えます。
かくいう私も、米留学中の娘に勧められて登録したまでは良かったのですが、
使い方がわからず、その後ほったらかしでした。
この際、この本を読んで少し勉強してから、
もう少しまともに使いこなしてみようと思ったわけです。
本のまえがきにもありました。
「使い方がわからない」「何をしていいのか困る」と戸惑い、
登録しただけで放ったらかしにしている人も多いと。
そうでしょう、そうでしょう・・・。
ということで、このフェイスブックで何ができるのか、
まずそこのところを追求してみましょう。
・・・ですが、まずその前に、フェイスブックの大前提、実名主義について。
実は登録の時にちょっとためらってしまいました。
実名登録。
これまで仮名が当たり前のネット社会で、これはちょっと勇気がいりますよね。
むろんこれも仮名で登録しようと思えばできなくはないのですが、
今や世界では、本人確認のためにフェイスブックを利用するようなこともあるそうで、
仮名を使うと後々困ることになるかもしれないとのこと。
仮名で誹謗中傷、無責任な発言が横行することもある実態を考えれば、
実名で責任のある発言を皆がするようになった方が安心です。
ネットはともすると仮想空間、実生活とは別の世界になりがちですが、
実名を使うことにより、より現実に即したモノとなるような気がします。
しかし、日本でも名前は多くの方がローマ字で登録するそうで、
うわ、しまった!
私はもろに漢字を使ってしまいました。
(汗っ!!)
では、フェイスブックの使いどころ・・・
★家族や友人とのつながりが深まる。
どこの誰ともしれない人のためではなく、
本当の家族や友人に向けてメッセージが発信できるし、相手の近況も知ることができる。
★それほど頻繁に書き込む必要がない。
筆まめな人もそうでない人も、それぞれの使い方ができる。
★世界とつながっていることを実感。
★ゲーム多種あり
うーん、はりきったわりに、やりたいことって少ない。
といいますか、何しろ身の回りにフェイスブックを使っている人がいなければ、
どうにもならないですよね。
さしあたっては、娘とのやりとりに使うだけ・・・
という認識をあらためただけだったりして。
これは将来的にもっと多くの人が利用し始めると面白くなるかもしれませんが、
今はまだどうなのか・・・という印象です。
でも、突然ブログ画面にフェイスブックの「いいね!」ボタンができていたりして、
環境は思った以上に整ってきていますね。
(その使い方を解っていないのが問題!)
著者は、まずプロフィールの欄だけでも意味がある、といっています。
自分の興味のある音楽や趣味、
ここを詳しく描けば、以前当ブログでご紹介した
「偏愛マップ」の役割を果たしそうです。
でも著者は、いきなり知らない人に友達リクエストをするのは、マナー違反ともいっています。
う~ん、やはり使い方が難しい。
3年後、5年後・・・。
はたして日本でもフェイスブックはなくてはならないものになっているのかどうか。
乞うご期待。
「いいね! フェイスブック」野本響子 朝日新書
満足度★★★☆☆
 | いいね! フェイスブック (朝日新書) |
| 野本響子 | |
| 朝日新聞出版 |
* * * * * * * *
世界中に広がり、「ソーシャルネットワーク」の映画でも評判となったフェイスブックですが、
日本ではまだ活用度はイマイチのように思えます。
かくいう私も、米留学中の娘に勧められて登録したまでは良かったのですが、
使い方がわからず、その後ほったらかしでした。
この際、この本を読んで少し勉強してから、
もう少しまともに使いこなしてみようと思ったわけです。
本のまえがきにもありました。
「使い方がわからない」「何をしていいのか困る」と戸惑い、
登録しただけで放ったらかしにしている人も多いと。
そうでしょう、そうでしょう・・・。
ということで、このフェイスブックで何ができるのか、
まずそこのところを追求してみましょう。
・・・ですが、まずその前に、フェイスブックの大前提、実名主義について。
実は登録の時にちょっとためらってしまいました。
実名登録。
これまで仮名が当たり前のネット社会で、これはちょっと勇気がいりますよね。
むろんこれも仮名で登録しようと思えばできなくはないのですが、
今や世界では、本人確認のためにフェイスブックを利用するようなこともあるそうで、
仮名を使うと後々困ることになるかもしれないとのこと。
仮名で誹謗中傷、無責任な発言が横行することもある実態を考えれば、
実名で責任のある発言を皆がするようになった方が安心です。
ネットはともすると仮想空間、実生活とは別の世界になりがちですが、
実名を使うことにより、より現実に即したモノとなるような気がします。
しかし、日本でも名前は多くの方がローマ字で登録するそうで、
うわ、しまった!
私はもろに漢字を使ってしまいました。
(汗っ!!)
では、フェイスブックの使いどころ・・・
★家族や友人とのつながりが深まる。
どこの誰ともしれない人のためではなく、
本当の家族や友人に向けてメッセージが発信できるし、相手の近況も知ることができる。
★それほど頻繁に書き込む必要がない。
筆まめな人もそうでない人も、それぞれの使い方ができる。
★世界とつながっていることを実感。
★ゲーム多種あり
うーん、はりきったわりに、やりたいことって少ない。
といいますか、何しろ身の回りにフェイスブックを使っている人がいなければ、
どうにもならないですよね。
さしあたっては、娘とのやりとりに使うだけ・・・
という認識をあらためただけだったりして。
これは将来的にもっと多くの人が利用し始めると面白くなるかもしれませんが、
今はまだどうなのか・・・という印象です。
でも、突然ブログ画面にフェイスブックの「いいね!」ボタンができていたりして、
環境は思った以上に整ってきていますね。
(その使い方を解っていないのが問題!)
著者は、まずプロフィールの欄だけでも意味がある、といっています。
自分の興味のある音楽や趣味、
ここを詳しく描けば、以前当ブログでご紹介した
「偏愛マップ」の役割を果たしそうです。
でも著者は、いきなり知らない人に友達リクエストをするのは、マナー違反ともいっています。
う~ん、やはり使い方が難しい。
3年後、5年後・・・。
はたして日本でもフェイスブックはなくてはならないものになっているのかどうか。
乞うご期待。
「いいね! フェイスブック」野本響子 朝日新書
満足度★★★☆☆

























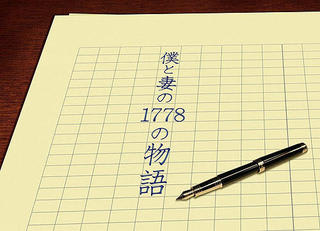




 本日は007第6作目の「女王陛下の007」。
本日は007第6作目の「女王陛下の007」。 でも、これはショーン・コネリーではないんだね。
でも、これはショーン・コネリーではないんだね。 それから、なんとボンドとボンドガールがついに結婚しちゃう!!
それから、なんとボンドとボンドガールがついに結婚しちゃう!! うそー。そんな話聞いたことないけど?
うそー。そんな話聞いたことないけど? いや、ホントに。けどまあ、長くは続かないというか・・・。
いや、ホントに。けどまあ、長くは続かないというか・・・。 はい・・・。
はい・・・。 何、その力のなさは・・・?
何、その力のなさは・・・? ジョージ・レーゼンビーか・・・。
ジョージ・レーゼンビーか・・・。 何だか花がない。・・・見るたびに「誰だこれ?」とつい思ってしまう。
何だか花がない。・・・見るたびに「誰だこれ?」とつい思ってしまう。





















