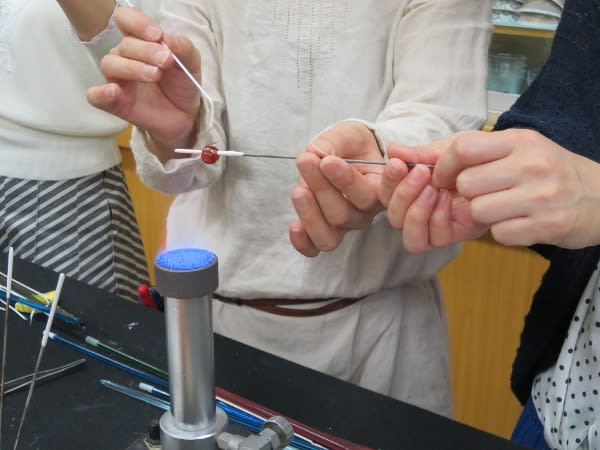3株植えてあったアーティチョーク
一株はすさまじいアブラムシ攻勢に負けて枯れてしまいましたが、2株は無事に冬を越しつぼみが上がってきました。

上から見たところ

食べるとしたらこのくらいを食べるんだろうか。でも、食べません。今回は花を楽しみにします。どうせ食べられるところはちょっとしかないし。食べた時のことはこちら
つぼみはぐんぐん大きくなり、直径3センチはあろうかという太い茎と、まっすぐ大きく広げた葉と、実に力強い立ち姿になりました。道行く人がしげしげと眺めて、中には畑の中に入り込んで四方八方から眺めてみる人まで現れました。これ、高さは1メートルを超えていると思います。

大人の拳よりも大きいつぼみ。春先の強風にも負けずしっかりと立っておりました。

が、
油断しました。つぼみはどんどん大きくなって、重くなることを忘れておりました。ある日、ついに強風に耐えきれず倒れてしまいました。
あわてて支柱を立てましたが後の祭り。

一度倒れた茎はその勢いを回復することなくしおれる一方でした。にもかかわらず、最後の力を振り絞って花を咲かせました。
そしてこちらは最後に残った1本です。これは一度植えてから場所を移した株で、そのためか著しく成長が遅れていました。

でも、春からは遅れを取り戻すかのように勢いを増し、少し遅れて花を咲かせました。

同じ頃にすかし百合も咲きましたが、百合の大きさをはるかにしのぐ大輪の花でした。ただ、以前見た花と少し印象が違います。萼がやたらと大きい気がするんですが、どうしてかな?

これを見るとほんとに頑丈そうなのですが、
アーティチョークってみかけによらず案外もろいのではないでしょうか。高温多湿に弱く、あんな小さな虫にも簡単にやられちゃって、移植にも弱いようです。いったん倒れたら二度と回復しませんし・・・
さて、花が終わった後は、
種ができるはずなんですが・・・

先に倒れて枯れた花、(これは多分種が熟しそうもないので)を割ってみましたら山姥の髪の毛のようなものがぞっわっと出てきました。
いやあ、咲いたときだけでなく枯れた後まで強烈な花でした。
ところで、我が家のアーティチョーク、実に立派に咲いたと自負しておりましたが、
たまたま通りがかったおうちの庭先にアーティチョークを植えてあるのを発見。それがねえ


高さは2メートル近いのではなかろうかと思われました。しかも支柱も立ててないような。そして枝分かれした先に大量のつぼみ。化粧パフのようにふさふさした花。
まいりました
一株はすさまじいアブラムシ攻勢に負けて枯れてしまいましたが、2株は無事に冬を越しつぼみが上がってきました。

上から見たところ

食べるとしたらこのくらいを食べるんだろうか。でも、食べません。今回は花を楽しみにします。どうせ食べられるところはちょっとしかないし。食べた時のことはこちら
つぼみはぐんぐん大きくなり、直径3センチはあろうかという太い茎と、まっすぐ大きく広げた葉と、実に力強い立ち姿になりました。道行く人がしげしげと眺めて、中には畑の中に入り込んで四方八方から眺めてみる人まで現れました。これ、高さは1メートルを超えていると思います。

大人の拳よりも大きいつぼみ。春先の強風にも負けずしっかりと立っておりました。

が、
油断しました。つぼみはどんどん大きくなって、重くなることを忘れておりました。ある日、ついに強風に耐えきれず倒れてしまいました。
あわてて支柱を立てましたが後の祭り。

一度倒れた茎はその勢いを回復することなくしおれる一方でした。にもかかわらず、最後の力を振り絞って花を咲かせました。
そしてこちらは最後に残った1本です。これは一度植えてから場所を移した株で、そのためか著しく成長が遅れていました。

でも、春からは遅れを取り戻すかのように勢いを増し、少し遅れて花を咲かせました。

同じ頃にすかし百合も咲きましたが、百合の大きさをはるかにしのぐ大輪の花でした。ただ、以前見た花と少し印象が違います。萼がやたらと大きい気がするんですが、どうしてかな?

これを見るとほんとに頑丈そうなのですが、
アーティチョークってみかけによらず案外もろいのではないでしょうか。高温多湿に弱く、あんな小さな虫にも簡単にやられちゃって、移植にも弱いようです。いったん倒れたら二度と回復しませんし・・・
さて、花が終わった後は、
種ができるはずなんですが・・・

先に倒れて枯れた花、(これは多分種が熟しそうもないので)を割ってみましたら山姥の髪の毛のようなものがぞっわっと出てきました。
いやあ、咲いたときだけでなく枯れた後まで強烈な花でした。
ところで、我が家のアーティチョーク、実に立派に咲いたと自負しておりましたが、
たまたま通りがかったおうちの庭先にアーティチョークを植えてあるのを発見。それがねえ


高さは2メートル近いのではなかろうかと思われました。しかも支柱も立ててないような。そして枝分かれした先に大量のつぼみ。化粧パフのようにふさふさした花。
まいりました