







マユハケオモト。その名の通り、本来は化粧パフみたいにふわふわの花なんですけどね。


もう一つ、秋の七草のフジバカマ。これが思いがけないところに植えてあって、アサギマダラが来るのだそうです。地元の方のブログでそれを知って急いで見に行きましたが






























































































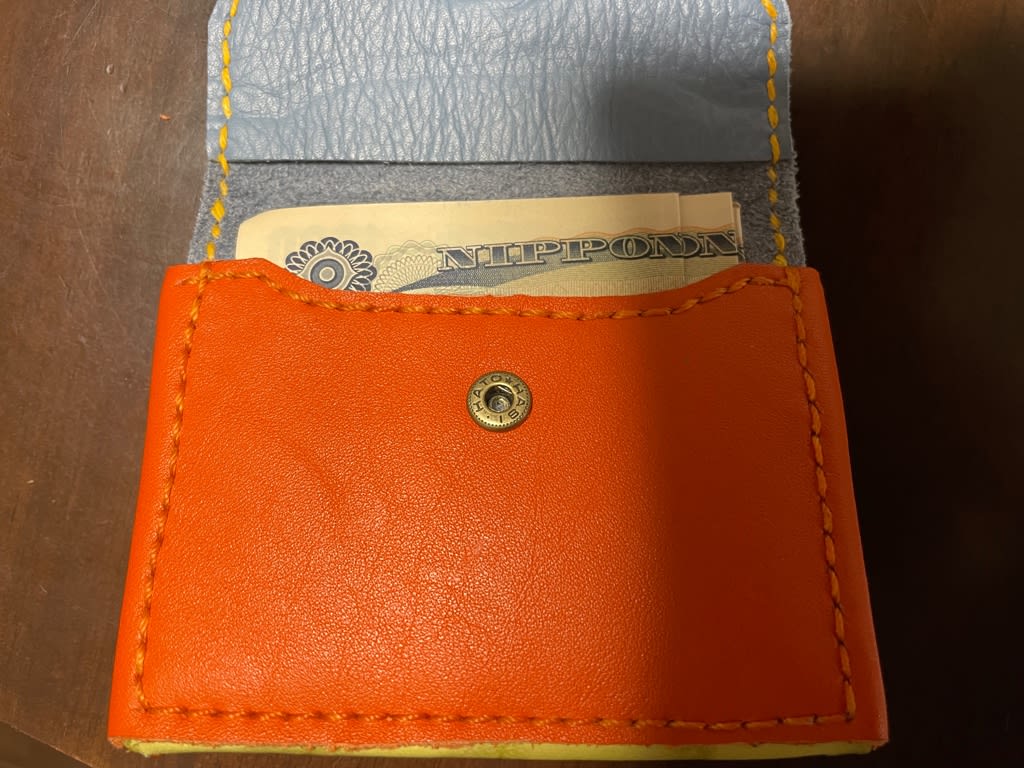

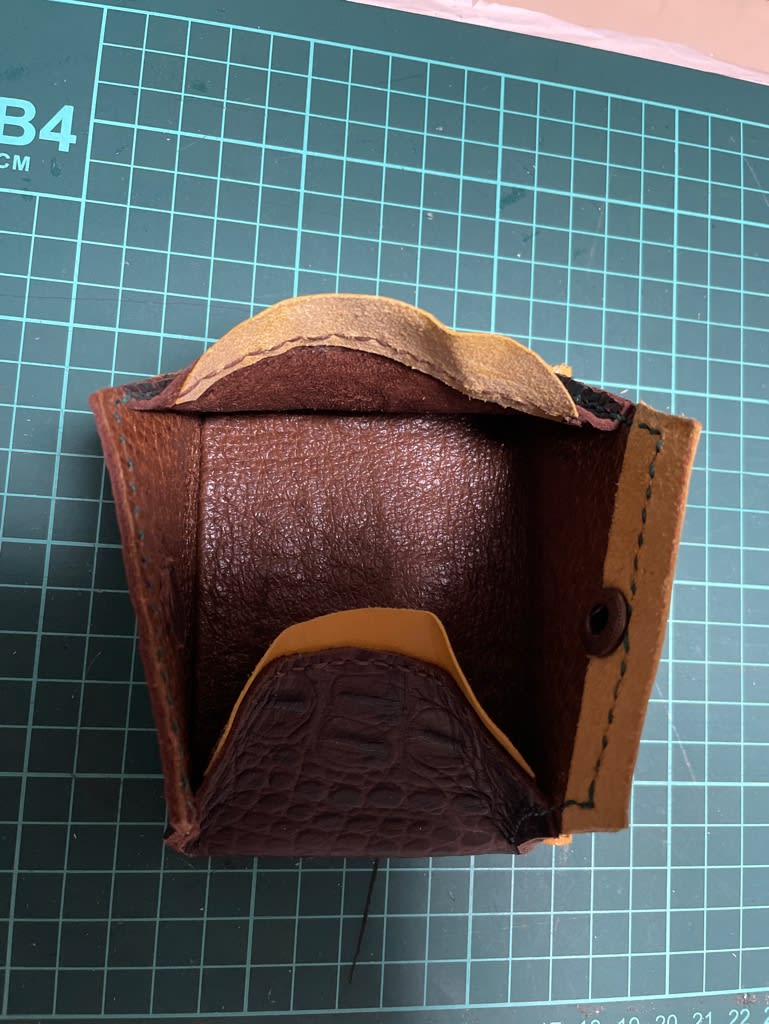































娘たちが、仲間をつのって石鎚山に行く計画を立てていました。 まだ車に乗れるというので私も連れて行ってもらうことにしました。去年と同じく、車は一緒でも別行動します。私は私なりのペースで行けるところまで行って、土小屋で待つもり。でも、できれば去年よりもうちょっと上まで行きたいなあ。
今年は山道に慣れない家族もいるということで、国道33号線から面河経由で行きました。 午前9時、大きな鳥居が見えてきました。 ああ、ここからが神の山なんだなあ、とちょっと厳かな気持ちになりました。

前を走っているバスは登山ツアーのみなさんで、これから先々でお会いすることになります。
今年は石鎚山の紅葉が早かったそうで、10月一週目には新聞やテレビでその様子が報じられていました。第3週ともなれば、紅葉はかなり下まで下りているはずーでしたが
まばらに赤い葉が見えているだけで、見えるはずの山頂は霧の中

あんなによい天気の日が続いたのに、よりによってこんな日に。前日まで行くかどうするか迷って、無理ならば散策とか山岳博物館見学とかに変更するということでやってきたのです。
ここまで来て、雨も降ってないときたら、登山決行です。
「雲にさわれるじゃん」一緒に来た男の子が目を輝かせて言いました。

土小屋の遙拝殿は、工事を終えてきれいになっていました。先ずここで入山の挨拶をして出発です。子どもたちがまだぐずぐずしている間に一足先に上り始めました。すぐに追いつかれましたけどね。
登山2回目となる今年は、あまり写真撮影で道草を食わず、一生懸命歩くことにしました。ただ、距離を書いた道しるべはきちんと写し、私の記録として残すことにしました。と言うわけで細々と書いておりますが、適当に読み飛ばしてください。
遙拝殿 10:10発
登山道の始まり 0 ㎞ 10:04
西日本最高峰への登山道とは思えないほど広々としてなだらかな道。去年、このあたりを散策するだけでもいいと思って孫たちについて来て、アサギマダラに惹かれてついつい上まで登ってしまったのでした。


1.1㎞地点 10:20 16分/1km
平地と同じくらいの速さでここまで来ました。さすがに山らしくなって、クマザサの茂みが広がってきました。



先週はすごい人だったそうですが、天候の崩れる予定だったこの日はさほどではありませんでした。 後から追いついた人に先に行ってもらい、自分のペースで歩きます。
1.6㎞地点 10:39 19分/500m
このあたりで、休憩している孫たちに追いつきました。また、ツアーの一行も休んでいました。私よりも先に出発したはずなので、かなりゆっくりしたペースだったようです。




2.1㎞地点 11.03 26分/500m
見覚えのある白骨林





2.6㎞地点 11:30 27分/500m 半分近く来ました。
赤い葉を探して写しました。というか、だんだん写真を撮るために立ち止まる回数が増えて・・・・写真を撮りながら息を整えつつ登るようになってきました。


3㎞地点 11:42 ここからトイレ休憩所まで1㎞
去年、ここから娘に電話したら、「ここからがきついよ」と言われ、とにかく休憩所までは行ってみようと決めてさらに登ったのでした。

3.1㎞地点 11:44 14分/500m
たしかに、ここまでは比較的楽だったのです。それが、急なアップダウンが繰り返し現れるようになりました。
上りを見てはうんざりし、下りを見てもまたうんざり。下ったら登らなくてはなりませんから。



3.6㎞地点 12:09 25分/500m 頂上まで1㎞
やはり500m登るのに25分もかかりました。
去年よりも土砂崩れの箇所が増えていて、がれきが道をふさいでいました。




西条市成就社側から来る道と、土小屋から来る道とが出会ったところに新しいトイレ休憩所があります。
4㎞地点 12:35 26分/400m 頂上まで0.6㎞ トイレ休憩所の下
ますますペースが落ちて、400m登るのに26分もかかってしまいました。やはりここまで来るのはしんどかった。

休憩所の下のわずかな平地は階段まで人て゛あふれていました。ツアーの皆さんが昼食を取っていたのです。そこへ上から下りてきた人の達成感あふれる声が加わってますますにぎやかになりました。どうやら、ここまでにした人と、山頂まで行った人とにわかれたようですね。自分の体力に合わせてコースは選べるようでしたけど、大変。私はまだまだツアーで登山する自信はありません。
うわあ、これは・・・・上へ行ってお昼にしたいけど、どうしよう。
あれ? こんなところで何してるの?
私が見つけたのは、大勢の人から離れて、なんとかお弁当を広げる場所を探している、ウマオとウマオパパでした。
上の方が広いのに?
上もいっぱいなんですよ。
なんで二人だけなの? トラオは?
みんな山頂に行ってます。ちょっとウマオの調子が悪かったもんで。
はあはあ、また例の? わたしは事情を察しました。そして3人で敷物を敷く場所を見つけて一緒に食べることにしました。
さあ、ここから登山はさらに苛酷な展開に














