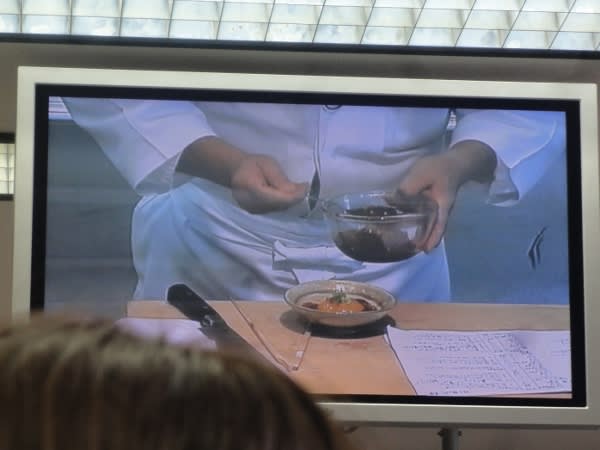さて、続いては、市の広報で見つけた「自然観察会」
市内のため池で鴨や植物の観察をするというのです。おお! こちらのため池にも鴨がいたのか。いつもは、松山市のため池や、東温市のため池をのぞいていたのですが、灯台もと暗しでした。
おもしろそう。けっきょくぶじこ一家も全員参加することにしました。赤ん坊はベビーカーに乗ってね。
しかし、こちらのため池は「兼久の大池」というだけあって、広かった

松山の池とちがって、鴨が豆粒のようにしか見えません。10倍の双眼鏡をお借りしました。
まずは池の畔でお話を聞いて・・・・・

あ! かわせみ!
いきなりの登場。 だれにとっても魅力的なこの鳥、しばらくはみんなこの鳥の動きに目を離せなくなりました。どこにいるかわかりますか?

30倍ズームのカメラではこれが限界。あとでこの場所を見ると白い糞がいっぱいでした。道のすぐそばなのに、きっとお気に入りの場所なんですね。
マガモの一群れ。なぜかこの一群は大勢の仲間からは離れています。

オスの頭の緑がきれいです。でもこの緑、見る場所によっては紫に見えるのです。光によって色が変わるそうです。
森の木の上にはアオサギ。カワセミがスズメくらいだとすると、ずいぶん大きな鳥だとあらためて思います。

空には猛禽類も飛んでいます。予想以上に多くの鳥がいることを知りました。
しばらく観察した後遊歩道へ

歩き出してすぐ見られたのは

大量のビナンカズラ。すごい。
一つ一つはこんなにきれいな実です。

道ばたにはいろいろな種類のドングリが。
クヌギ、アラカシ、マテバシイ、ツブジイ・・・ ぶじおJr.のエンジンがかかってきましたよ。そのうち参加していたこどもたちが一緒に遊び始めました。大きい子は小学四年生くらい、ぶじおJr.と同じくらいの女の子、男の子、最年少はうちの赤ん坊、八ヶ月。ほほえましい光景でした。
池ではかもが

おもしろい、一列になって泳いでいく。
でも、これにはわけがあってー
やまびこさ~ん やまびこさ~ん やまびこさ~ん
子どもたちの声に、かもがどんどん逃げていく姿だったのです。ついに小学生の男の子のお父さんが
「そろそろやめてもらえませんか」と子どもたちにお願いしていたそうです。
これらの水鳥の中にはオシドリも混じっていました。でもわたしにはさっぱり。思わず、「こんなにいる中でよく見つけられますねえ」とインストラクターの先生に言ってしまいました。
オシドリの姿は望遠鏡で確認できました。きれいでした。
頭上にはノスリが舞っていましたが、カメラに入るのはからすだけ。写すことはできませんでした。
帰り道は、子どもたちの冬イチゴ探しを手伝いながら。小学生のお兄ちゃんが、女の子に「あっちにいぱいあるから」と教えているのを見て、仲良しの兄妹だなあと思っていたら、まったくの他人だったらしいです。ぶじおJrにもとても優しくしてくれて、すてきな男の子でした。
さて、わたしの学習の成果
ヒドリガモ

望遠鏡で確認して、そのあたりを当てずっぽうで撮影したので、確信はないのですが、この鴨は頭が明るい茶色で目がまっかなのです。
頭が茶色の鴨はホシハジロがいますが、これは写ってなかったです。
この池に飛来する鴨は、
マガモ、カルガモ、ヒドリガモ、ホシハジロ、ヨシガモ
はあ~鴨もいろいろいるんですねえ。オシドリも鴨の仲間です。ほかにカワウもいました。
それから、この木

ミミズバイ。きれいな紫色の実がなっていました。
それからそれから、

アカネ。この根っこであのあかね色を染めます。茎が四角なのが特徴です。草木染めをするときは、場所を確認しておいて地上部が枯れてから根っこを掘り出すんだとか。
染色ではよく知られた植物ですが、まさかこんな道ばたに見られるとは。感激でした。
こうして二時間があっという間に過ぎ、参加者の皆さんとすこしお話しして分かれました。最後の話で盛り上がったのは・・・・なぜかぶじこのすきなイモムシ。
市内のため池で鴨や植物の観察をするというのです。おお! こちらのため池にも鴨がいたのか。いつもは、松山市のため池や、東温市のため池をのぞいていたのですが、灯台もと暗しでした。
おもしろそう。けっきょくぶじこ一家も全員参加することにしました。赤ん坊はベビーカーに乗ってね。
しかし、こちらのため池は「兼久の大池」というだけあって、広かった


松山の池とちがって、鴨が豆粒のようにしか見えません。10倍の双眼鏡をお借りしました。
まずは池の畔でお話を聞いて・・・・・

あ! かわせみ!
いきなりの登場。 だれにとっても魅力的なこの鳥、しばらくはみんなこの鳥の動きに目を離せなくなりました。どこにいるかわかりますか?

30倍ズームのカメラではこれが限界。あとでこの場所を見ると白い糞がいっぱいでした。道のすぐそばなのに、きっとお気に入りの場所なんですね。
マガモの一群れ。なぜかこの一群は大勢の仲間からは離れています。

オスの頭の緑がきれいです。でもこの緑、見る場所によっては紫に見えるのです。光によって色が変わるそうです。
森の木の上にはアオサギ。カワセミがスズメくらいだとすると、ずいぶん大きな鳥だとあらためて思います。

空には猛禽類も飛んでいます。予想以上に多くの鳥がいることを知りました。
しばらく観察した後遊歩道へ

歩き出してすぐ見られたのは

大量のビナンカズラ。すごい。
一つ一つはこんなにきれいな実です。

道ばたにはいろいろな種類のドングリが。
クヌギ、アラカシ、マテバシイ、ツブジイ・・・ ぶじおJr.のエンジンがかかってきましたよ。そのうち参加していたこどもたちが一緒に遊び始めました。大きい子は小学四年生くらい、ぶじおJr.と同じくらいの女の子、男の子、最年少はうちの赤ん坊、八ヶ月。ほほえましい光景でした。
池ではかもが

おもしろい、一列になって泳いでいく。
でも、これにはわけがあってー
やまびこさ~ん やまびこさ~ん やまびこさ~ん
子どもたちの声に、かもがどんどん逃げていく姿だったのです。ついに小学生の男の子のお父さんが
「そろそろやめてもらえませんか」と子どもたちにお願いしていたそうです。
これらの水鳥の中にはオシドリも混じっていました。でもわたしにはさっぱり。思わず、「こんなにいる中でよく見つけられますねえ」とインストラクターの先生に言ってしまいました。
オシドリの姿は望遠鏡で確認できました。きれいでした。
頭上にはノスリが舞っていましたが、カメラに入るのはからすだけ。写すことはできませんでした。
帰り道は、子どもたちの冬イチゴ探しを手伝いながら。小学生のお兄ちゃんが、女の子に「あっちにいぱいあるから」と教えているのを見て、仲良しの兄妹だなあと思っていたら、まったくの他人だったらしいです。ぶじおJrにもとても優しくしてくれて、すてきな男の子でした。
さて、わたしの学習の成果
ヒドリガモ

望遠鏡で確認して、そのあたりを当てずっぽうで撮影したので、確信はないのですが、この鴨は頭が明るい茶色で目がまっかなのです。
頭が茶色の鴨はホシハジロがいますが、これは写ってなかったです。
この池に飛来する鴨は、
マガモ、カルガモ、ヒドリガモ、ホシハジロ、ヨシガモ
はあ~鴨もいろいろいるんですねえ。オシドリも鴨の仲間です。ほかにカワウもいました。
それから、この木

ミミズバイ。きれいな紫色の実がなっていました。
それからそれから、

アカネ。この根っこであのあかね色を染めます。茎が四角なのが特徴です。草木染めをするときは、場所を確認しておいて地上部が枯れてから根っこを掘り出すんだとか。
染色ではよく知られた植物ですが、まさかこんな道ばたに見られるとは。感激でした。
こうして二時間があっという間に過ぎ、参加者の皆さんとすこしお話しして分かれました。最後の話で盛り上がったのは・・・・なぜかぶじこのすきなイモムシ。