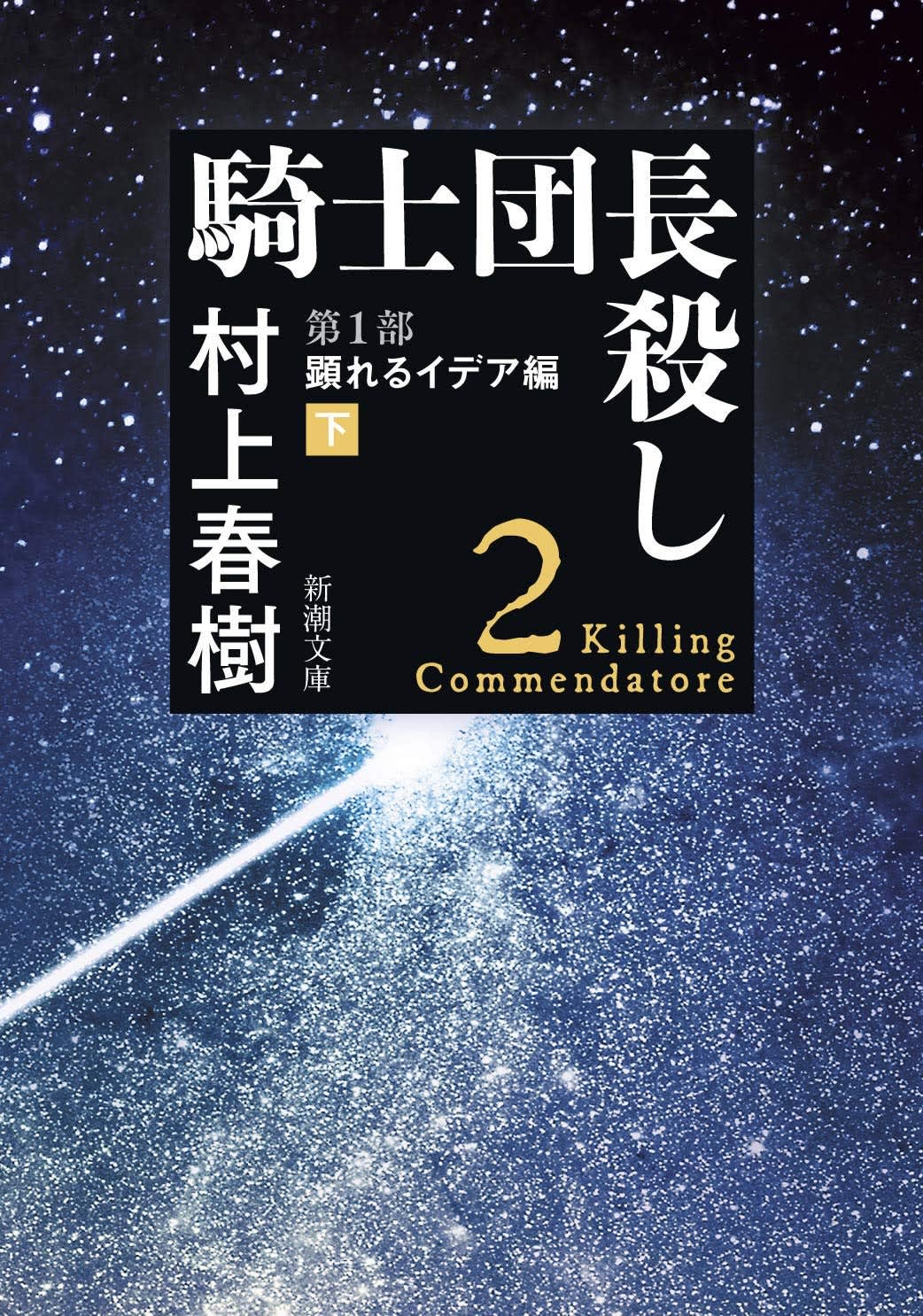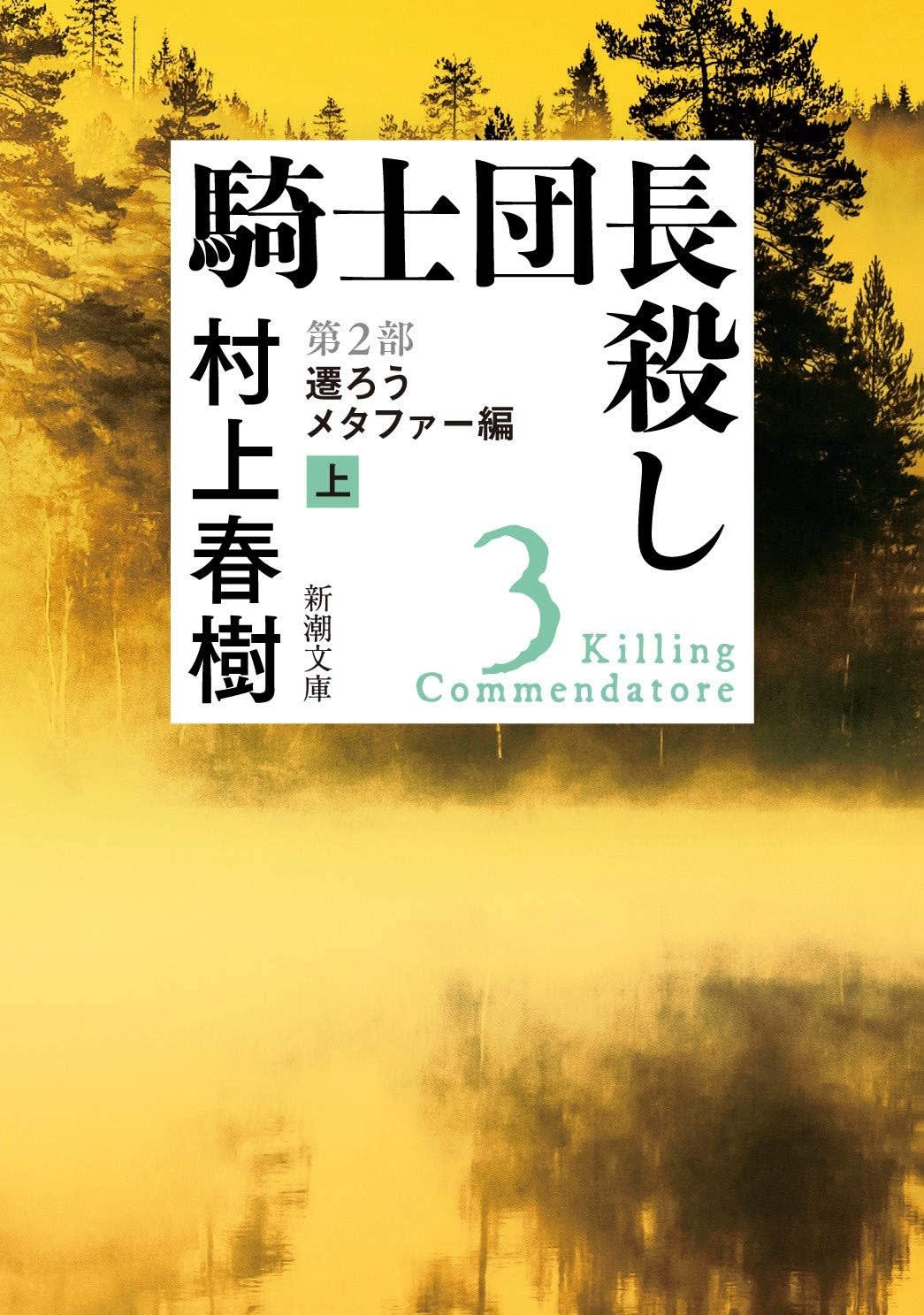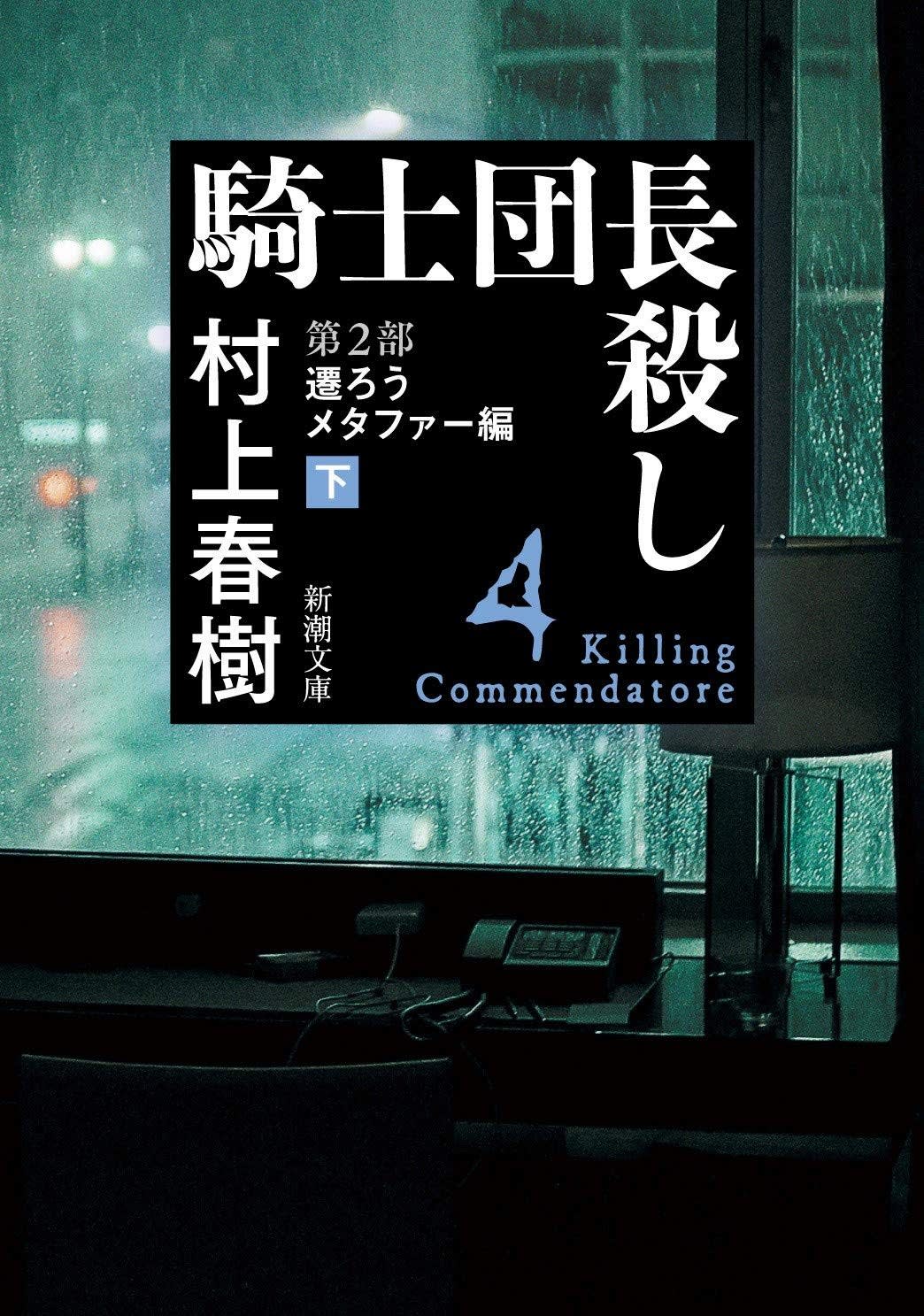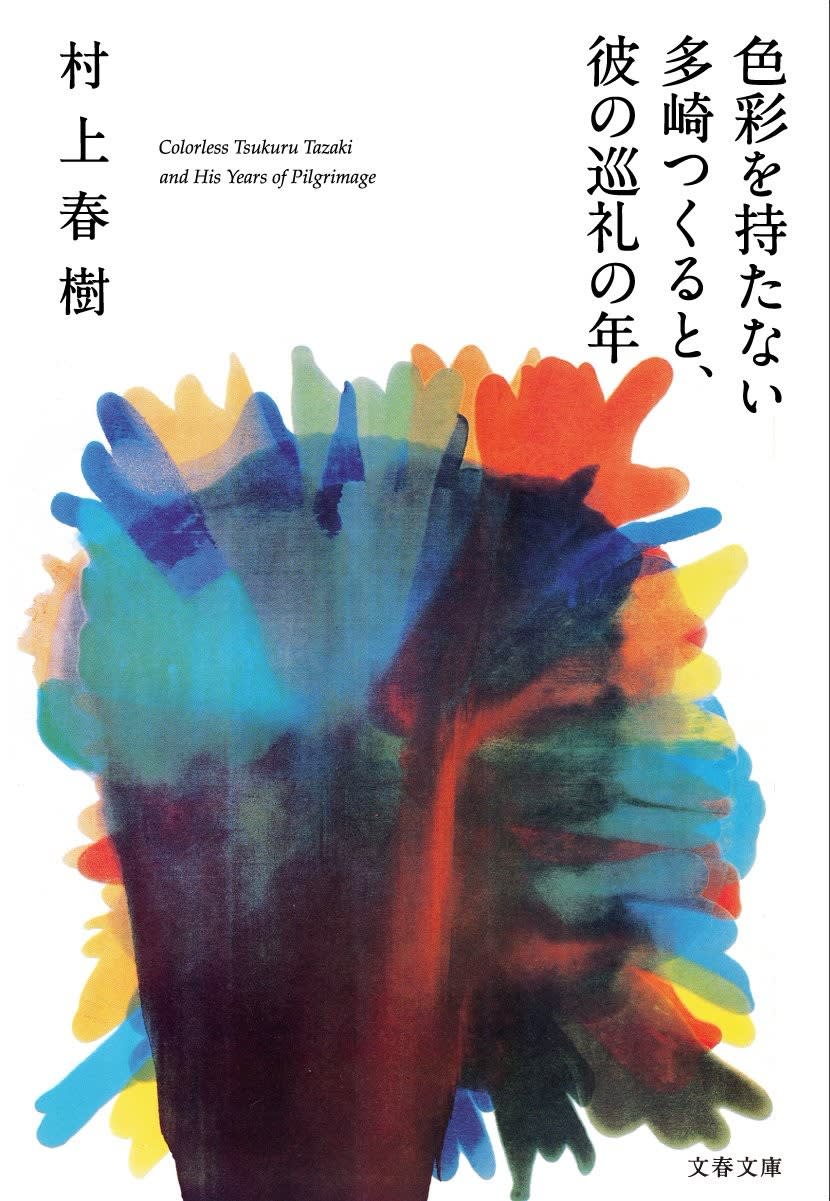カモメが仲間たちから抜け出して、飛ぶことの技術を高めることに喜びを見い出し、同じ目的を持つ者たちで師匠と弟子のような関係ができて、瞬間移動のような神秘的な境地にまで到達する物語である。子どもでも読めるようなとても平易な文章と短さにもかかわらず、難しい小説であった。どこに感動すればいいのか、どう解釈すればいいのかがわからないのである。大衆化・形骸化した一般社会と、個人の自由と成長の対立を描いているようにも見えるが、単純にそれだけではないようにも思える。かんたんには見えない深い意味が隠されているようにも思えるのだが、それが何なのかがわからない。
私は25年くらい前に人から贈られて読んだ「ONE」という小説に、そうとうな感銘を受けたことがあった。その著者が、「かもめのジョナサン」の著者でもあるリチャード・バックであった。心がどうにかしてしまったときに読んだら、大きな気づきをもたらしてくれて、救われたような気持にしてくれた本であった。「かもめのジョナサン」もそういうタイプの小説なのだろうか?本書は、1970年に米国で初版が出版され、最初はヒッピーの間で読まれていたのが、一般大衆、そして世界に広まり、2014年時点で世界で4000万部売れたという。日本でも270万部を超えている。そして、2014年に、新たに第4章が加わった完成版が出版された。初版も完成版も、日本では五木寛之氏が訳(創訳)している。その五木寛之氏はあとがきにおいて、心理学用語のゾーン、仏教者のブッダや法然などを持ち出して、なんとか本書の意味を解釈しようとしているが、不思議な物語だと言っている。
1970年は、米国では泥沼のベトナム戦争の最中であり、一方では1950年代から広がってきた禅ブームという精神性への回帰や、ヒッピームーブメント、フォーク・ロックなどのカウンターカルチャーの流行もあった。そのころは、みな現状にいい加減うんざりしていて、今いる場所の呪縛から抜け出して自由になりたかったのではないだろうか。そんなときに「かもめのジョナサン」は、救いを見せてくれたのかもしれない。
2014年に加わった第4章では、かもめの師匠となったのち消えていったジョナサンが神格化され、飛ぶことの修業は軽視され、ジョナサンの伝説を崇める儀式へと形骸化していくというどんでん返しが付け加えられた。イリュージョン(=かもめの一般社会)から抜け出してせっかく自由になったのに、見えてきたのはまた別のイリュージョン(=形ばかりの儀式)だったというストーリーだ。1969年に発表されたヴェルヴェット・アンダーグラウンドの「I'm set free」という曲の歌詞を連想させてくれた。