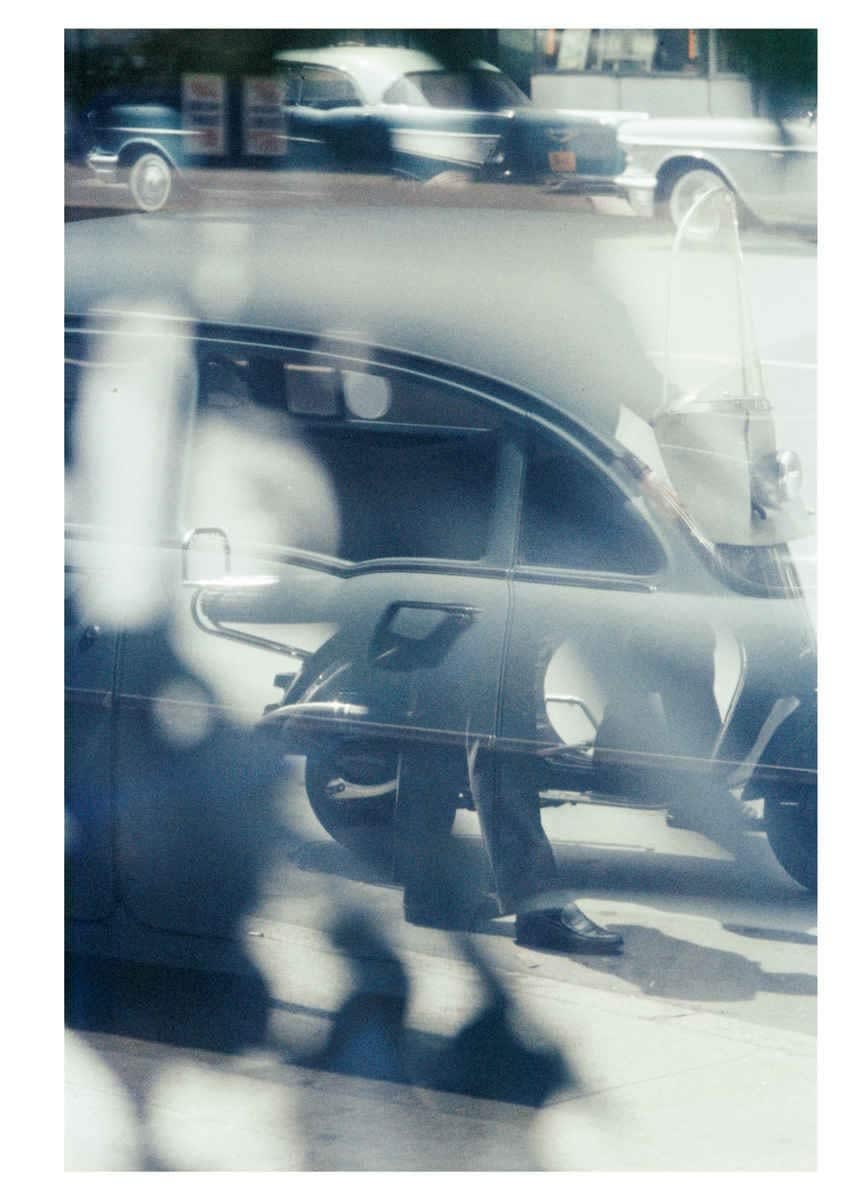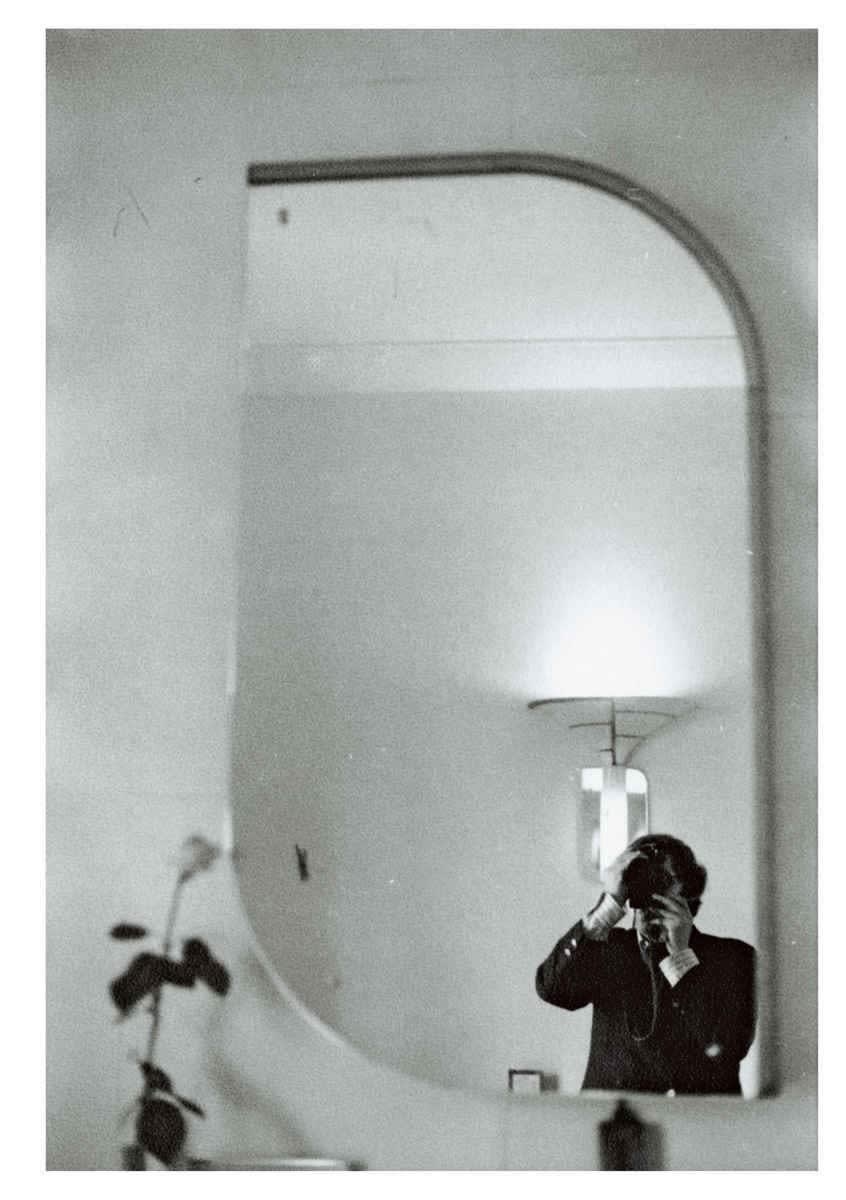不器用にしか生きていけない男たちの心のよりどころ、高倉健(本名:小田剛一)。2014年11月10日に永眠して、もうすぐ6年になるが、お墓参りしたくても正式なお墓がないし、住んでいた家ももう残っていない。最後の17年間をともに過ごした養女が、骨も遺品も遺産もすべて独り占めしてしまったといって世間からずいぶん叩かれた。その養女、小田貴月(おだたか)さんは何を考えているのかずっと知りたいと思っていたところ、ついに本書を執筆・出版した。
この二人が男女の関係にあったのだとしたら、一般的に見たらずいぶん不思議な関係だったのだなあというのが感想だ。その17年間の間柄は、一緒に出掛けることもなく、会うのは自宅の中だけの、世間から完全に隔離されたひっそりとしたものだった。そして、関係がまったく対等でないのだ。小田貴月さんは高倉の忠実な家政婦兼記録者になりきっている。そういう関係であることをお互いに認め合っていたようにも見える。
これまでに、あちこちで書かれてきたように、高倉は生涯に一度だけ歌手の江利チエミさんと結婚しているが、それは対等な関係だった。しかし、夫婦生活は苦難に満ちたものだった。チエミさんの義姉を名乗る吉田よし子という女が家政婦になり、疫病神のように悪行の限りを尽くした。家に火をつけて全焼させる、財産を横領する、高倉が浮気しているとチエミさんに吹き込んで離婚させる。それが嘘だったとわかり、チエミさんは高倉に謝って再婚を願い出るが、高倉は半年待ってくれと言う。チエミさんはその間にアルコール依存症になってしまい、ほとんど自死に近いような死に方をしたのだった。その後、高倉は亡くなるまで再婚することはなかったが、その理由としてはチエミさんへの思いもあっただろうし、結婚という形に心底懲りてしまったということもあったのかもしれない。
だから、世間から見たらずいぶんと変わっているのだが、心から信用できる、そして女性としても愛する小田貴月さんという人が現れて身の回りの世話までしてくれるようになったことは、高倉にとってはとても幸せなことだったのだろうなと思った。高倉は亡くなる2カ月前にこう書き遺したー「僕の人生で一番嬉しかったのは貴と出逢ったこと 小田剛一(p.330)」。そして、亡くなる2年くらい前に、「僕のこと、書き残してね。僕のこと一番知ってるの、貴だから(p.8)」と高倉から言われた宿題を果たすために、膨大な資料と記憶をもとに書かれたのが本書である。内容は、高倉の映画人生、生活で起きたこと、二人の間に起きたことの記録である。
小田貴月さんも最初は不安でいっぱいだったようでー「高倉への一歩は、地図のない山に入山記録を残さず、単独登攀に臨むようなもの。迷路あり、行き止まりあり、判断を誤れば、遭難、滑落するかもしれない大きな決断でした(p.28)」と述べているが、覚悟を決めた後はー「”目立たずに過ごしたい”という希望に副い、高倉とは国内外の旅はもちろん、一緒に外食すらしたことはありませんでした(p.28)」そして、高倉の食生活の偏りを心配して、「食事のことで、私でお役に立てることはないでしょうか(p.66)」と尋ねたことをきっかけに、自ら望んで家での料理係となった。高倉が亡くなった後、家を処分したことについては、「高倉にとって、家は一代、誰にも見られたくない聖域でした。その思いをうけ、高倉の旅立ちとともに封印しました(p.57)」と、書いている。
文化大革命後の1978年ごろから中国で日本の映画が公開されるようになり、高倉が主演の「君よ憤怒の河を渉れ(1976年)」は中国全土で10億人以上が観たとも伝えられている。それ以降、高倉は中国で圧倒的に支持されるようになり、「あなたは、高倉健の様だ」と言われることは、男性への最上の褒め言葉で、女性にとっては理想の結婚相手となった。
日本生命/ロングランのCM(1984~1989年)に出演して、「自分、不器用ですから・・・・(どうか幸せで)」というコピーがきっかけで、高倉健=不器用というイメージが固まった。それに対して高倉は「『不器用ですから』というのは、コマーシャルでライターが考えた文句。とっても器用に生きてきたつもりです」とか「自分じゃ、全然不器用って思ってないけど」と、否定していたという。
この本を読んだことをきっかけに、テレビから録画したままだった高倉の映画をいくつか見た。「新幹線大爆破(1975年)」「八甲田山(1977年)」「遥かなる山の呼び声(1980年)」「単騎、千里を走る。(2006年)」―どれを見ても、ぶっきらぼうで不愛想だけれど心に人への強い思いをかかえている健さんが出てくる。もう他に、こんなタイプの映画スターも、中国人が憧れ尊敬する日本人も、出てこないかもしれない。稀有な存在だった。
健さんが亡くなったときの私のコメントはこちらです。