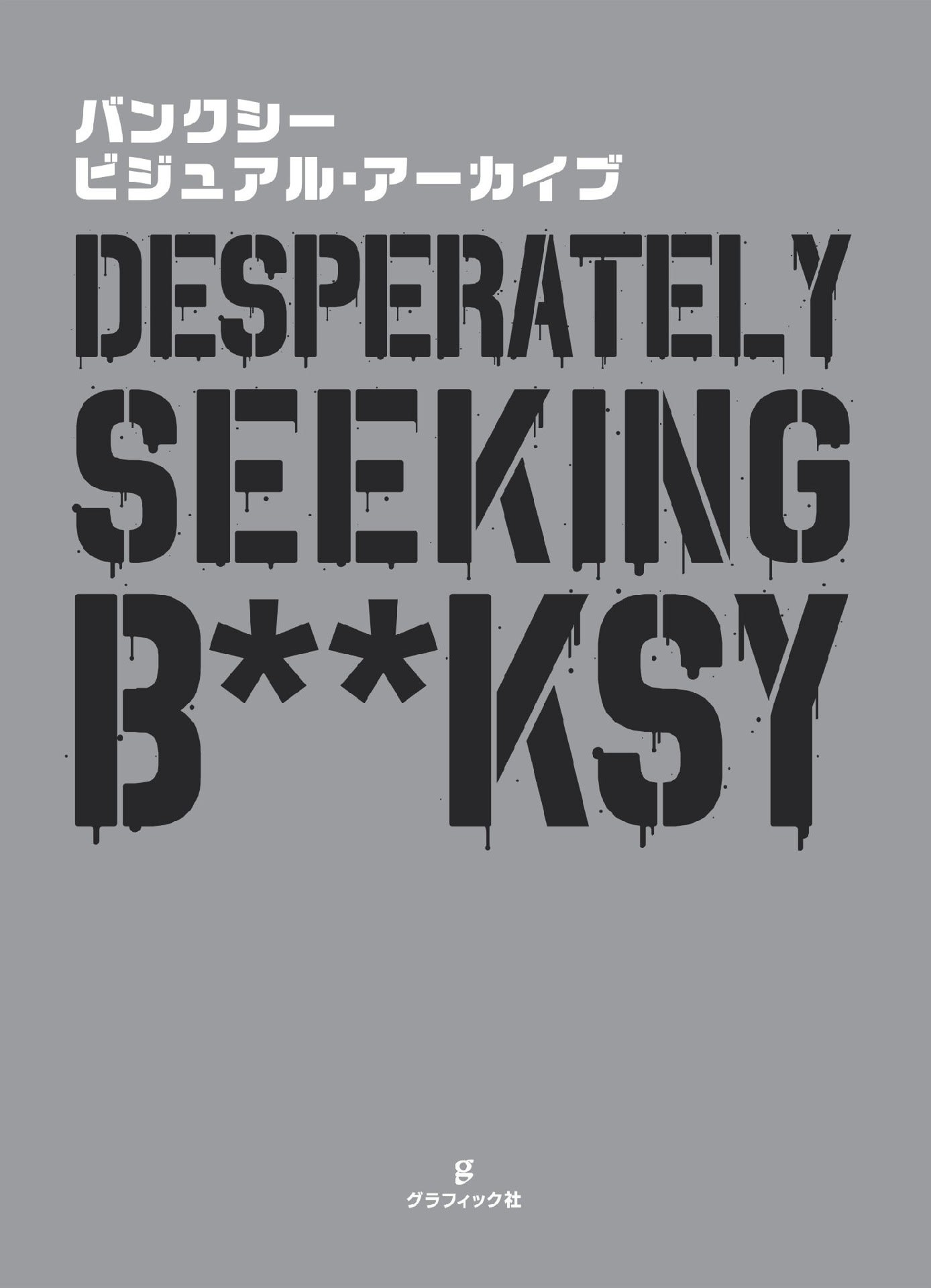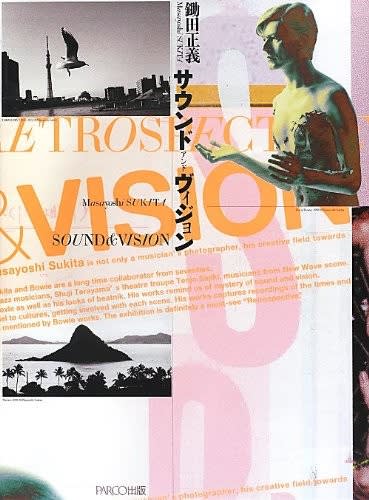ミュージック・マガジンの創刊50周年記念号である。
音楽通向けのワールド・ポピュラー・ミュージック総覧的な本誌は、洋楽ロック好きの私には少し指向性が違うので、これまではあまり手に取ることがなかった音楽雑誌なのだが、特集「50年の邦楽アルバム・ベスト100」と特集「細野晴臣」に惹かれて購入した。復刻された創刊号も同封されている。
特集「50年の邦楽アルバム・ベスト100」では、1969年から2018年までの「50年の邦楽」、ポップスの枠にくくられるものすべてが選出対象となり、50人の選者から選ばれたものを集計して選出された。1位から10位までを下記に抜粋する。
1.はっぴいえんど「風街ろまん」
2.シュガー・ベイブ「SONGS」
3.大滝詠一「ロング・バケイション」
4.ゆらゆら帝国「空洞です」
5.イエロー・マジック・オーケストラ「ソリッド・ステイト・サバイバー」
6.フィッシュマンズ「空中キャンプ」
7.ザ・ブルー・ハーツ「THE BLUE HEARTS」
8.細野晴臣「HOSONO HOUSE」
9.荒井由実「ひこうき雲」
10.サディスティック・ミカ・バンド「黒船」
あまりよい邦楽聞きではなかった私でも、10位までのうち5枚はCDを持っていた。だから、ここで選ばれているアルバム群はとても順当だと思うと同時に、未知の世界-とくに、ゆらゆら帝国、フィッシュマンズ-も残されていて老後の楽しみができてよかった。11位以降はさらに未知の世界が大きく広がっている。どれだけ売れたかというよりは、全体的に音楽通のために選ばれたベスト100という趣である。それから、10位までで、少なくとも5枚は細野晴臣が関わっているアルバムである。まさに、この50年の日本のポピュラー・ミュージックを一人で作ってきた人といっても過言ではないだろう。
特集「細野晴臣」では、デビューして今年で50周年となる細野晴臣の1973年の作品「HOSONO HOUSE」とそのリメイク版として今年リリースされた「HOCHONO HOUSE」を中心に、この50年についてインタビューが行われている。この特集に14ページを割いているが、もっと読みたかった。
ニューミュージック・マガジンという名前だった創刊号では、当時の編集長だった中村とうようをはじめ、音楽評論家たちの評論やエッセーが載っているが、寺山修司の「対話としての歌の役割を考えよう」というインタビューが4ページにわたって載っていて、興味深かった。