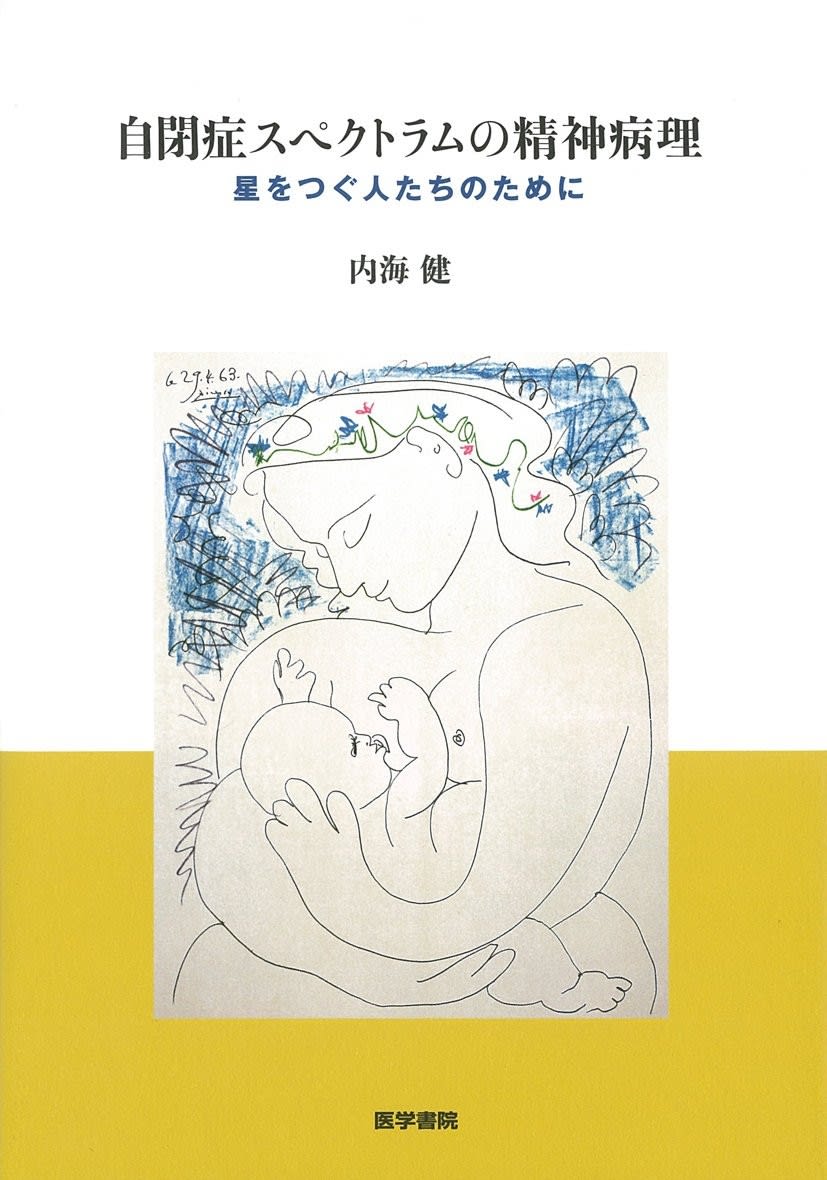
自閉症スペクトラム(ASD)の人の心の構造はどのようになっているのか、これまでの自閉症研究者たちの説やASD当事者たちの自白・体験談などを参照しながら、著者独自の見解をまじえ、やや哲学的に論じた本である。ASD者を対象とすることのある医師向けの本ではあるが、ASDの当事者が読んでも自己理解のためにそうとう得るものがあると思われた。ここで出てくる最も重要なキーワードは「志向性」である。一言で言えば、ASD者の最大の特徴は、他者からの「志向性」をうまく受け止められないことにより、自己の形成が十分でないこと。そして、エンパシー(志向的な共感)が発達していなくて、シンパシー(本能的な共感)で反応する。言語は身体で覚えるのではなく、頭で覚えたスキルとして使っている。そうなると、ASD者の心の構造は定型発達者とはずいぶんと異なっているということになる。本のタイトルにある「星をつぐひと」とは、あたかも異星人であるがごとく苦労を重ねてこの星に棲む者という意味である。
ASDの特徴として、「コミュニケーション能力や社会性の低さ、こだわりの強さ」などが一般的によく言われているところであるが、そこからさらに深いところに入っていって論じている本書のポイントを記したい。
・ASDを理解する説明である「心の理論」障害仮説はまちがっているというところから、議論がはじまる。「心の理論」は推論によって解ける「サリーーアン問題」というテストでよく知られている。幼児がこの問題を解けなければ、ASDの可能性が疑われるのだが、人間はそんなやり方で他者を理解するのではない。「心の理論」においては、他者のこころは推論するものとしているが、著者の考えでは、それは直感されるものであるという。ASD者は、他者の心があることを事後的に推論し、心を読むためにはもっぱら推論するのだという。
・「志向性」という概念は、中世に起源をもつが、19世紀にフランツ・ブレンターノによって改めて用いられ、その後、フッサールやヴィトゲンシュタインらに受け継がれて現代思想における現象学や言語学領域のキーワードの一つになっている。人が考えるときには、何かを考え、喜ぶときには、何かを喜ぶ、心的現象はつねに「何か」を対象として持つ。「志向性」とは、対象にかかわり、対象に向かうことであり、「こころ」にはあって「もの」にはない。われわれが他者を直感するのではなく、他者のもつ異質性strangenessのほうが、われわれに飛び込んでくる。その異質性の源泉が、まさに他者のもつ「志向性」であり、志向性は人間のこころに固有のものである。
・自己は他者からやってくる志向性により触発されて生成する。他者のしるした痕跡〈Φ〉が、自己の最も奥底に存在する。この自己の起源を自己自身は知らないし、自己の経験を越えたものである。ASDではこのΦが未形成にとどまる。
・ASDには想像力の障害がある。それは、経験が目の前にあるもので飽和してしまい、余白がないことによる。体験に余白がなければ、想像力も立ち上がらない。母に怒られた子どもは母の怒りで飽和してしまう。目の前の母と普段の母がつながらない。想像力の障害のため、ASD者は他者が知らなかったり間違えたりすることがあるのを理解できないことがある。
・「定型」の心の発達においては、こちらには「私」がいて、向う側には「対象」がある。対象と私とは別の系であるが、つじつまが合うようになっている。一方、ASDでは「私」と「対象」が連続している。こうした地続きの世界では、目の前のことがすべてであり、一つのピースが欠けたり、配置が変わることは、カタストロフを引き起こす。世界全体へと波及するカタストロフへの恐怖があるため、同じものの与える安心感や反復のリズムに固着してしまうことになる。
・本能的、地続き的、「こころ」を経ないで成立する共感をシンパシー、「心の理論」を介する志向的な共感をエンパシーと呼ぶ。定型発達では、ひとみしり以降、エンパシーがシンパシーに取って代わり、シンパシーは傍流に押しやられる。一方、少なくとも一部のASDでは、長じてもシンパシー能力が保たれる。ASD者は、他者の抱える不安や痛みは、直接感じとることができたりする。一方、「こころ」を前提とした感情である、悪意、善意、親切、嫉妬、やっかみ、ふてくされ、不機嫌、当てつけ、皮肉、媚びつらいなどは、さっぱりわからなくなる。ASD者は、直感、本能的にわかるべきことを、推論、知性で代償しなければならない。そもそも、定型者も、そこにある暗黙のルールが何であるか知っているわけではなく、知っているかのようにふるまっているのだ。
・ASDには、「被影響性」、つまり染まりやすさの問題がある。相手の言葉を真に受けてしまう。その要因の一つに、デカップリングする能力の問題がある。相手の言うことは矛盾に満ちているが、それを話半分に聞き流すことで相手からの影響を和らげることができるようになるのが、デカップリングである。ASDでは、それがうまくできない。一般にASD者は、自分自身についてのよい語り手であるより、よい書き手である。語るよりも書いているときの方が、自分との距離ができるからだろう。
・他者の志向性(みつめる、呼びかける、触れる)によって触発されたしるし(痕跡)がΦであるが、自己はこのΦを中心にして構造化される。そして、Φには認知行動特性にかかわる二つの機能がある。一つは、事象を経験として束ねる機能である。もう一つは、文脈からデカップリングする機能、つまり、いまここの状況から離脱して俯瞰してみる機能である。ASDにとっての世界は、相対化できずに現前にはりついている。いま目の前にあることだけで、経験が飽和してしまう。
・ASDでは言語が身体に沁み込んでいない。むしろ道具のように、無骨に使われている。ASDの世界は、母語によってフォーマット化されておらず、言語はアプリのようにインストールされる。彼らはあたかも外国語のように母語を学んでいく。日常的なコミュニケーションの局面では、ASDの言葉は不自然であり、拙劣である。ことばのやりとりの中で、自分のことばを、そして他人のことばを確認できないために、ASD者は会話の中で、いつも遅れてしまう。遅れを取らないためには、あらかじめいうことを準備してこなければならない。ただ、それは一方的なものであり、本人にしてもただ言っただけになる。だが、情報の伝達というところから離れてみると、彼らは、定型者には失われた感性的なことばのきらめきを示すことがある。たとえばそれは韻律であり、歌であり、そして詩である。そこでは伝達は問題となっていない。これもシンパシーの回路である。
・乳児の無垢なほほえみを見れば、身体の内側から自然に笑みが溢れてくる。泣き声を聞けば、放ってはおけない。ここまでは、直感的、感覚的レベルでのキャッチである。おそらく動物は、このシンパシーの水準だけで十分に機能できる。しかし人間において、乳児の泣き声を聞いた母は、「おなかがすいたのかしら?」「おむつがぬれたのだろうか?」などと、ことばの水準で対応する。乳児は母とのシンパシーの回路の中にあると同時に、母の中ではエンパシーが作動している。
・日常において、知覚は感覚を統御している。その逆はない。感覚における変化や差異や強度の波立ちは、言語的に束ねられている。おそらく、ASDにおいてしばしばみられる感覚過敏は、感覚における沸き立つざわめきを、言語をとおして知覚化することの困難にある。
・ASD者は孤独に強いようにみえるが、かならずしもそうとはかぎらない。いったん自分が孤立していたことを意識すると、しばしば孤独感にさいなまれることになる。それゆえASD者の多くは、人とのかかわりを希求している。だが、どう関係を結んでよいか見当もつかない。不器用に相手の感情や意図を読まなければならぬはめになる。ASDは、他者というものの存在に気づくことによって、自己にめざめる。他者は、最終的には自分と同等の等身大の存在に落ち着くのだが、それまでに様々な様相を呈する。もっともポピュラーな現れ方は、対人緊張、社交不安障害(SAD)である。自他未分という世界に生きていた彼らは、新たにできた自分を隠す場所をもたないのだ。ASDにおいて頻度の高い二次障害は、抑うつと並んでSADであるという。
・ASDと、統合失調症や境界性パーソナリティ障害との鑑別診断はむずかしくはない。統合失調症とASDとでは、自閉という用語が共通しているが、対極にあるといえる。統合失調症は定型発達のベースの上に起こる病である。ASDは発達の異形であり、大きな切断なく経過する。境界性パーソナリティ障害の多くは誤診である。本来の境界性パーソナリティ障害は、独特の不安定性や相手への操作性などによって特徴づけられる。
・最後に、ASD者に対する臨床的な対応が述べられている。ASDは発達の一つのバリアントであり、それ自体疾病ではないというスタンスが述べられる。固有の世界を持っていることを、まずは率直に肯定することからすべてが始まるとしている。「治療」や「支援」の目標は、定型への矯正ではない。突き当たった壁を迂回したり、袋小路から引き返したりしながら、彼らのもっている資質が、それを束縛しているものから解放され、開花してゆくことである。他者のことばに当意即妙に応じることは、ASD者にとってはすぐには克服が難しい課題である。当座は無理をせず、遠慮せずに聞き返したり反芻したりしながら、ゆっくりでも自分のペースで考えたほうがよい。ASD者は、他者のことばだけでなく、自分の思考に対しても距離が取れない傾向がある。ASD者は、スピーチは不得意だが、書くことに長けていることがある。書くことが、距離を作るのに役立つ。ASD者の多くは人に関心をもっているが、向かない対人業務で不適応を起こす場合は無理にしない。
私自身の感想を述べたい。本書はこうして、経験的、思索的に、ASDの心の構造を明らかにしてみせた。そして、もし私がASD者だとすると、自分の実感に近いことが書かれていたと思う。しかし、ここに書かれている論考の多くは哲学の領域であり、科学的に見たらまだ仮説の段階なのだろう。志向性、Φ、シンパシー、エンパシーなどを含めたこれらの仮説を、心理学や脳科学の科学的方法論によってどこまで実証されるのか興味が持たれる。









