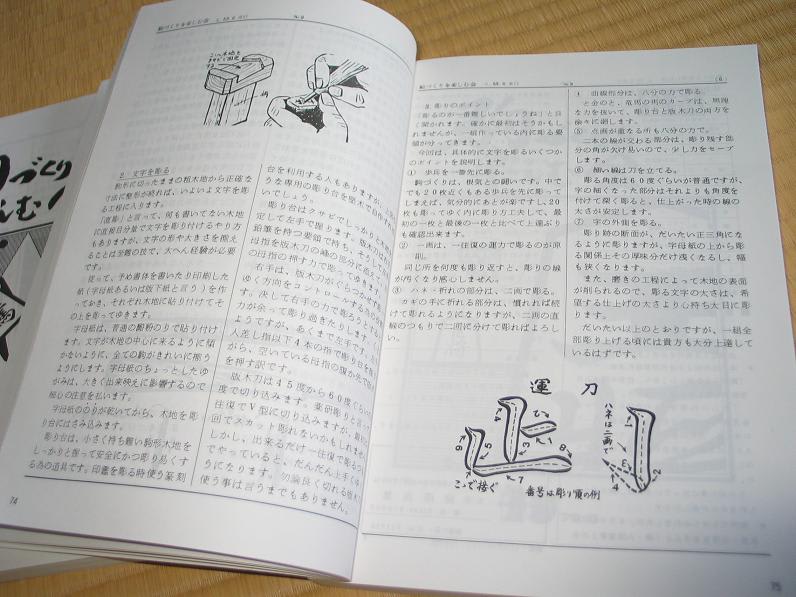1月23日(金)、曇。
朝から「源兵衛清安」を彫り始めました。彫り終わるのは数日先です。
材は薩摩つげ孔雀杢です。
会報11号。発行日は昭和53年10月20日です。
第3回作品展が、正月に池袋・三越百貨店で開催することが決まり、皆さんに応募を呼びかけています。
会場は、新春将棋まつりの一部を使っての展示です。このときは確か関屋喜代作先生が理事で、プロデュースされていたと記憶しています。
この頃、東京の将棋連盟にはよく行きました。1ヶ月に1回か2回は仕事で上京していましたから、用事があると、午前中とか夕方に出向く訳です。
当時は将棋会館の5階が泊まれるようになっていて、空いていると一般客もOKだったので、ここにもよく泊りました。
丁度、関西将棋会館の建設運動が始まり、大山名人が旗振り役で、永井近代将棋社社長が秘書役。それに荻山さんという方も大山名人の特別秘書をされていましたので、大山名人へのお願い事などは荻山さんを通じる事もありました。
駒づくりを楽しむ会としても、僅かながらですが、会館建設の寄付金を集めて協力しました。
会報に戻って、
4ページには竹内六郎さんからの手紙の一部を載せさ手います。
竹内六郎さんは、竹内淇洲翁のご子息です。
小生が駒作りを始めた頃、作家の倉島竹二郎さんが名人戦の観戦記の中で、「六郎さんから頂いた淇洲翁が書いた将棋の漢詩の軸を大切にしている」ことを書かれているのを読みました。
「駒づくりの勉強のため、お持ちの駒を拝見させて欲しい」と、倉島さんの鎌倉・腰越のお宅を訪ねたのがこの少し前でした。いろいろな駒を見て、駒づくりに生かしたいという思いでしたし、駒と一緒に淇洲翁の軸も拝見しました。六郎さんの住所を教えていただいたのはこのときです。
早速、六郎さんに手紙を出して、何通か頂いた返事の一部を載せさせていただいたわけです。
六郎さんは確か三菱化学に勤められていて、この頃は既に定年退職なさっていたと思います。
初めてお会いしたのは東京での作品展会場だったか、川崎のお宅だったかは忘れましたが、淇洲著「将棋漫話」や、正真正銘の「淇洲」字母紙も頂きました。
手紙は5~6回頂きました。貴重な事が記されていますので、資料として大切に保管しています。
六郎さんは、15年位前に他界されました。
なお、山形県酒田市に淇洲翁の弟子・佐藤公太郎さんを訪ねたのは、六郎さんの紹介で、この手紙をいただいた少し前です。公太郎さんが預けている竹内家家宝の真正の「淇洲駒」は、このとき本間美術館で拝見することが出来ました。
今から30年以上前のことです。
今日はここまで。おやすみなさい。
朝から「源兵衛清安」を彫り始めました。彫り終わるのは数日先です。
材は薩摩つげ孔雀杢です。
会報11号。発行日は昭和53年10月20日です。
第3回作品展が、正月に池袋・三越百貨店で開催することが決まり、皆さんに応募を呼びかけています。
会場は、新春将棋まつりの一部を使っての展示です。このときは確か関屋喜代作先生が理事で、プロデュースされていたと記憶しています。
この頃、東京の将棋連盟にはよく行きました。1ヶ月に1回か2回は仕事で上京していましたから、用事があると、午前中とか夕方に出向く訳です。
当時は将棋会館の5階が泊まれるようになっていて、空いていると一般客もOKだったので、ここにもよく泊りました。
丁度、関西将棋会館の建設運動が始まり、大山名人が旗振り役で、永井近代将棋社社長が秘書役。それに荻山さんという方も大山名人の特別秘書をされていましたので、大山名人へのお願い事などは荻山さんを通じる事もありました。
駒づくりを楽しむ会としても、僅かながらですが、会館建設の寄付金を集めて協力しました。
会報に戻って、
4ページには竹内六郎さんからの手紙の一部を載せさ手います。
竹内六郎さんは、竹内淇洲翁のご子息です。
小生が駒作りを始めた頃、作家の倉島竹二郎さんが名人戦の観戦記の中で、「六郎さんから頂いた淇洲翁が書いた将棋の漢詩の軸を大切にしている」ことを書かれているのを読みました。
「駒づくりの勉強のため、お持ちの駒を拝見させて欲しい」と、倉島さんの鎌倉・腰越のお宅を訪ねたのがこの少し前でした。いろいろな駒を見て、駒づくりに生かしたいという思いでしたし、駒と一緒に淇洲翁の軸も拝見しました。六郎さんの住所を教えていただいたのはこのときです。
早速、六郎さんに手紙を出して、何通か頂いた返事の一部を載せさせていただいたわけです。
六郎さんは確か三菱化学に勤められていて、この頃は既に定年退職なさっていたと思います。
初めてお会いしたのは東京での作品展会場だったか、川崎のお宅だったかは忘れましたが、淇洲著「将棋漫話」や、正真正銘の「淇洲」字母紙も頂きました。
手紙は5~6回頂きました。貴重な事が記されていますので、資料として大切に保管しています。
六郎さんは、15年位前に他界されました。
なお、山形県酒田市に淇洲翁の弟子・佐藤公太郎さんを訪ねたのは、六郎さんの紹介で、この手紙をいただいた少し前です。公太郎さんが預けている竹内家家宝の真正の「淇洲駒」は、このとき本間美術館で拝見することが出来ました。
今から30年以上前のことです。
今日はここまで。おやすみなさい。
1月22日(木)、雨。
写真は小生作「鰭崎英朋書」の盛り上げ。材は「御蔵島つげ・杢」。
平成16年の作です。
さて本日は、10時過ぎ、隣の山城町にある青果市場(競り市)に出かけました。
時居り好物の筍とか、柿、トマト、メロンなどを箱単位で買うのですが、去年、梅干用の梅を買いに行ったとき、店の人から「どこから来たのか」と尋ねられました。
素人がうろちょろして邪魔なんだろうな、と思いながら「加茂駅の近く。将棋の駒を作っている」と答えたところ、「将棋は私もする」と言うのでびっくり。
以来、時々将棋を指すようになりました。
今日は家内から頼まれて「りんご」を買いに出かけたのですが、もう一つの用件もありました。
実は、あるところから「囲碁タイトル戦で使う道具を探して」とのことで、どなたか持っておられる方を探していたところです。
最近になって、青果市場の会長をされているお父さんが囲碁好きだと聞いたので、「立派な道具をお持ちなら、タイトル戦に提供されてはどうか」と、ご意向をお伺いすることもありました。
結果は、良い方向に進みそう。良かったと思っています。
午前14時、共同通信OBの小林さんら3人が来房。
このうちのお一人が例の「はらだ山荘」の依頼人。今日、初めてお会いしました。
山荘は紀伊半島の南端に近い尾鷲にあり、何んと、息子さんからのプレゼントなんだそうです。驚きましたネ。
もう一つ驚きましたのは、その方の従姉妹が、昔、勤めていた日本板硝子の同期入社の「池ちゃん」でした。(池ちゃん、といっても分かる人はほとんどいないですがネ)
世間は狭いのですね。
「一期一会」と言う言葉のように、人との出会いは大切ですネ。
もっとも「私の友達の友達が、どこそこのゲリラ」とか言った話もありますがね。
写真は小生作「鰭崎英朋書」の盛り上げ。材は「御蔵島つげ・杢」。
平成16年の作です。
さて本日は、10時過ぎ、隣の山城町にある青果市場(競り市)に出かけました。
時居り好物の筍とか、柿、トマト、メロンなどを箱単位で買うのですが、去年、梅干用の梅を買いに行ったとき、店の人から「どこから来たのか」と尋ねられました。
素人がうろちょろして邪魔なんだろうな、と思いながら「加茂駅の近く。将棋の駒を作っている」と答えたところ、「将棋は私もする」と言うのでびっくり。
以来、時々将棋を指すようになりました。
今日は家内から頼まれて「りんご」を買いに出かけたのですが、もう一つの用件もありました。
実は、あるところから「囲碁タイトル戦で使う道具を探して」とのことで、どなたか持っておられる方を探していたところです。
最近になって、青果市場の会長をされているお父さんが囲碁好きだと聞いたので、「立派な道具をお持ちなら、タイトル戦に提供されてはどうか」と、ご意向をお伺いすることもありました。
結果は、良い方向に進みそう。良かったと思っています。
午前14時、共同通信OBの小林さんら3人が来房。
このうちのお一人が例の「はらだ山荘」の依頼人。今日、初めてお会いしました。
山荘は紀伊半島の南端に近い尾鷲にあり、何んと、息子さんからのプレゼントなんだそうです。驚きましたネ。
もう一つ驚きましたのは、その方の従姉妹が、昔、勤めていた日本板硝子の同期入社の「池ちゃん」でした。(池ちゃん、といっても分かる人はほとんどいないですがネ)
世間は狭いのですね。
「一期一会」と言う言葉のように、人との出会いは大切ですネ。
もっとも「私の友達の友達が、どこそこのゲリラ」とか言った話もありますがね。
1月21日(水)、曇のち雨。
アメリカ合衆国大統領が、ニクソン否、ブッシュさんからオバマさんにチェンジしました。
オバマさんへの期待はアメリカ国民のみならず、全世界的なものなのは言うまでもありませんが、アメリカ国民の熱狂振りはうらやましい限りです。
オバマさんの就任演説は、日本のテレビ各局で実況中継していましたが、英語が分からない小生は特に見ることも無く、後で日本語に翻訳した新聞記事で全文を読みました。
ところどころ、繰り返し読んでも理解できない部分はありますが、具体的で小生にも共感できる内容が多かったように思います。
熱狂するアメリカ国民は「人民による人民のための政治」と呼びかけた、かってのリンカーン大統領の再来を感じたのでありましょう。
一方、日本国内はどうでしょうか。
昨日とその前と、ラジオで連日、国会中継を聞いておりますが、与党の質問者は「あっそう」さんに、ヨイショ・ヨイショの発言がいまだに多いのです。
見苦しい。否、聞き苦しい。真剣さに欠けて世論を無視、国民を愚弄しているとしか思えてならないのは、私だけでしょうか。
今日、アメリカの空には、希望の星が輝きはじめました。
日本の希望の星は、今、どこにいるのでしょうか。
ソレニシテモ、国会議員は多すぎます。国費の無駄遣いです。
半分にしてもまだ多いくらい。
ソレニシテモ、渡辺さんに続く[ i can ]と言う与党議員はまだおりません。
おっと、今日の仕事ですか。今日も大したことはしていません。
午前中は、手紙と木地の発送など。
午後はお客様。その後は、前回、盛り上げが済んだ「無双」の磨きでした。
明日は、共同通信の小林さんとお仲間が3人お見えになります。
アメリカ合衆国大統領が、ニクソン否、ブッシュさんからオバマさんにチェンジしました。
オバマさんへの期待はアメリカ国民のみならず、全世界的なものなのは言うまでもありませんが、アメリカ国民の熱狂振りはうらやましい限りです。
オバマさんの就任演説は、日本のテレビ各局で実況中継していましたが、英語が分からない小生は特に見ることも無く、後で日本語に翻訳した新聞記事で全文を読みました。
ところどころ、繰り返し読んでも理解できない部分はありますが、具体的で小生にも共感できる内容が多かったように思います。
熱狂するアメリカ国民は「人民による人民のための政治」と呼びかけた、かってのリンカーン大統領の再来を感じたのでありましょう。
一方、日本国内はどうでしょうか。
昨日とその前と、ラジオで連日、国会中継を聞いておりますが、与党の質問者は「あっそう」さんに、ヨイショ・ヨイショの発言がいまだに多いのです。
見苦しい。否、聞き苦しい。真剣さに欠けて世論を無視、国民を愚弄しているとしか思えてならないのは、私だけでしょうか。
今日、アメリカの空には、希望の星が輝きはじめました。
日本の希望の星は、今、どこにいるのでしょうか。
ソレニシテモ、国会議員は多すぎます。国費の無駄遣いです。
半分にしてもまだ多いくらい。
ソレニシテモ、渡辺さんに続く[ i can ]と言う与党議員はまだおりません。
おっと、今日の仕事ですか。今日も大したことはしていません。
午前中は、手紙と木地の発送など。
午後はお客様。その後は、前回、盛り上げが済んだ「無双」の磨きでした。
明日は、共同通信の小林さんとお仲間が3人お見えになります。
1月19日(月)曇時々雨。
今日は、朝から琵琶湖の畔へ出かけて、先ほど戻りました。
仕事は休みです。
たまたま、出かけた先の近くに、古い駒があるということで、拝見させていただきました。江戸時代のものです。
先に購入者を募っておりました「チェスト」は、結局23台ご注文を頂きました。
ありがとうございます。
出来上がり予定は3月上旬です。出来上がりましたら、お知らせいたします。
さて、会報は10号を見ながら解説します。
発行は昭和53年8月1日です。
冒頭は「第3回会展は中止!!」という記事。
交渉中だった名古屋の「オリエンタル中村」と、大阪の「近鉄百貨店」での開催が出来なくなったという内容です。
オリエンタル中村は、板谷進八段を通じてお願いし、2年目の近鉄百貨店は、小生が直接交渉していたのですが、ともに実現できなかった、という内容です。
いずれも百貨店としては、単位面積あたりの売上高が大きい商品を並べたいということだと思います。
渡辺汀さん(汀は「みぎわ」と読みます)が、「女王駒の誕生」を寄せておられます。
西武百貨店での作品展で、渡辺さんが、昭和52年度高校女子チャンピオンになった中瀬奈津子さんのお父さんから「王将」の裏に「女王」にした駒を頼まれて、「女王駒」が出来上がった経緯のレポートです。
この中瀬さんの名前は、若い人は知らないかもしれませんが、団塊の世代あたりの人ならご存知ですね。アマ強豪と結婚された藤森奈津子さんです。
ソレニシテモ、木村文俊さんも中瀬さんから頼まれて「女王駒」を作っていたのですね。
6ページには永井兼幸さんが「駒の著作権問題」について、結論としては、人それぞれのモラルの問題だと述べておられます。
前号に戻りますが、9号編集後記には、水無瀬神宮で「将棋馬日記」を見せられて、びっくりした時のことが書いてあります。
この「将棋馬日記」との出会いは、小生の水無瀬駒研究の原点です。
今日は、朝から琵琶湖の畔へ出かけて、先ほど戻りました。
仕事は休みです。
たまたま、出かけた先の近くに、古い駒があるということで、拝見させていただきました。江戸時代のものです。
先に購入者を募っておりました「チェスト」は、結局23台ご注文を頂きました。
ありがとうございます。
出来上がり予定は3月上旬です。出来上がりましたら、お知らせいたします。
さて、会報は10号を見ながら解説します。
発行は昭和53年8月1日です。
冒頭は「第3回会展は中止!!」という記事。
交渉中だった名古屋の「オリエンタル中村」と、大阪の「近鉄百貨店」での開催が出来なくなったという内容です。
オリエンタル中村は、板谷進八段を通じてお願いし、2年目の近鉄百貨店は、小生が直接交渉していたのですが、ともに実現できなかった、という内容です。
いずれも百貨店としては、単位面積あたりの売上高が大きい商品を並べたいということだと思います。
渡辺汀さん(汀は「みぎわ」と読みます)が、「女王駒の誕生」を寄せておられます。
西武百貨店での作品展で、渡辺さんが、昭和52年度高校女子チャンピオンになった中瀬奈津子さんのお父さんから「王将」の裏に「女王」にした駒を頼まれて、「女王駒」が出来上がった経緯のレポートです。
この中瀬さんの名前は、若い人は知らないかもしれませんが、団塊の世代あたりの人ならご存知ですね。アマ強豪と結婚された藤森奈津子さんです。
ソレニシテモ、木村文俊さんも中瀬さんから頼まれて「女王駒」を作っていたのですね。
6ページには永井兼幸さんが「駒の著作権問題」について、結論としては、人それぞれのモラルの問題だと述べておられます。
前号に戻りますが、9号編集後記には、水無瀬神宮で「将棋馬日記」を見せられて、びっくりした時のことが書いてあります。
この「将棋馬日記」との出会いは、小生の水無瀬駒研究の原点です。
1月17日(土)、晴れ。
今日は「王将戦」第1局初日です。
四日市の尾崎さんから「観戦に行きませんか」とのお誘いがあり、行きたかったのですが、定例の「駒サロン」があるので、泣く泣く断念、行けませんでした。
今日の「駒サロン」は、昭和42年に開催された「将棋400年展」の34ページほどのパンフレットのコピーを配布して解説しました。
表紙の写真を掲示しておきます。
表紙の錦絵は江戸時代後期の絵師「一勇斎国芳」の描いた版画「盤上太平棊」。駒が擬人化されている図柄です。
現品は、越智信義さんがお持ちのものだと思います。
この展では、駒が9点ほど展示されました。
①、豊島作・小野書の駒。これは小野十二世名人ではなく、小野画鵞堂の筆跡だと思います。
②、大橋宗金作・黒柿の駒。
③、関白秀次愛用の駒。
④、お城将棋の駒。
⑤、大橋宗桂(政教)作の駒。
⑥、錦旗ノ駒。これは関根名人所蔵のものではなく、木村名人所有のものです。
⑦、龍山作・関根十三世名人書の駒。これは将棋大成会記念の駒です。
⑧、奥野作・日下部鳴鶴書の駒。
⑨、坂田三吉愛用の駒。
「駒サロン」を終わって、田中さんたちと近くの居酒屋で小一時間。
17時ごろから福島へ移動。書道具屋で筆と印肉を買い求めて後、林田さん・橋本さんたちが待つ「虎の穴」に。
加茂への帰着、23時。
気になっていた王将戦。中継で確認したところ進行が早いようですネ。
盤上の駒はロングショットでもう一つはっきりしませんが、どうやら見慣れたもののようです。
明日、確かめに行こうかとも思っているところです。
今日は「王将戦」第1局初日です。
四日市の尾崎さんから「観戦に行きませんか」とのお誘いがあり、行きたかったのですが、定例の「駒サロン」があるので、泣く泣く断念、行けませんでした。
今日の「駒サロン」は、昭和42年に開催された「将棋400年展」の34ページほどのパンフレットのコピーを配布して解説しました。
表紙の写真を掲示しておきます。
表紙の錦絵は江戸時代後期の絵師「一勇斎国芳」の描いた版画「盤上太平棊」。駒が擬人化されている図柄です。
現品は、越智信義さんがお持ちのものだと思います。
この展では、駒が9点ほど展示されました。
①、豊島作・小野書の駒。これは小野十二世名人ではなく、小野画鵞堂の筆跡だと思います。
②、大橋宗金作・黒柿の駒。
③、関白秀次愛用の駒。
④、お城将棋の駒。
⑤、大橋宗桂(政教)作の駒。
⑥、錦旗ノ駒。これは関根名人所蔵のものではなく、木村名人所有のものです。
⑦、龍山作・関根十三世名人書の駒。これは将棋大成会記念の駒です。
⑧、奥野作・日下部鳴鶴書の駒。
⑨、坂田三吉愛用の駒。
「駒サロン」を終わって、田中さんたちと近くの居酒屋で小一時間。
17時ごろから福島へ移動。書道具屋で筆と印肉を買い求めて後、林田さん・橋本さんたちが待つ「虎の穴」に。
加茂への帰着、23時。
気になっていた王将戦。中継で確認したところ進行が早いようですネ。
盤上の駒はロングショットでもう一つはっきりしませんが、どうやら見慣れたもののようです。
明日、確かめに行こうかとも思っているところです。
1月16日(金)、大体は晴れ。
本日は「錦旗」の盛り上げ。昨年の秋に2組を彫り始めて、彫り埋めの状態にまでにしていたものです。
ところで14年前、平成7年の今日は確か月曜日だったと思います。
以下は、明日書いても良かったのですが、明日は「駒サロン」がありますので、
今日書くことにします。
この年は、成人の日の15日が日曜日、16日が振り替え休日でした。
当時小生は52歳。まだ、日本板硝子のコンピューター部門で勤務していましたが、3月末を以って退職する日が、2ヶ月余りに迫っていました。
週明け17日(火)に会議があるので、16日夕方に上京して、大井町の新阪急ホテルの10階あたりに宿泊しておりました。22時頃には就寝したと思います。
いつものとおり、窓の厚いカーテンは閉めません。これは朝寝坊しない工夫です。
朝の光が部屋いっぱいに差し込めば、自然に目が覚めます。
ここまでは、特に変わったところはありません。
おやっと思ったのは、翌朝目が覚めて間もない5時45分頃でした。
横になったまま、ボヤーっとNHKテレビを見ていたとき、部屋が「ミシミシ」と僅かにですが、音を立てました。
直感的に「安普請なホテルだなあ」と思いました。
丁度、太陽が昇る時間帯でした。太陽の熱で外壁の金属が膨張して、音を鳴らした。そう直感したのでした。
ところが、暫くするとテレビの様子がいつもと違うのです。細かくは良く覚えていませんが、
「只今、琵琶湖付近の名神高速道路が通行止めになりました」とのことです。
事故でもあったのかなあ、と思っていると、「先ほど、京都で大きな地震がありました」。
「ホーっ」と思って聞いていると、画面では、京都放送局内のゆれる様子が映し出され、少しすると、大阪放送局の様子も流れたように思います。
関西地方で、大地震が起きたことは分かりました。
暫くテレビの画面に釘付けでしたが、それ以上のことは良く分からないままでした。
やがて朝食をとり、浜松町の東京本社に出勤しました。
9時からの会議にはまだ時間があるので、大阪本社に電話を掛ける。誰も出ない。
奈良の家に電話すると、大きな揺れだったが、被害は無いらしいということで、小生は一安心しました。
「神戸がものすごい。ビルが横倒しになっている」と分かったのは、それからだいぶ経ってからの昼近くでした。
あれから14年。ソレニシテモ、早朝の5時45分ごろのホテルの「ミシミシ」。あれは神戸淡路大地震の音だったのですネ。間違いありません。
500キロメートル隔てても、あの音を聞いていたのです。
あの日から1年以上は、神戸方面には行きませんでした。
テレビでは眼にはしても、実際の姿を直視するのは出来なかった。逃げていたんですね。
あの大地震で亡くなったり、住む家がつぶれたりしているのを現地で直視するのが怖かったのですネ。
本日は「錦旗」の盛り上げ。昨年の秋に2組を彫り始めて、彫り埋めの状態にまでにしていたものです。
ところで14年前、平成7年の今日は確か月曜日だったと思います。
以下は、明日書いても良かったのですが、明日は「駒サロン」がありますので、
今日書くことにします。
この年は、成人の日の15日が日曜日、16日が振り替え休日でした。
当時小生は52歳。まだ、日本板硝子のコンピューター部門で勤務していましたが、3月末を以って退職する日が、2ヶ月余りに迫っていました。
週明け17日(火)に会議があるので、16日夕方に上京して、大井町の新阪急ホテルの10階あたりに宿泊しておりました。22時頃には就寝したと思います。
いつものとおり、窓の厚いカーテンは閉めません。これは朝寝坊しない工夫です。
朝の光が部屋いっぱいに差し込めば、自然に目が覚めます。
ここまでは、特に変わったところはありません。
おやっと思ったのは、翌朝目が覚めて間もない5時45分頃でした。
横になったまま、ボヤーっとNHKテレビを見ていたとき、部屋が「ミシミシ」と僅かにですが、音を立てました。
直感的に「安普請なホテルだなあ」と思いました。
丁度、太陽が昇る時間帯でした。太陽の熱で外壁の金属が膨張して、音を鳴らした。そう直感したのでした。
ところが、暫くするとテレビの様子がいつもと違うのです。細かくは良く覚えていませんが、
「只今、琵琶湖付近の名神高速道路が通行止めになりました」とのことです。
事故でもあったのかなあ、と思っていると、「先ほど、京都で大きな地震がありました」。
「ホーっ」と思って聞いていると、画面では、京都放送局内のゆれる様子が映し出され、少しすると、大阪放送局の様子も流れたように思います。
関西地方で、大地震が起きたことは分かりました。
暫くテレビの画面に釘付けでしたが、それ以上のことは良く分からないままでした。
やがて朝食をとり、浜松町の東京本社に出勤しました。
9時からの会議にはまだ時間があるので、大阪本社に電話を掛ける。誰も出ない。
奈良の家に電話すると、大きな揺れだったが、被害は無いらしいということで、小生は一安心しました。
「神戸がものすごい。ビルが横倒しになっている」と分かったのは、それからだいぶ経ってからの昼近くでした。
あれから14年。ソレニシテモ、早朝の5時45分ごろのホテルの「ミシミシ」。あれは神戸淡路大地震の音だったのですネ。間違いありません。
500キロメートル隔てても、あの音を聞いていたのです。
あの日から1年以上は、神戸方面には行きませんでした。
テレビでは眼にはしても、実際の姿を直視するのは出来なかった。逃げていたんですね。
あの大地震で亡くなったり、住む家がつぶれたりしているのを現地で直視するのが怖かったのですネ。
1月15日(木)、大体晴れ。
9時過ぎ、使っていた木地を成型する機械に異音が発生。機械といっても、30年ほど前に小生が設計して知り合いの機械屋さんに発注した比較的小型の切削機です。
機械には切削した木屑がびっしり。その粉がモーターとかベアリングの隙間に入り込んで、異音が発生していることは、容易に判断ができます。
だが、ゴーっと言う異音は、モーターからか、ベルトで動かしているシャフトのベアリングからか判断がつかないので、モーター部分を取り外すことに。
つまり、モーターを取り外して電気を流すと、モーターだけが回転する。
このとき、異音が出るか出ないかで、問題の箇所を切り分けることが出来ます。
結果は、モーターが問題とわかりました。
モーターは、O社製の密閉構造。密閉構造といっても、軸の部分は何十ミクロン程度の僅かな隙間があるので、その隙間から中にあるベアリングの部分に木粉が入り込んで悪さをしているようだ。
30年も順調に働いてくれた機械です。木屑が取り除ければよいが、場合によってはモーターを取り替えねば。30年前と同じモーターを製造しているだろうか。いずれにしても、数日は機械が使えなくなるかも、などとの思いが頭をよぎります。
さてどうするかですが、こんなときに威力を出すのが「フッ素ガス」のスプレイ。確か、どこかにあることを思いだして、早速モーターの軸周りの隙間に向かって、シューっと吹き付けることに。
シューっとやってはモーターを廻す。これを5回10回と繰り返すと、段々異音が和らいで、軽やかな回転音に戻ってきました。
これなら、モーターを取り替えずにokです。幸運でした。
元にとおりに組み立てて、作業は終了。11時少し前でした。
18時から、奈良の樽井さんのところで、「KOM」の新年会。樽井さんは奈良漆器の塗師です。
集まった連中は、赤膚焼きの尾西さん、西さん、筆の萬谷さん、仏師の佐野さん、鹿角細工の畑里さん、一刀彫の土井さん、それに今回から若い木工の岡林さん。
春日の岡本さんは所用で欠席です。
会の途中から「面白い人がいる」と言うことで、寮美千子さんという作家夫婦を呼んで、わいわいがやがや。寮さん夫婦は、2年前に東京から奈良に移り住んで、作家活動をしている変わり種。何でも最近、泉鏡花文学賞を受賞したそうです。
日にちが変わりました。寝ることにします。
9時過ぎ、使っていた木地を成型する機械に異音が発生。機械といっても、30年ほど前に小生が設計して知り合いの機械屋さんに発注した比較的小型の切削機です。
機械には切削した木屑がびっしり。その粉がモーターとかベアリングの隙間に入り込んで、異音が発生していることは、容易に判断ができます。
だが、ゴーっと言う異音は、モーターからか、ベルトで動かしているシャフトのベアリングからか判断がつかないので、モーター部分を取り外すことに。
つまり、モーターを取り外して電気を流すと、モーターだけが回転する。
このとき、異音が出るか出ないかで、問題の箇所を切り分けることが出来ます。
結果は、モーターが問題とわかりました。
モーターは、O社製の密閉構造。密閉構造といっても、軸の部分は何十ミクロン程度の僅かな隙間があるので、その隙間から中にあるベアリングの部分に木粉が入り込んで悪さをしているようだ。
30年も順調に働いてくれた機械です。木屑が取り除ければよいが、場合によってはモーターを取り替えねば。30年前と同じモーターを製造しているだろうか。いずれにしても、数日は機械が使えなくなるかも、などとの思いが頭をよぎります。
さてどうするかですが、こんなときに威力を出すのが「フッ素ガス」のスプレイ。確か、どこかにあることを思いだして、早速モーターの軸周りの隙間に向かって、シューっと吹き付けることに。
シューっとやってはモーターを廻す。これを5回10回と繰り返すと、段々異音が和らいで、軽やかな回転音に戻ってきました。
これなら、モーターを取り替えずにokです。幸運でした。
元にとおりに組み立てて、作業は終了。11時少し前でした。
18時から、奈良の樽井さんのところで、「KOM」の新年会。樽井さんは奈良漆器の塗師です。
集まった連中は、赤膚焼きの尾西さん、西さん、筆の萬谷さん、仏師の佐野さん、鹿角細工の畑里さん、一刀彫の土井さん、それに今回から若い木工の岡林さん。
春日の岡本さんは所用で欠席です。
会の途中から「面白い人がいる」と言うことで、寮美千子さんという作家夫婦を呼んで、わいわいがやがや。寮さん夫婦は、2年前に東京から奈良に移り住んで、作家活動をしている変わり種。何でも最近、泉鏡花文学賞を受賞したそうです。
日にちが変わりました。寝ることにします。
1月14日(水)、晴れのち曇一時雨。
8時頃の気温は氷点下1度。夜来の雪は止んでいましたが、強い冷え込みでした。
皆様の所は、どうでしたか。
今日の会報は9号。6月1日の発行です。
前号の発行日が3月1日で、間隔が3ヶ月に広がっていますネ。この頃から段々ネタ切れ気味で、何を書こうかと悩んだり、2ヶ月毎に発行するのが、大変シンドかったという記憶があります。
今号では、東大阪市の米田嘉重さんが2ページにわたって「字母紙の貼り方」について研究発表してくれました。このように、投稿原稿があると大変助かりました。
しかし、残りのページを埋めるのは大変でした。
一刻も早く皆に届けなければと、気はあせるし、時には学校の試験勉強でもやったことが無い徹夜で原稿作りもしました。
印刷は、会社の業務で取引のある東洋紙業さんの子会社に依頼しました。
会報の発送以下の雑用は、封筒の宛名書き、封入、切手貼りを含め自分でやりました。ですから、会員の名前(姓名)と住所の町名あたりまでは、大体憶えることができました。
余談ですが、「紙」の作業は、得意でした。
19歳上の兄の仕事が「紙」で、子供の頃、良く手伝いました。ですから、紙を数えるとか、折るとか「紙」の取り扱いは、実はプロ並みです。
例えば、紙を数える方法です。
新聞紙ほどの大きさの紙が10000枚ほどあるとします。
普通の厚みなら、大体1メートルの高さ。基本作業は、先ずこれを100枚ずつに正確に分けることです。
先ず左手の肘とか腕で、紙の山がずれないように軽く押さえながら、右手の親指と人差し指で紙束の端を一つまみして、これを捻じりながら起こします。
そうすると、紙の1枚1枚の端が等間隔になって立ち上がります。
これを5枚ずつをブロックにして、左手の親指の腹で軽く押さえるようにして、残った指で区切りながら、これを20回繰り返せば100枚です。
5枚ずつ数える速さは、1秒間に2回から3回。5枚は数えるのではなく、指先の感覚。100枚で20秒。10000枚なら30分あれば良いわけです。
ところで、紙のプロの凄さはその指の感覚なのです。
数を数えなくても、数が指で分かるのです。
将棋でプロは、「読む凄さ」もありますが、「読まない凄さ」もそなえていますね。
同じ厚みの紙を、500枚くらい読み進むと、右手の親指と人差し指で、ぱっと、一摘みすると、100枚きっちり摘めるようになります。
これは、子供の頃に経験しています。
人間の指の感覚は、凄いのです。
寿司屋が、一摘みするす飯の米粒、これも調子が乗ると、数がきっちり揃うという話を聞いたことがありますが、同じことなのですね。
と言うことで、本日はこれまで。
8時頃の気温は氷点下1度。夜来の雪は止んでいましたが、強い冷え込みでした。
皆様の所は、どうでしたか。
今日の会報は9号。6月1日の発行です。
前号の発行日が3月1日で、間隔が3ヶ月に広がっていますネ。この頃から段々ネタ切れ気味で、何を書こうかと悩んだり、2ヶ月毎に発行するのが、大変シンドかったという記憶があります。
今号では、東大阪市の米田嘉重さんが2ページにわたって「字母紙の貼り方」について研究発表してくれました。このように、投稿原稿があると大変助かりました。
しかし、残りのページを埋めるのは大変でした。
一刻も早く皆に届けなければと、気はあせるし、時には学校の試験勉強でもやったことが無い徹夜で原稿作りもしました。
印刷は、会社の業務で取引のある東洋紙業さんの子会社に依頼しました。
会報の発送以下の雑用は、封筒の宛名書き、封入、切手貼りを含め自分でやりました。ですから、会員の名前(姓名)と住所の町名あたりまでは、大体憶えることができました。
余談ですが、「紙」の作業は、得意でした。
19歳上の兄の仕事が「紙」で、子供の頃、良く手伝いました。ですから、紙を数えるとか、折るとか「紙」の取り扱いは、実はプロ並みです。
例えば、紙を数える方法です。
新聞紙ほどの大きさの紙が10000枚ほどあるとします。
普通の厚みなら、大体1メートルの高さ。基本作業は、先ずこれを100枚ずつに正確に分けることです。
先ず左手の肘とか腕で、紙の山がずれないように軽く押さえながら、右手の親指と人差し指で紙束の端を一つまみして、これを捻じりながら起こします。
そうすると、紙の1枚1枚の端が等間隔になって立ち上がります。
これを5枚ずつをブロックにして、左手の親指の腹で軽く押さえるようにして、残った指で区切りながら、これを20回繰り返せば100枚です。
5枚ずつ数える速さは、1秒間に2回から3回。5枚は数えるのではなく、指先の感覚。100枚で20秒。10000枚なら30分あれば良いわけです。
ところで、紙のプロの凄さはその指の感覚なのです。
数を数えなくても、数が指で分かるのです。
将棋でプロは、「読む凄さ」もありますが、「読まない凄さ」もそなえていますね。
同じ厚みの紙を、500枚くらい読み進むと、右手の親指と人差し指で、ぱっと、一摘みすると、100枚きっちり摘めるようになります。
これは、子供の頃に経験しています。
人間の指の感覚は、凄いのです。
寿司屋が、一摘みするす飯の米粒、これも調子が乗ると、数がきっちり揃うという話を聞いたことがありますが、同じことなのですね。
と言うことで、本日はこれまで。
1月13日(火)、曇一時雨。
写真は、新作の「無双」です。
材は御蔵島ツゲの杢。山川さんという木地師から11年前に駒形で仕入れてストックしていたものを駒に仕立てました。
午後、荒川君から電話がありました。昨日、少し触れた中学2年生です。
「日本の伝統文化を勉強する」ことが、生徒全員に課せられての京都訪問なのだそうだ。
どんな中学2年生か。声の主の人物像を想像しながら話を聞きました。
遠慮がちな会話の中から、とに角将棋が好きで、近代将棋を通じて小生のことはある程度知っているとのことが分かりました。
生徒のそれぞれが自分なりの目的を決めて京都に来る。荒川君は「駒と駒づくり」。他の生徒にも声をかけているが、今のところ、一人だとのこと。
「それでもいいですよ。朝8時30分頃京都を発てば、工房には10時ころですね」。
そんな会話をしながら、カレンダーの3月4日に「荒川君」と記入しました。
写真は、新作の「無双」です。
材は御蔵島ツゲの杢。山川さんという木地師から11年前に駒形で仕入れてストックしていたものを駒に仕立てました。
午後、荒川君から電話がありました。昨日、少し触れた中学2年生です。
「日本の伝統文化を勉強する」ことが、生徒全員に課せられての京都訪問なのだそうだ。
どんな中学2年生か。声の主の人物像を想像しながら話を聞きました。
遠慮がちな会話の中から、とに角将棋が好きで、近代将棋を通じて小生のことはある程度知っているとのことが分かりました。
生徒のそれぞれが自分なりの目的を決めて京都に来る。荒川君は「駒と駒づくり」。他の生徒にも声をかけているが、今のところ、一人だとのこと。
「それでもいいですよ。朝8時30分頃京都を発てば、工房には10時ころですね」。
そんな会話をしながら、カレンダーの3月4日に「荒川君」と記入しました。
水無瀬兼成卿の読み方について、質問がありましたのでお答えします。
読み方は「みなせかねなり」か「みなせかねしげ」かですが、小生は、分かりやすい読み方「かねなり」といっておりますが、30年余り前、先代の宮司・忠寿さんにお訊ねしました。
答えは「分からない」そうです。
なお、ご長男で現在の宮司・忠成さんは「ただしげ」と読みます。
駒の写真集
リンク先はこちら」
http://blog.goo.ne.jp/photo/11726