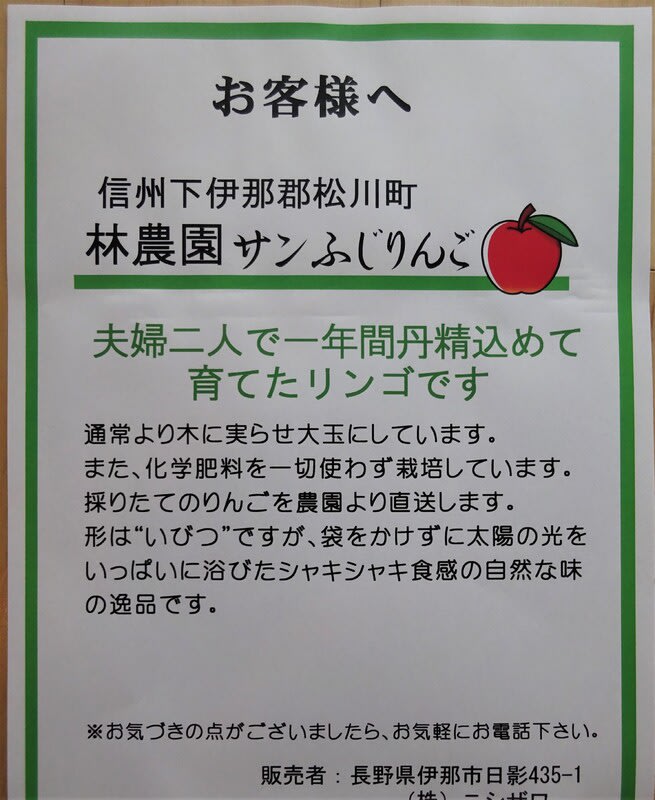今の時代とは、「男らしい」「女らしい」なる言葉すら死語化していると日頃感じている原左都子だ。
そんな私は先程、2021.11.22付 朝日新聞紙上にて時代錯誤も甚だしいと驚くべく記事を発見した。
その題目は、「『男らしさ』『女らしさ』あなたの意識は」なのだが。
別に見なかったことにして放置しておけばよいのだが…
取り上げた以上、不本意ながら以下に本文を要約引用しよう。
女性の社会進出の妨げになっている潜在的価値観に光をあてるのが狙いで、「結婚相手探しに苦労するため、女性は東大へ進学すべきでない」といった質問を入れたのが特徴。 伝統的な性別役割分担や家父長制度などの意識をみる質問も加えた。 「とてもそう思う」が1点、「全くそう思わない」が4点で32点満点。 合格点が低いほど保守的な考え方であることを示す。
昨年3月、調査会社に登録した全国の男女約2400人を対象に調べたところ、平均は男性が14.73点、女性16.01点で、統計的に意味のある差がついた。
(以下略すが、以上朝日新聞記事より一部を引用したもの。)
原左都子自身も、この意識調査に回答してみたが。
10問の問いに答えた結果、すべてが「全くそう思わない」に該当して、32点満点だった。
私の観点で、特筆するべき質問に関してピックアップしてみよう。
② 女性の幸せは、仕事での成功に左右されない。
ちょっと待ってよ。 私の人生など、それを目指してあえて婚期を遅くしたようなものであり、実際、仕事での成功を勝ちとった結果の「成功感」が強い人間だ。
⑤ 結婚相手探しに苦労するため、女性は東京大学へ進学するべきでない。
一体どうしたというの?? いつの時代の話かと呆れるばかりだ。 今時、東大卒の女性など世にわんさか存在するだろうし、おそらく“引く手あまた”じゃないかな?
⑥ 高学歴は、女性がよいパートナーを見つけることの障害になる。
これまた、とんでもない時代錯誤感覚だ。 私自身が「見合い結婚」だが、今時の見合い結婚とは、学歴や職歴で釣り合うことが必須条件であるとの印象を、我が身を振り返って持っている。 お陰で、私は高学歴、専門職種の相手と巡り会えている。
⑦ キャリアは、女性がよいパートナーを見つけることの障害となる。
問⑥同様に、とんでもない時代錯誤的思考であろう。 むしろ今の時代は、女性とてキャリアも良きパートナーを見つけるに際して重要要件であろう。
⑧ 妻は夫に意見するべきではない。
あり得ないなあ。 日々夫婦で意見交換をすることにより、家庭とは健全に築かれていくものだよ。
原左都子として、多少迷った質問もある。
③ 妻は夫の3歩後ろをあるくべきという考えに共感する。
これに関しては、あえてそうした方が夫婦仲が良好に保たれるかと計算することはあるなあ。 実際は後ろを歩く訳ではないが、妻側のその演技が一家を支えることはありか、とも思う。
(これって、結局は妻側が優位な地位にある証ともいえるよね。)
④ 女性の外見は、知性よりも重要である。
「外見を繕う」こととは、私に言わせてもらうと“一趣味”の位置づけであろう。 「知性」と「外見」を同一線上に並べる必要もなければ、「外見」を繕ったから「知性」が疎かになることもあり得ないよ。
今回のエッセイの最後に。
「男らしさ」「女らしさ」についての意識を、数値で示す方法を思いついたらしき学者先生に申し上げたいが。
本心から「女性が自由に羽ばたける社会になって欲しい」と望んでおられるのならば。
ご自身の意識改革から、やり直されては如何だろうか??